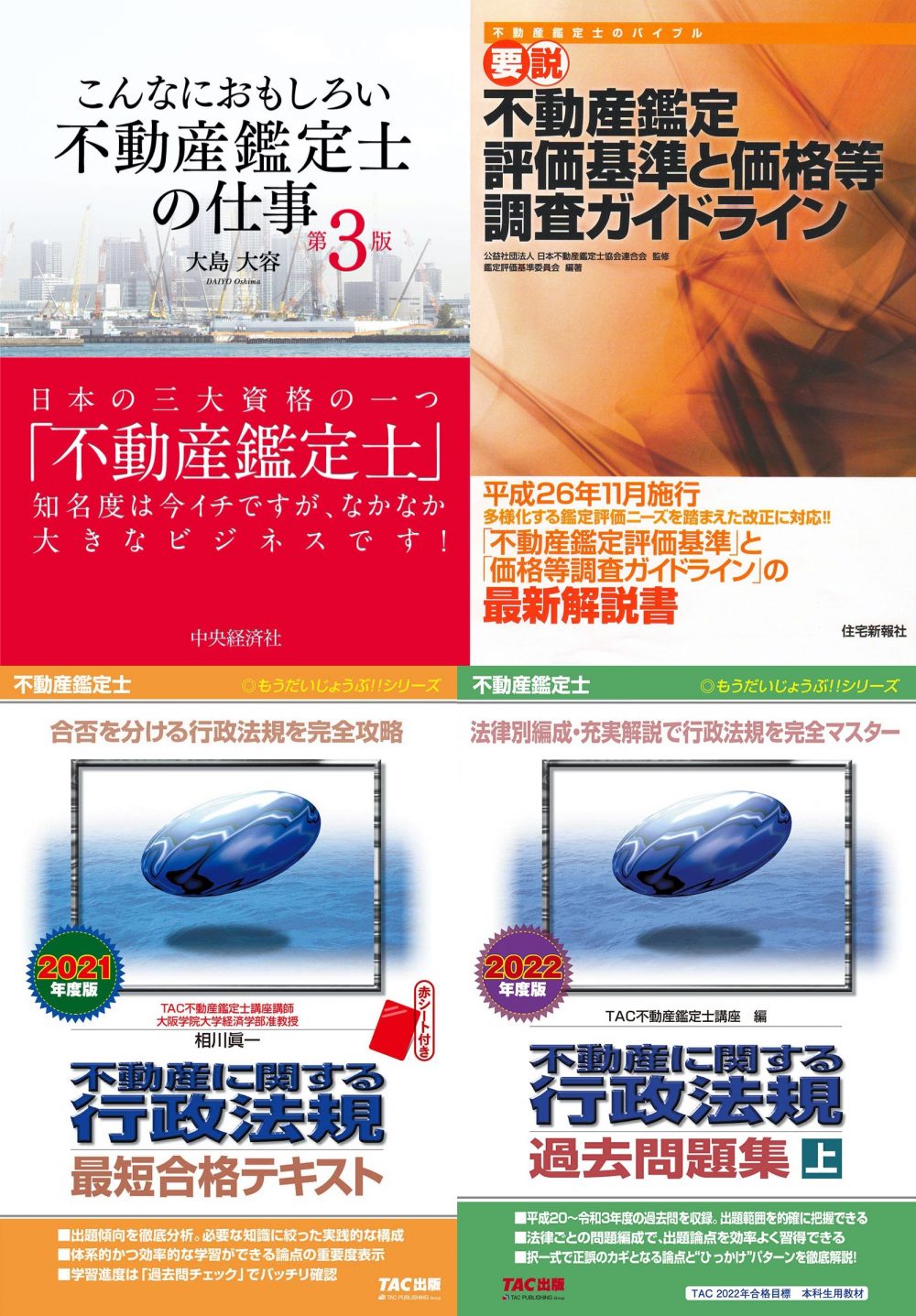不動産鑑定士は将来性や需要がある?資格がなくなる可能性はあるのか?
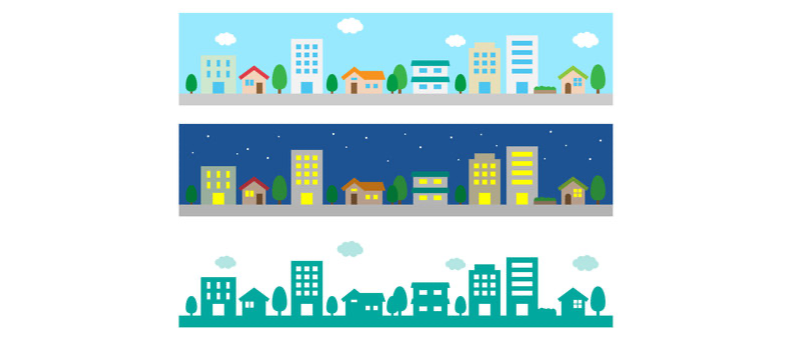
不動産鑑定士は、不動産の鑑定業務とコンサルティング業務を行う、不動産の評価に関する専門家です。不動産の鑑定は独占業務で、公的評価の業務が割合として多いとされています。
不動産鑑定士は市場の規模の小ささや業務がAI(人工知能)に代替されるという懸念から、将来性がないと感じる関係者もいるようです。そこで今回は、不動産鑑定士の将来性について取り上げていきたいと思います。
不動産鑑定士の将来性がないと言われる理由
不動産鑑定士という資格には、将来性がないと言われることがあります。
その理由は、
・市場の規模が小さく、需要が少ない
・業務が定型的で、AI(人工知能)に代替されやすいと考える人が多い
・公的評価業務の受注は、ベテランの鑑定士に取られていることが多い
・業界の新陳代謝が無く、人間関係が狭いために人を選ぶケースが多い
といったものがあります。
市場の規模が小さいことは事実で、不動産鑑定士の有資格者は全国で8,000人程度と少ないにもかかわらず、公的評価業務で人手不足に陥っていることはあまりないようです。
ただし、若手の不動産鑑定士の人材獲得合戦が起きている、という記事があるように、若年層の不動産鑑定士を雇いたい事務所やアセットマネジメント会社も存在しています。
過度な悲観は必要ないように思えます。
AIに代替される懸念については、実際の業務は確かにAIの活用が進められるでしょう。
一方で、不動産は利害関係が複雑に絡まる場合が多く、鑑定の妥当性を担保するために、第三者の立場からの検証も求められる可能性があると思います。そのため、全体的な業務は減るものの、不動産鑑定に関連する仕事が全て無くなるわけではない、という流れになる可能性が高いかもしれません。
現状の業界の構造の問題は、時間が経過することで改善される点もあるでしょう。しかし、既得権益になりやすい構造を変えない限り、繰り返される懸念は残ります。
こうした問題は、国土交通省の政策次第であるので、行政の動向を見ておいた方が良さそうです。
不動産鑑定業界は政策に左右されやすい
不動産鑑定の業界は、政府や地方公共団体の政策に大きく影響を受けます。公共工事の数と公的評価業務の数が連動していることが主要な理由です。また、不動産は規制が多い業界であるため、業務内容や業界の環境も政策の変更によって変わることになります。この点は意識しておく必要があるでしょう。
不動産鑑定士の需要は一定程度ある
不動産鑑定業界は、政策によって状況が左右されますが、鑑定業務には一定の需要があることは確かです。REITの普及が推進されていることによって、金融機関での不動産鑑定士の需要が生まれていたり、不動産の効果的な活用に着目され始めたことにより、コンサルティング業務の開拓が検討されていることも考慮した方が良いでしょう。
ただ、REIT関連業務以外の民間業務はまだまだ少ないようです。今後コンサルティング業務が増えるかはわかりませんが、鑑定業務の需要は現時点でも一定水準はあります。
まとめ
全体的に、悲観的な意見が多い不動産鑑定士ですが、取得して無駄になる資格ではありません。不動産の評価方法や法律といった専門知識を身につけることは、将来にわたってプラスになるでしょう。
REITの普及や海外からの国内不動産への投資の活発化といった追い風となる出来事もあり、悲観的になりすぎる必要性はあまりないと思います。ただ、業務効率化や商品の複雑化によって、人材の選別が行われていく可能性も出てくるかもしれません。
不動産鑑定士として活躍できる機会はゼロにはなりにくいと思いますので、不動産鑑定業界で働きたいのであれば、取得して、不動産鑑定士として働くことがおすすめです。