一般気象学 第2版補訂版
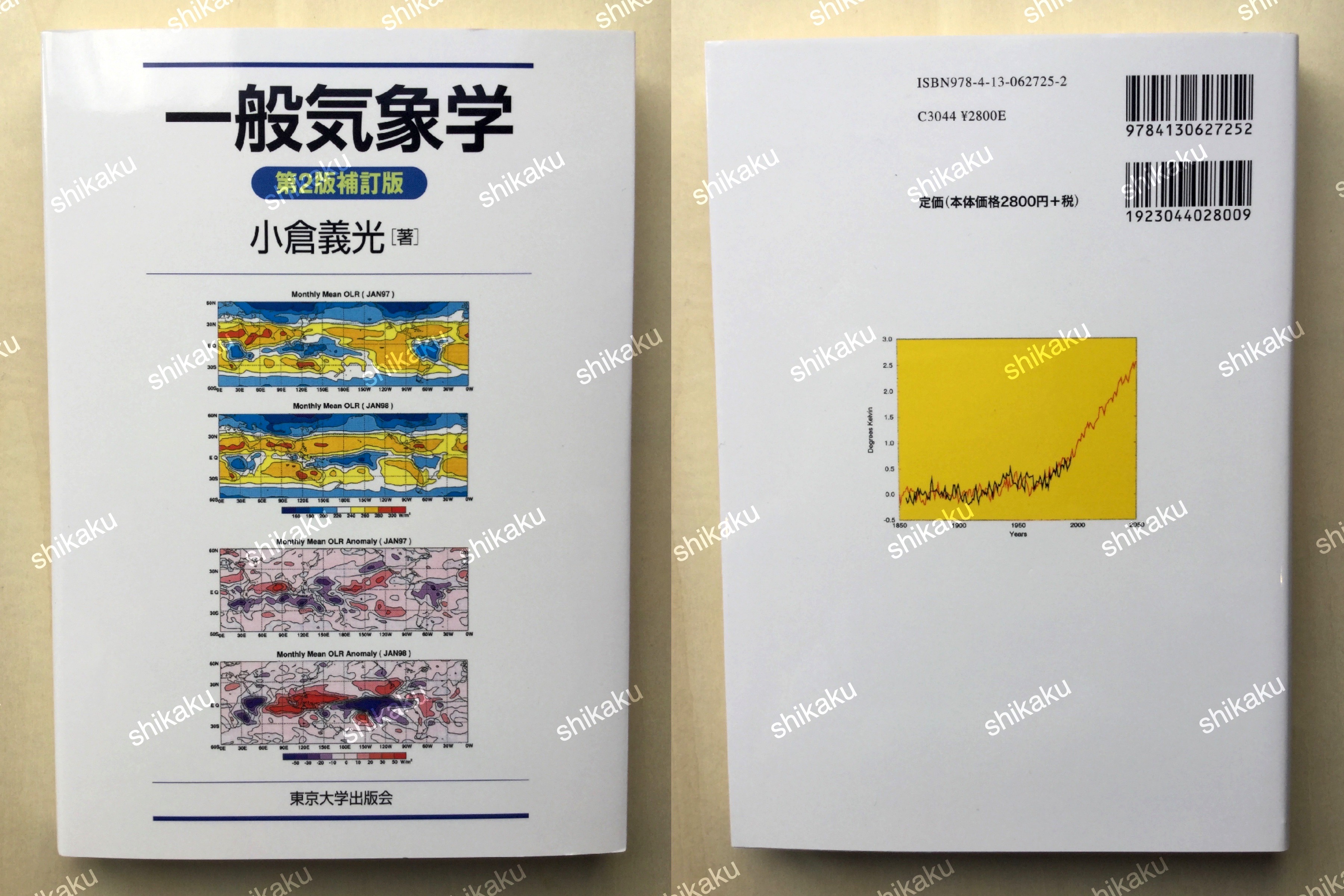
【気象予報士試験のおすすめ参考書・テキスト(独学勉強法/対策)】も確認する
第2版 まえがき
本書の旧版が出版されてからちょうど15年,幸いにも予想以上の好評をもって読者に迎えられ,今日までに22刷を数えた.
これは著者としてはたいへんにうれしいことであるが,また同時に大きな責任のようなものも感じている.この15年間に気象学は大きく進歩した。もともと本書の目的は気象学の研究の最前線を紹介することではなく,基本的な法則や考え方をできるだけていねいに解説することであるが,それでも気象学の関心の重点が時代とともに変わるということはある.また気象学の知識が普及するにつれて,かつては専門的と思われていた知識がいまや本書で扱うのが適当な一般的知識とされている部分もある。さらに基本的な事柄の具体例としてあげた事例でも,歴史的なものを除けば、できるだけ記憶に新しい最近のものが望ましい。
このような事情から今回第2版を出版することとなった.改定に当っては,旧版を実際に教室で教科書として使用してくださったと思われる数十人の方々に、どのような改定が望ましいかご意見を伺った。また私自身の新しい体験として,気象大学校の研修部予報課程の講師を7年間勤めたし,1994年に新しい国家資格「気象予報士」制度が発足してから4年間,試験委員長として計9回試験問題の作成と各問題の正解率の観察などに関わった。こうした経験も第2版の執筆に役立った。このような機会を与えてくださった方々に感謝したい.
結局この第2版では、基本的な性格や記述のレベルは旧版と全く変わらない.章立ても,第8章を「中・小規模の運動」から「メソスケールの気象」とした以外は全く同じである。内容が大きく変わったのは序章と第8章と第10章(気候の変動)である。その他いくつかの章で,主に後半部分に追加や改定などがある.たとえば第6章では、要望に応じて大気境界層の記述が少し詳しくなっている。
とはいえ,第2版の執筆に当っては最新の知見を取り入れたので,実質的には分量が約15%増えている。もともと本書は教科書としては例外的に図の数が多かったが,この第2版ではさらに増加して,約200の図がある.こうした増加にもかかわらず,旧版から引き続いて企画編集を担当された東京大学出版会の清水恵さんは,本文の組み方を変えたり,図の入れ方などを工夫するなどして,旧版とほとんど同じ総ページ数でまとめてくださった.
旧版の執筆のさいには多くの友人や同僚の方々から多大のご援助を頂いた.
この第2版でも,上に述べたように改定の方向を決めるのに多くの方からの懇切なご意見に導かれたこと,また多くの有益なコメントを頂いたことを記して,厚く感謝の意を表したい.図の提供や転載の許可をしてくださった方々にも厚くお礼を申し上げたい.
旧版に劣らず,本書が若い人たちに気象学を学ぶ楽しさを呼び起こすのに私立てば,私にとってこれ以上の喜びはない.1999年春小倉 義光
近年新聞やテレビなどのマスメディアで地球温暖化など大気環境の変化を報じる記事が多くなってきている.この問題は重要であり,本書では主に第10章(気候の変動)の前半で解説しているが,第2版1刷の出版以来すでに17年が過ぎているので,今回(補訂版)この部分を改定した.また,近年多くの人工衛星が太陽系の諸惑星を探索していることを反映して,第1章(太陽系の中の地球)で僅かながら変更した部分がある.2016年立春一般気象学 第2版補訂版
初版 はしがき
この本は大学の教養課程ではじめて気象学を学ぶ人の教科書として書かれたものである。だから予備知識としては高等学校卒業程度の物理学と数学で十分である.式が出てくるが,注釈の部分を除けば、すべて代数方程式である。
この本の基礎となった材料はイリノイ大学の大気科学教室の教官がやはり教養課程の学生の選択科目として毎年講義をしてきたものである。なかなか人気があり,毎学期多くの学生がこの講義をとっている。そのなかには将来気象学を専攻しようとする学生もいるが,それはほんの少数である。ほとんどすべての学生はハイスクールや大学初年程度で習った物理学の原理法則が身近な大気中の現象にどう応用されているかという知的好奇心を満足するため、あるいは子供のころから毎日の天気予報や気象現象に興味をもち,それをより深く学びたいと思っているか,あるいは自分の将来の職業に気象が直接間接に関連がありそうだから,大学在学中に気象学をひととおり勉強しておこうなど,その動機はさまざまである。
それで所属している学部も,理・工・農が大部分であるが,社会科学・教育・文科系の学部の学生も少なからずいる。実際私たちの社会が高度に複雑化されるにつれ、私たちの生活は日々の天気変化のみならず,気象災害,凶作,大気環境,気候変動などに大きく左右される。気象学の入門講座を選択科目としてとる学生数が多いわけである。
教室で実際に授業をすると、講義のどの部分で学生諸君が退屈するか,どの部分で理解が困難であったか,かなりよくわかる。このことは教科書を書くさいに役に立つが、この本はわが国の大学の教養課程の教科書として適切であるように,全く新たに書き下したものである。これは単に米国付近の天気図をわが国付近の天気図に置き換えるということに留まらない、イリノイ大学での講義は1学期約42時間ある。
わが国の大学の教養課程で気象学にこれだけの時間をさいている大学は稀であろう。たいていはもっと広義の地球科学の一部として気象学の話をするか,10時間足らずの集中講義ですませてしまうそうした場合にもこの本を教科書として使用していただいたとすれば,この本の大部分は教室外の独学ということになる。そのときにもこの本をできるだけ楽しく読めるように、ふつうの教科書とは少し形態を変えて書いた。1つは記述が無味乾燥でないように多少読み物的な要素を入れたことである。
もう1つは、すべてのことをもれなく記述するというよりは、記述された項目はできるだけ理解しやすいように,つまり基本的な法則から出発して説明をていねいにしていくようにしたことである。また多くの図を入れた。それは、概念的な説明図はもちろん理解を助けるのに必要であるが,実際に雨や雪が降り集中豪雨や雷雨か襲っているときの大気がどんな状態にあるのか、その臨場感を伝えたかったからである.このため図の数は当初に予定されたものの倍近くにもなってしまった.それに快く協力してくださった東京大学出版会に敬意を表したい。さらに図の転載を許可してくださった出版社・原著者の方々に心より感謝したい。
この本の原稿の大部分は1982年から83年にかけて,東京大学の海洋研究所の潜在中に執筆したものである。気象学の最近の進歩は目ざましく、その全貌とはいわなくても、重要な領域を1人で書くことは予想以上に困難であった。幸いにも多くのすぐれた友人に囲まれていたので、とにかくここまで書きあげることができた。滞在中ほとんど毎日顔を合わせていた海洋研究所の浅井富雄教授と木村龍治助教授からは,いろいろのことを教ええていただいた。石川浩治さんと三沢信彦さんには図の作成をお願いしたりした。
東京大学理学部地球物理学教室の岸保勘三郎教授と松野太郎教授からは,この本の構想をたてる段階から有益な助言を頂いた、また京都大学にも一ヵ月ほど滞在して講義をしたし,筑波大学でも集中講義を行った。その経験も本書の執筆に役立った。京都大学の山元龍三郎教授と廣田勇教授,筑波大学の吉野正敏教授と河村武教授にもお礼を申しあげたい.最後に東京大学出版会の清水恵さんは図版の1つ1つに至るまで気をくばって、ていねいに編集してくださった。
本書はかなりもれなく大気科学の基礎的なことを記述しているが,その反面応用気象学に関連したことは紙数の関係で省略したことをお断りしたい。大気中の光学的および電磁気学的現象,大気汚染,降水や気候の人口調節などについては、ほとんど触れてない。1984年新春 東京にて著者
目次
第2版まえがき
初版はしがき
序章
第1章 太陽系のなかの地球
1.1 太陽の概観
1.2 惑星の大気
1.3 地球大気の起源と進化
第2章 大気の鉛直構造
2.1 対流圏と成層圏
2.2 オゾン層とオゾンホール
2.3 電離層
2.4 熱圏
2.5 外気圏と地球脱出速度
第3章 大気の熱力学
3.1 理想気体の状態方程式
3.2 静水圧平衡
3.3 高層気象観測と高層天気図
3.4 熱力学の第一法則
3.5 乾燥断熱減率と温位
3.6 相変化
3.7 大気中の水分
3.8 湿潤断熱滅率
3.9 大気の静的安定度
3.10 対流不安定
3.11 逆転層
第4章 降水過程
4.1 水滴の生成
4.2 エーロゾルと凝結核
4.3 凝結過程による雲粒の成長
4.4 併合過程による雨粒の成長
4.5 水晶の生成と氷晶核
4.6 氷粒子の成長
4.7 雲の分類
4.8 霧
第5章 大気における放射
5.1 入射する太陽放射量
5.2 黒体放射とプランクの法則
5.3 放射平衡温度と太陽放射・地球放射
5.4 地球大気による吸収
5.5 温室効果
5.6 放射平衡にある大気の温度の高度分布
5.7 散乱
5.8 地球大気の熱収支
第6章 大気の運動
6.1 ニュートンの力学の法則
6.2 見かけの力(コリオリの力)
6.3 風と気圧場の関係(地衡風)
6.4 風と気圧場と温度場の関係(温度風)
6.5 地表面摩擦の影響
6.6 エクマン境界層と湧昇
6.7 大気の境界層
6.8 いろいろな運動のスケール
6.9 発散・収束と過度
第7章 大規模な大気の運動,
7.1 ハドレーが描いた大気の大循環
7.2 地球をめぐる大気の流れI 南北方向の循環
7.3 地球をめぐる大気の流れⅡ 東西方向の循環
7.4 モンスーン
7.5 偏西風帯の波動と温帯低気圧
7.6 傾圧不安定波
7.7 前線形成過程
7.8 数値予報と数値実験
第8章 メソスケールの気象
8.1 ベナール型対流
8.2 降水セルと雷雨
8.3 降水セルの世代交代(自己増殖)
8.4 団塊状のメソ対流系
8.5 線状のメソ対流系
8.6 梅雨期の集中豪雨
8.7 台風の概観
8.8 台風の構造と発達
8.9 海陸風と山谷風
第9章 成層圏と中間圏内の大規模な運動
9.1 なぜ成層圏や中間圏に興味があるのか
9.2 中層大気の大循環
9.3 成層圏の突然昇温
9.4 準二年周期の変動
第10章 気候の変動
10.1 過去100万年の気候
10.2 地球温暖化
10.3 エルニーニョ
10.4 気候システム
10.5 決定論的カオスと天気予報
付録1 よく使う単位
付録2 天気図に使う記号
付録3 よく使う数値
索引一般気象学 第2版補訂版
序章
本書の題名は「一般気象学」であるが,もし気象学とはどんな学問かと尋ねられたら,なんと答えよう、気象学とは大気中に起こる現象を扱う自然科学の一分野であるといえば無難であるが,これでは当り前すぎてなんの面白みもない.気象学の客観的な定義は気象関係の辞典にまかせることにして,ここではもっと個人的な感じとして,気象学がもつ2つの特殊性について述べたい、その1つは、気象学は入りやすいが奥が深い学問であるということ,もう1つは、すべての自然科学の分野では,一方の端には実利を考えずただ真理の探究を目指す基礎研究の部分があり,他方の端にはその基礎知識を実利に応用する部分とがあるが,気象学では基礎研究と応用研究が重なり合っている部分が多いということである。
まず前者については,小学生の夏休みの宿題や中学校の理科部の活動として,毎日の新聞に掲載されている地上天気図や気象衛星「ひまわり」の雲画像を切りとって並べ、自身が校庭で測った気象記録と比較して,日々の天気の変化を調べることが例として挙げられる、自分なりの天気予報を試みる生徒がいるかもしれない。そうして入っていった気象学が奥深い学問であることを示す一番よい例は決定論的カオス理論である。この理論は10.5節で簡単に解説するが、「ニュートン以来の近代科学の自然観に劇的な変革を与え,広い分野の基礎科学に大きな影響を与えた」(京都賞受賞理由書)そしてそれを発見した人はエドワード・ロレンツ(EdwardN.Lorenz)という気象学者である。
彼は第二次世界大戦中に召集されて軍の気象隊に勤務して気象学に興味をもち,除隊してからマサチューセッツ工科大学(MIT)で気象学を専攻し、以後同大学の象学教室で独創的な気象学の研究を続けているが,その研究の一環としてベナール型対流を題材としコンピューターを用いた研究中にカオス理論を発見した。ベナール型対流自身は気象学ではおなじみの現象である(8.1節)。彼の使ったコンピューターは当時としても小型で,現在のワークステーション劣る性能のものであったが,彼の比類のない洞察力が新理論を生み出したのである。
しかし,このように気象学の奥深くに入る手前でも,いろいろな段階の学習はそれ相当の気象風景を眺める喜びを与えてくれる.以下天気の変化と温帯低気圧の発達に注目して話を進めよう、上に述べた地上天気図と「ひまわり」の雲画像を眺める段階を入門とすると,それに続く初級の段階では高層天気図が登場する.温帯低気圧は大気中で3次元的に発生し発達するものであるから。
入門時代のように地上天気図だけを眺めていたのでは、それこそ障子に映る影法師だけを見ているようなもので、低気圧の発達のさいに大気中にどんな流れがあり、どんな立体的な温度分布があるか,発達する低気圧と発達しない低気圧ではどこが違うか,全くわからない。テレビの気象情報でよく耳にする「気圧の谷」という用語も,地上天気図だけを見たのではわかりにくいが,高層天気図では一目で納得できる。
次の中級が大学の一般教養課程のレベルで、本書『一般気象学』がそれにあたる。微分・積分を使った数学的議論は次の上級におまかせするものの,熱力学(第3章)とニュートンの運動の法則(第6章)から話が始まるから、使う用語ははっきり定義されているし、なるべく少ない基本的な法則でなるべく多くの現象を説明し理解しようとする態度が明確となる。それに従い,初級のレベルではそのまま受け入れていた表現,たとえば「東に進行していた温帯低気圧は前方の高気圧に阻害されて進行が遅くなり」とか、「台風は太平洋高気圧の真ん中を突っ切れないからその周辺を回って西に進み」とか、「南方からの暖湿な空気が梅雨前線を刺激して大雨が降り」といった表現に違和感を感ずるようになる.
どうして温帯低気圧は前方に高気圧があることを察知して目スピードを緩めることができるのか、こうした表現では低気圧というものが秘的な能力を具えたもののような感じになって、かえってわからなくなってしまう。またカエルの脚の筋肉を針で刺激するとピクンと動くことは中学校の科の実験で経験したからわかるが、前線を刺激するとはいったいどんなことか。
このような表現よりも,温帯低気圧も台風も空気の渦巻だから、川にかかった橋桁でできた渦巻が川の流れとともに下流に流されるのと同じようなことが,温帯低気圧や台風でも起こっていること(8.7節),南風が吹いてきて梅雨前線に沿って収束ができ,下層に上昇気流ができ,そのため不安定な大気中に積乱雲が発達する傾向があるのだという3.10節の説明の方がむしろわかりやすい、丸暗記に努めるよりも、なるほどそうなのかと考え納得し理解することが中級では重要である.
いま注目している温帯低気圧の発達についていえば,発達している地上低気圧の西方に上層の気圧の谷があり、上層の温度の谷(サーマルトラフ)は気圧の谷の西方にあり,相対的に気圧の谷の前方(東側)は後方より温度が高い.そして上層の気圧の谷の前方には上昇気流があり,後方には下降気流がある.この配置によって、「位置のエネルギー」が減少し「運動のエネルギー」が増加して低気圧が発達するというのが話題の中心である(7.5節).そしてここでも、低緯度と高緯度の温度差があまり大きくならないように中緯度で温帯低気圧が発達するのだということを考えると、一見複雑そうな上述の低気圧の構造も理解しやすくなる。
次の段階の上級は理工系の学部の3・4年あるいは修士課程の初年度に相当する。この段階までには微分・積分やベクトルを含む数学の演算や偏微分方程式の解法にも慣れてくる。そして上に述べた温帯低気圧は,実は偏西風の風速が高度とともに増加する割合がある限度を越えたときに発生する傾圧不安定波というものであることを学ぶ、この数学的な理論によって,偏西風の波動(気圧の谷と尾根の一組)ではなぜ波長が数千kmのものが卓越するのか、初めてわかる。
次の段階の特級は研究の世界であり、周囲にはどの本にも書いてない未知の風景が広がっている。上記のように,傾圧不安定波は対流圏上層の偏西風が強いと発達しやすい。そして偏西風は冬季日本上空付近で最も強い(図7.9).それならば傾圧不安定波の活動は冬季に最も活発となることが期待される、ところが実際に観測データを用いて調べてみると、日本付近上空で擾乱の振幅が最大となるのは晩秋と早春の2回あり、真冬にはむしろ振幅が小さくなる。
これは中級や上級のときに学習した教科書と整合しない、どうしてなのか」と疑問が研究の第一歩である。ちなみに,いうまでもないが気象学の分野にてっては微積分などの数学を使わない研究はたくさんあり,上記の意味の上、特級の区別にこだわる必要はない.
次に気象学のもう1つの特性である基礎研究と応用研究の重なりについては、人類は大気のなかで生活していることを思えば,たとえば天文学とくらべて、象学の方が実用性が高いことは容易に想像できる.ところが私が大学の学生であった1940年代前半では事情は現在とはかなり違っていた.一般的に気体や液体のような形を変えやすい物体(流体という)の運動を扱う物理学として流体力学というものがある。当時、東京帝国大学の理学部物理学科の今井功先生や工学部航空学科の谷一郎先生などはすでに圧縮性流体や乱流境界層などについて優れた研究を行い,その成果は航空機の翼の設計などに応用されていた.
ところが同じ流体を扱う気象学の状況はといえば,「大気中の流れは風洞のなかの流れよりはるかに複雑だから、学校で習った流体力学はほとんど役に立たない」と当時の中央気象台の方からいわれたものである。事実,当時の天気予報はベテランの予報官の長年の経験と勘に頼るところが大きかったことからも、この言葉はうなずける。
ところが実は当時すでに新しい気象学が生まれる胎動はあった。1930年代終りから40年代にかけてラジオゾンデによる高層気象観測網が整備され,対流圏上層に偏西風が吹いていること,そしてそのなかに長い波長をもつ波動があることが発見された。そして,その波動の振舞いは,絶対渦度の保存則という流体力学の基本的な法則で記述できることを示したロスビーの論文を総合書館の片隅に積まれていた学術雑誌で読んだのは、上記の状況下で感動的といえるものであった。
そして1940年代の終りには、準地衡風の渦位保存則を用いてチャーニーやイーディーはそれぞれ別に、偏西風帯のなかには傾比べダー波とよばれる波動が発達する可能性があることを理論的に示した.そして観から知られていた発達中の気圧の谷や尾根の振舞いは、理論的に導出された。圧不安定波の性質と多くの点でよく一致していたのである。こうして新しい施帯低気圧像が誕生した。それ以上に意義深いことは,日々の天気の変化をもらす大気の流れはちゃんと流体力学の法則で記述できるのだということとsを目の当りに示したことである.
こうして、折から登場してきた電子計算機を用いて,純粋に流体力学と熱力学の式に基づいた数値計算によって24時間先の大気の流れを予報しようという数値予報の試みが開始された.1950年代には伝統のあるいくつかの大学の最精鋭の気象力学者が数値予報の研究に没頭していたのである。基礎研究と応用研究の重なり合いの好例といえるだろう、ひとたび道が開かれると,あとの進歩は,そのときどきに苦労はあったが一直線である.気象衛星などを用いてグローバルに地球大気を観測する技術,多量のデータを瞬時に送信する通信技術,数値計算の技術,そして驚異的な計算能力をもつスーパーコンピューター開発の技術などの発展に助けられて,予報期間もいまや7日先までと延び,予報精度も年々向上している。
天気の予報という点からいえば,対象とする現象の実態がよく観測され,それを起こすメカニズムがよりよく理解されれば,予報精度の向上は期待される.業務としての気象観測網はこれまで主に高低気圧などの大規模な気象を対象として整備されてきた.しかし近年集中豪雨や竜巻などのメソスケールの気象(第8章)の重要性が認識され,それを観測する測器の開発・整備が行われるとともに研究も急速に進展している.現在米国では、アカデミックに得られた最新の技術・知見をできるだけ速やかに現業に移転できるよう,大学と米国海洋大気庁(わが国の気象庁に相当する)が協力して、海洋大気庁の職員の再教育プログラムを実施していることも、基礎と応用の研究の重なりを示す別の例と見なせるだろう。
もっと最近の例としては、地球温暖化を含む気候の変動や(第10章),オゾン層の破壊(2.2節)を含む地球環境の保全の問題がある。これは気象学が初めて社会に発信した警告といえるだろう。ここでは,もはや基礎研究と応用研究の重なりといった表現が不適切なほど、社会全般に大きなインパクトをもつ未知の研究領域に気象学は足を踏み入れている.
このように、きわめて主観的にいえば,気象学は入りやすく奥が深く、趣味と実益を兼ね備え、若々しく魅力にあふれた学問である。そのような気象学を、できるだけ統一的に体系的に、高等学校卒業程度の物理学と数学と化学の言華で記述するのが本書の目的である。その程度を越えると思われる部分は小活字で示してある。その部分はとばして読んでも,あとの部分の理解には明い。大学初年度の物理学や微積分を学んだ諸君には,本書の内容はさらに分かりやすいはずである.
いくつかの問題が解答つきでのせてある。できれば三角関数や指数関数など初等関数の計算ができるポケット電卓を用いて,自分で答えを出してほしい気象学は定量的な科学である.数値がものをいうああかも知れない,こうかも知れないといろいろな可能性を考えることは重要であるが,同時にどれが一次的に重要で,どれが副次的であるか定量的に見極める必要がある.本書の問題を解くさいに、正しい答えを得るまでに,案外物理量の単位を正しく使わなかったり,ある量が意外に大きかったり小さかったり,いくつかの小さな発見をするかもしれない。もちろん問題の部分をとばして読んでも次の部分の理解には困らない。本書では原則として国際単位系(SI単位系)を使う(付録1).
また,本書のページ数には限りがあるから、随時に章または節の終りに【課外読み物】として,いくつかの本を紹介している。わが国では,気象の入門から上級までそれぞれのレベルで多くの良書が出版されているが,ここでは原則的に本書とほぼ同じレベルの本だけに限っている。もっと広い範囲の参考書案内は,日本気象学会編『新教養の気象学』(1998,朝倉書店)の巻末に掲載されている。
関連記事
証券外務員(一種)試験のおすすめテキスト・問題集(独学勉強法/対策)
一種外務員資格試験について 日本証券業協会は2012年(平成24年)1月より、一種外務員資格試験(以下、一 種試験)を一般に開放し、誰でも受...
日経テストのおすすめ参考書・テキスト – 公式から使える書籍まで
今回は、日経TESTの対策の参考書 / 問題集を厳選して紹介しています。公式の問題集から、幅広く国内外の政治、経済問題を扱った書籍まで、得点...
Google公認のおすすめ認定資格一覧 – 無料で受講も可能!
Googleの認定資格とは? Webに関する資格は数多くありますが、Googleが実施する公認の資格があります。 資格を取得することで、Go...
衛生管理者試験のおすすめテキスト・過去問予想問題(独学勉強法/対策)
労働条件、労働環境の衛生的改善と疾病の予防処置等を担当し、事業場の衛生全般の管理をするのが衛生管理者です。一定規模以上の事業場には選任が必要...
土地家屋調査士は本当に将来性があるのか?これからの業務内容や資格の在り方につ...
土地家屋調査士は不動産の登記や調査、測量に関する専門家と言える国家資格です。不動産の正確な面積などを調べて、記す際に必要です。 土地家屋調査...




試験のおすすめ参考書・テキスト(独学勉強法)1-1-493x328.jpg)




