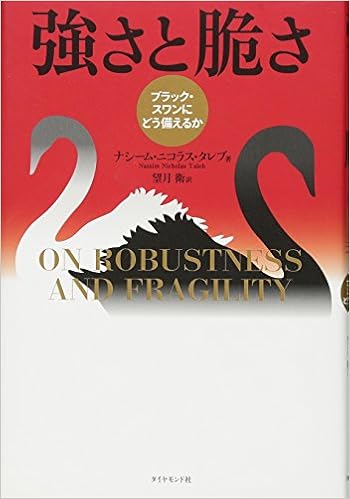ページコンテンツ
知の巨人から学ぶ(新刊)
ナシームタレブはトレーダー出身で現在はニューヨーク大での教授職で、これまで有名な書籍をいくつか出しております。これまで(2020年)で彼による論文ジャーナルを除いた作品は6作の一般向け作品で、最初のDynamic Hedgingを除く、Fooled by Randomness(まぐれ)、Black Swan(ブラックスワン)、The Bed of Procrustes(ブラック・スワンの箴言)、Antifragile(半脆弱性)、そしてSkin in the Game(身銭を切れ)から構成されている “INCERTO” のシリーズとして扱われています。(ちなみに日本語書籍だと“強さと脆さ”というタイトルのものもありますが、こちらはブラックスワンでの原書の2nd editionの追加になる部分です)。
「Dynamic Hedging」はトレーダー時代の中で書かれた専門書的な要素が多く、数式も含んだ専門向けな書籍ですが、その後「まぐれ」からは現在出ている書籍群は “INCERTO” シリーズとして(ちなみにラテン語で不確実性の意味を持つINCERTOから来ています)出版されています。
独立したテーマとして扱われているのでなく、「まぐれ」では日常の偶然、ランダム性、不確実性などを描きつつ、1つの章でまれな確率を扱った章を設けて、それを1つのトピックとして書籍として発展させたのが、「ブラック・スワン」となります。またブラックスワンから実際、我々はどのような行動を取るべきなどの指南書となっているのが「半脆弱性」となっており、実践的で主要な書籍となっています。続く「身銭を切れ」では半脆弱性の後半で一部で扱われてる脆弱なシステムの中ででてくる非対称的な部分に焦点を当てております。また「ブラック・スワンの箴言」は短文集となっております。
原初と翻訳本の関係(要約)
上記でも紹介した原初との翻訳本の関係は以下のとおりです。
Dynamic Hedging → 翻訳なし
【INCERTOシリーズ】
Fooled by Randomness → まぐれ
Black Swan → ブラックスワン
The Bed of Procrustes → ブラック・スワンの箴言
Antifragile → 半脆弱性
Skin in the Game → 身銭を切れ
(原書Black Swanの2版で追加された章は、日本では単独として「強さと脆さ」として扱われています。)
タレブいわく、INCERTOシリーズは単独としてではなく一連の流れがあるといいます。今回の記事を通して是非これまでのタレブの書籍を読んでみましょう。
反脆弱性の読み方は(はんぜいじゃくせい)
ちなみにですが、Antifragileでの邦題の半脆弱性は「はんぜいじゃくせい」となっております。この辺り、Black Swanは「ブラックスワン」なので、Antifragileも「アンチフラジャイル」でも良かったかもしれません。Skin in the Gameも「スキン・イン・ザ・ゲーム」もそうなのですが、邦題がこれだと通じないということもあったのかと思われます。
目次 – まぐれ―投資家はなぜ、運を実力と勘違いするのか
はじめに
知識を真に受けてはいけない
この本は私の二つの個性が結びついて生まれた。私は、偶然にだまされないように抵抗し、偶然に引きずられがちな感情をなだめすかし、現実の世界で不確実性を相手にプロとしての人生を送ってきた人間だ。しかし同時に、美に取り憑かれ、文学を愛し、洗練されて品があって独創的で趣味のいいナンセンスならどんなものにでも喜んでだまされる人間でもある。たまたまの出来事にだまされるのは避けられない。できることといえば、ただ、そういうことになるのを美的に楽しめる分野だけにしておくことだけだ。

この本は、筆者が思うところを真っ正直に書いた私事のエッセイであって、基本的に、リスク・テイクの実践に関連した考えや営み、観察にもとづいている。学術論文というわけではないし、どう見ても、おお神よ許し給え、科学的な調査報告でもない。楽しみのために書かれた本であり、(基本的には)楽しむために読んでもらえる本、そして楽しんで読んでもらえる本を志している。
ランダムな事象を扱うときの(身についたものにせよ、生まれついたものにせよ)私たちのバイアス(偏り)については、ここ一〇年ほどの間にたくさんのことが書かれている。この本の第一版を書くときに自分で決めたルールは、(a)題材について、自分で見たことか自分で考えたこと以外は書かない、そして(b)題材についてほとんど苦もなく書けるぐらいよくわかっていること以外は書かない、ということだった(訳注:日本語版は原書改訂第二版のペーパーバックをもとにしている)。ちょっとでも仕事みたいな感じのすることは全部ルール違反だ。学者の名前を並べてふんぞり返ったりといったようなことも含め、図書館で調べてきたみたいに見える文章は削る羽目になった。覚えていて自然に浮かんだものや、長年私が親しくやりとりしてきた人の書いたもの以外は引用しないようにした(借りものの知恵を好き勝手に使うというやり方は大嫌いだ。これについては後で詳しく)。Aut tace aut loquere meloiora silencio (沈黙は金なり)である。
そうしたルールはこの版でも生きている。でも、人生に妥協はつきものだ。友だちや読者からの圧力に負けて、この版では、でしゃばらない程度に文献を並べた付注をつけた。それから、ほとんどの章は書き加えたし、とくに第1章を大幅に拡張したため、本全体の分量は三分の一以上も増えた。
勝ち馬に乗る
トレーダーが言うところの「勝ち馬に乗る」ことで、この本が生き物みたいに成長してくれればと思う。手に入れた新しいアイディアを、別の本のためにとっておくのではなく、この本に私自身の成長を反映させたいと思う。おかしなことに、この本を世に出して以降、いくつかの章で書いたことについて、以前よりずっと考えるようになった。具体的には次の二つの分野だ。(a)私たちの脳が、この世界で起きることは実際よりもずっと、はるかにずっと、偶然ではないと思い込む仕組み、そして(b)「ファット・テイル」、つまり大きく極端に振れた事象を起こす強い種類の不確実性だ(私たちの生きている世界が、めったに起きないはずの出来事で説明できてしまうケースがどんどん増えている。それなのに、そういう出来事は私たちの先祖の時代から相変わらず直感に反して起きている)。この第二版は、著者である私が、ほんの少し、以前ほど不確実性の研究者ではなくなり(ランダム性について私たちにわかることは本当に少ない)、むしろ人が不確実性にどうだまされるかの研究者になったことを反映している。
もう一つ起きたことがあって、それは書いた私自身がこの本によって変わったということだ。最初にこの本を書いて以降のほうが、私はこの本どおりに振る舞うことが多くなった。まったく思いもしなかったところで運の要素に気づくようになった。なんだか、星が二つあるみたいな感じだ。一つは私たちが実際に暮らしている星、そしてもう一つは、私たちが暮らしていると信じている、ずっと決定論的な星だ。これはとても単純な話だ。すでに起きたことはいつだって実際ほどには偶然には思えないものだから(後知恵バイアスと呼ばれる)。誰かが自分の過去の経験を語るのを聞くと、ほとんどは勘違いした頭で振り返ってでっち上げた後知恵の説明だったりする。そういうのは我慢がならない。
社会科学(とくに主流派の経済学)をやっている人たちや投資の世界の人たちを見ていて、こいつらバカじゃないのかと思うことがよくある。誰かの言葉が、その人が語ろうと思っている対象よりもその人自身について語ってしまっていることがよくある。浮世がそんなだと、とくに、生きていくのは楽じゃない。今朝歯医者で『ニューズウィーク』を手にとると、記者が財界の大物について書いていて、「機を見るに敏」などと述べている。はっと気づくと私は、記事に書いてあることを考えるよりも、その記者が陥っているバイアスを頭の中で並べたてている。書いてあることのほうは真に受ける気にもならない。(マスコミっていうのは、どうして自分で思っているほどわかっちゃいないということがわからないんだろう?半世紀前、「専門家」たちが過去の失敗から学ばないという現象を研究した学者たちがいた。専門家とは、一生ありとあらゆる予測をはずし続け、それでもなお次こそは間違いないと信じてしまう人たちなのだ。)
不信と確率
大事に育てていかないといけない自分の財産は、心に深く根ざした自分の知性への不信感だと私は 考えている。私のモットーは「自信満々で、自分の知性を信じきっているやつらはいじめてやろう」 である。そんな不信感を知性への自信に満ち溢れた場所で育てていこうというのは奇妙なことだし、 簡単ではない。自分の頭から、最近よく見る知性への信頼を追い出さないといけない。
最初は読者で、その後文通相手になった人のおかげで、私は一六世紀のフランスの哲学者で根っからの懐疑派だったモンテーニュを再発見した。それからというもの、モンテーニュとデカルトの違いが意味するものに取り憑かれた。確かなものを求めるデカルトの探求の後を追った私たちは道に迷ってしまった。あいまいでいい加減(しかし重要)なモンテーニュの方法ではなく、デカルトの厳密な 方法にもとづく思考に従うことで、私たちの視野は間違いなく狭くなった。五〇〇年経った今、とても懐疑的で不信に満ちたモンテーニュは、現代哲学者のお手本として高く評価されている。加えて、この人は並外れて勇敢だった。懐疑的であり続ける――物事を疑い、自己批判し、自分の限界を認める――のは勇気のいることだ。私たちが自分で自分にだまされるように、母なる自然は私たちをつくった。そんな証拠が科学者の手でどんどん積み重ねられている。
確率とリスクを把握する枠組みはたくさんある。一口に「確率」といっても、分野が違えば意味もちょっとずつ違う。この本で扱う確率は、数量的あるいは「科学的」なものではなく、質的で人文的なものである(だから経済学やファイナンスの先生に警告しておく。この手の人たちは、自分たちは確率をちゃんとわかっていると信じていて、そのうえ便利なものだと思い込んでいるからだ)。ギャンブル本に出てくる考え方ではなく、ヒュームの帰納法(もっと一般的にいえばアリストテレスの推論)の問題から生まれた概念として確率を扱う。つまりこの本では、確率とは本質的には懐疑主義を応用したもので、工学の一分野ではない(確率を数学的に扱おうとするとものすごく大仰なことになる。でもそうした確率解析周辺の話はだいたいが脚注に書くほどの価値もない)。
そんなことをするのはなぜか?確率はさいころの目や、あるいはもっと複雑な変数のオッズを計算するためだけのものではない。確率とは、私たちの知識が不足していて、確実なことはわからないと認めることであり、自分の無知を相手にするためにつくられた方法なのだ。教科書やカジノの外では、確率が数学の問題だったり頭の体操だったりすることはほとんどない。母なる自然はルーレットにポケットがいくつあるかなんて教えてくれないし、教科書みたいな形で問題を出すこともない(現実の世界では、正解よりも問題そのものを推測しなければならないことが多い)。
この本では、実際に起きた結果とは違う結果が起きていたかもしれないことを考慮したり、世界はこうではなかったかもしれないと考えたりすることが確率論的な考え方の核心となる。実際のところ、私は仕事を始めて以来ずっと、確率を数量的に扱うことを批判してきた。私にとっては(懐疑主義と理性主義を扱った)第13章と第14章こそが、この本の中心となる部分なのだけれど、だいたいの人は第11章(この本の中で一番独創性に欠ける章で、確率に関するバイアスを扱った文献を押し込んだ章だ)に挙げた、確率の間違った計算例に関心を持つ。それに、自然科学ならまだ確率がわかることもいくらかあるけれど、経済学のような社会「科学」の世界では、専門家がいくらはやしたてようが、ほとんどなにもわからない。
(一部)読者の汚名をそそぐ
私の仕事は数理系トレーダーだ。でも、できるだけそんな仕事の話は出さないように努めた。市場での仕事がこの本に与えた影響といえば、きっかけになったということぐらいだ。つまりこれを市場のランダム性を語る本だと思うのは、『イーリアス』を軍事教本だと思うようなものだ。全一四章のうち金融の話をしているのはたったの三章だけである。市場というのは、ランダム性の罠の特別なケースであるにすぎないけれど、運がとても大きな役割をするという点で、圧倒的に一番興味深いケースだ(私が剥製職人かチョコレートのラベルの翻訳屋だったら、この本はかなり短くなっていただろう)。また、金融の世界では、誰も運の何たるかをわかっていないのに、そんな彼らのほとんどが、自分はちゃんとわかっていると思い込んでいる。そのおかげで私たちのバイアスに拍車がかかる。市場をたとえ話に使うときは、たとえば(第二世代の友人ジャック・メラブを頭に思い描いて)知的好奇心を持った心臓内科医と晩ごはんを食べながら話をするときに出すような具体例にした。
第一版を出してから大量の電子メールを受け取った。そういうやりとりができるのはエッセイストとして夢のようだ。第二版を書くのにはうってつけだからである。メールをくれた人にはそれぞれ(一回は)返事をして感謝の気持ちを表した。そんな返事の一部をいろんな章に盛り込んである。私は偶像を壊して回る人間だと見られているので、「ウォーレン・バフェットを云々するなんてお前何様だ」だの「バフェットの成功がねたましいだけだろ」だのといった、怒った読者の手紙が来るのを楽しみにしていた。だから、そういう悪口のほとんどが名無しのまま書けるアマゾン・ドット・コムあたりでしか見られないのにはがっかりした(云々されて困るなんてことはこの世にはない。他人の仕事の悪口を言いふらし、結局は売上げを伸ばしてくれるような人までいるのだ)。
攻撃されなかったのは残念だけれど、代わりに、この本で救われたという人たちから手紙をもらったのはうれしかった。一番報われた気がしたのは、自分のせいではないのに不運な出来事に出くわした人たちからもらった手紙だ。この本の話を使って、奥さんに、自分は義理の弟ほど運がよくないだけだ(能力が低いわけじゃない)と説明したのだそうだ。一番私の心に響いたのは、ヴァージニアに住む人からの手紙だ。この人はほんの数ヵ月のうちに、仕事を失い、奥さんを失い、財産を失い、そのうえあの恐ろしげな証券取引委員会の捜査まで受けた。そんな彼が、本を読んでいくうちに、理性的になるべきなんだと悟ったという。
「黒い白鳥」、つまり大きな衝撃をもたらす予期しない事件(お子さんが亡くなった)に出くわした人からの手紙を読んでしばらくは、偶然でひどい目にあったとき、人がどうやってそれに適応するかを扱った文献にどっぷり浸ってすごした(そういう分野でも、不確実性の下で人が見せる非合理的な行動の研究という分野を切り開いたダニエル・カーネマンが第一人者だ)。トレーダーをやっているころ、別に(自分以外の)誰かの役に立っているなんてぜんぜん思わなかった。エッセイストになって、人のお役に立っているという気高い気分を味わった。
あるかないか
この本で言いたかったことについていくつか。私たちの脳みそは確率が高いとか低いとかの話が簡単にわかるようにはできていない。すぐ「あるかないか」なんていう極端な話になってしまう。この本で書いたのは「物事は私たちが思っているよりもたまたまなんだ」ということで、「物事は全部たまたまなんだ」ではないということがなかなかわかってもらえない。おかげで「疑り深いタレブは、すべてはたまたまで、成功した人なんてみんな運がよかっただけだと主張している」なんて扱いを受けた。
「まぐれ」病はあの有名なケンブリッジ・ユニオン・ディベートにまで広がっていて、「肩で風切って街を歩く連中なんて、ほとんどは運がよかっただけだ」と言っているのに、「肩で風切って街を歩く連中なんて、全部運がよかっただけだ」と言っていることにされてしまった(恐るべきデズモンド・フィッツジェラルドとの討論では完全に負けた。あれは生まれてからやった中で一番楽しい討論だった。考えを変えようかとさえ思ったほどだ!)。(この本でも書いたが)恐れを知らないのを傲慢さと取り違えるのと同じように、彼らは懐疑主義をニヒリズムと取り違えているのだ。
一つはっきりさせておこう。準備を怠らないからこそチャンスも生まれるのだ!一所懸命に仕事をして、約束の時間を守って、清潔な(できれば白い)シャツを着て、ちゃんと風呂に入って、そのほか普通にやるべきことをやっていてこそ成功できるのだ。そういうことをやっていないと成功できないけれど、それだけで成功できるわけじゃない。そういうことが成功の原因ではないからだ。粘り強さ、根気、忍耐力も同様。大事だ、とても大事だ。宝くじだって買わないと当たらない。ということは、宝くじの売店へ行ったことが宝くじに当たったことの原因なんだろうか?もちろん、能力があれば助けになるけれど、歯医者の業界に比べると、たまたまの要素が多い世界で、能力が果たす役割は小さい。
いや、仕事に対する意識の高さが大事だというあなたのおばあさんの教えが間違っているなんて、私は言ってない!それに、稀にしか見られない「チャンスが訪れたとき」を捉えてこそ成功できるのだから、そんなときを逃せばキャリアもおしまいかもしれない。運を味方につけろ!
私たちの脳みそは因果の方向をさかさまに捉えてしまうことがある。いい仕事が成功の原因だとしよう。そう仮定すると、頭がよく、よく働き、粘り強い人がみんな成功しているからといって、成功している人がみんな、頭がよく、よく働き、粘り強い人だとはかぎらないのに、なんとなくそんな気がしてしまう。いつもはとても賢い人たちがこんな初歩的な論理の誤りを犯すのにはいつも驚かされる。おかげで今書いた話が再確認できるのだ。このあたりの話は、この本では「二重思考」の問題と呼んで検討している。
どうすれば成功するかの研究には、こじつけの類がよくあって、こんなうたい文句とともに本屋に並んでいる。「億万長者はこんな人たちだ。彼らのように成功するためにあなたに必要なこととは」とか。(第8章で触れるけれど)「となりの億万長者』の勘違いした著者の一人が「なぜ、この人たちは金持ちになったのか:億万長者が教える成功の秘訣』という輪をかけてバカな本を書いている。それによると、彼が調査した一○○○人を超える億万長者たちのほとんどは、子供のころ、さほど頭がよかったわけではなかった。そこで彼は、人は生まれつきの能力でお金持ちになるわけではなく、むしろよく働くからこそお金持ちになるのだと考えた。それを見て、成功にはたまたまの要素が入り込む隙はないなんて無邪気に思う人がいるかもしれない。
私はというと、もし億万長者の特徴が普通の人と変わらないなら、それは彼らの運がよかったってことだと不穏なことを考える。幸運というのは民主的なもので、人の能力がどうだろうと関係なく、准に訪れても不思議はない。先ほどの著者たちは、お金持ちにはいくつか普通の人とは違う点もあることに気づいた。たとえば粘り強いとかよく働くとかといったことだ。これも必要なことと結果として起きたことを取り違えている。お金持ちはみんな粘り強くてよく働く人たちだからといって、粘り強くてよく働く人がみんなお金持ちになるとはかぎらない。失敗した起業家はたくさんいるけれど、多くの場合彼らだって粘り強くてよく働く人たちだ。
教科書にでも出てきそうな単純な実証主義に従って、著者たちは億万長者に共通する特徴を探し、彼らが皆、リスクをとるのを厭わない人たちであることを発見した。大きな成功を収めようと思ったらリスクをとる必要があるのは当然だ。でも、大きな失敗のほうにもそれは言える。著者たちが調査したのが破産した人たちだったとしても、やっぱり元々リスクをとるのを厭わない人たちであるのを発見しただろう。
読者の一部(や、私が運よくこの本を出してくれたテクセア社に行き着く前に話をした、人まねしかできない出版社)から、「データ」やグラフやチャートや絵や座標や表や数字や推薦図書や時系列やその他を示して、この本の主張を裏づけてくれと言われた。この本は論理的な思考実験を積み重ねたもので、経済学の期末試験の論文ではないのだから、実証で裏づけたりする必要はないのだ(これもまた、私が「逆もまた真」の誤りと呼ぶもののせいだ。マスコミや一部の経済学者がよくやっているけれど、理論の裏づけなしで統計を使うのは間違いだ。でも、その逆は間違いではない。つまり、統計の裏づけなしに理論を使うのは間違いではない)。
お隣さんが成功したのは、仕事に偶然の要素があって、大なり小なり運に恵まれたおかげなのだと思うと書いたとして、それを「実証」する必要などない。ロシアン・ルーレットの思考実験で十分だ。ただ、お隣さんは天才だという仮説に代わる別の説明がありさえすればいい。残念な知能水準の人を集めれば、そのうちほんの数人しかビジネスマンとして成功できないだろうけれど、そういう成功した連中だけが目立つのだと示すのが私のやり方だ。ウォーレン・バフェットなんか能力があるわけじゃないとは言わない。ただ、投資家をでたらめにたくさん集めれば、ほとんど必ず誰かは、運だけでバフェット並みの成績を上げると言っているだけだ。
からかうチャンスを逃す
この本でマスコミを信じるなとさんざん書いているのに、北アメリカやヨーロッパでテレビやラジオの番組に呼ばれたのには驚いた(その中にはラスヴェガスのラジオ局での「聞くのに不自由同士の会話」もあった。あれには笑った。インタビュアと私は話がかみ合わないままずっと喋り続けたのだ)。私を守ってくれる人なんて誰もいないので、インタビューを受けることにした。おかしなもので、マスコミは毒だという話をするにもマスコミを通さないといけない。短いコメントに編集されて、ぜんぜん違う話として使われるんじゃないかと思ったけれど、それでも面白かった。
マスコミの主なインタビュアたちは私の本を読んでもいないし、私がバカにしているのをわかりもしない(ああいう連中は本を読んでいる「時間がない」から)。彼らほど稼げていない連中のほうは深読みしすぎで、自分たちのやっていることが認められたと思っていた。そんな中での逸話をいくつか。有名なテレビ番組の連中が「このタレブってやつは株のアナリストの予測なんてみんなデタラメだって言っている」と聞きつけて、番組に出てきて説明してほしいと言う。ところが、私の「能力」を証明するために株の推奨を三銘柄持ってこいというのが条件だった。結局出なかったので、デタラメに銘柄を三つ選んで、さもありそうな説明をでっちあげるというすばらしいいたずらをするチャンスを逃してしまった。
別のテレビ番組で、株式市場はデタラメに動くものだという話と、何かが起きるといつも後づけの説明が出てくるという話をしていて、「人は材料なんてなくても何かあるに違いないと思うものだ」と言った。そこですぐに番組のキャスターが割って入った。「今朝はシスコに材料が出ています。何かコメントはありますか?」そして最高傑作:ラジオの金融番組で一時間の討論に招かれたけれど(彼らは第11章を読んではいなかった)、番組が始まる数分前になって、この本の話はしないでくれと言う。トレーディングの話をしてもらうために呼んだので、ランダム性の話をしてほしいんじゃないからと言われた(このときも絶好のいたずらのチャンスだったけれど、そんな準備はしてこなかったので、番組が始まる前に帰ってしまった)。
記者のほとんどには、それほどひどい思い込みはない。結局、このジャーナリズムという商売は純粋にエンタテイメントであって、真理の探究ではないのだ。ラジオやテレビはとくにそうだ。大事なのは、自分たちは単なる芸人なんだということがわかってなくて、自分はインテリだと思ってそうな連中(第2章に出てくるジョージ・ウィルなんかがそう)には近寄らないようにすることだ。
マスコミにはそれ以外にも、人の言っていることを正しく理解できないという問題がある。このナシームってやつは、市場はランダムだ、つまり市場は今後下落すると思ってるんだ。おかげで私は、そんなつもりはないのに、大災害を予言する人に祭り上げられてしまった。黒い白鳥、つまりめったに起きず、思ってもみないときに起きる異常事態は、いいほうに異常であることも悪いほうに異常であることもあるのだ。
しかし、マスコミには、一見して思うよりもずっといろんな人種がいる。考え深い人もけっこういて、耳ざわりのいいキャッチフレーズで埋め尽くされた商業主義マスコミを抜け出し、視聴率よりも伝えることに重きを置いた活動をしている。コージョ・アナンディ(NPR)、ロビン・ラスティック(BBC)、ロバート・スカリー(PBS)、そしてブライアン・レーラー(WNYC)と話したかぎりでの素朴な観察結果でいえば、ジャーナリストでも、お金のためにやっているわけではない人たちは、全体として知能がある種族だ。見たところ、番組での議論の質はスタジオの豪華さと逆相関している。WNYCで、ブライアン・レーラーは議論を深めようととても努力していた。そして、あそこのオフィスはカザフスタンよりこちら側では一番みすぼらしいのだ。
最後に文体について一言。第一版からそのままに、この版でも独自の文体を貫くことにした。善かれ悪しかれ、私は人間だ。間違いだってするし、ちょっとした間違いなら、それだって私の人格の一部なのだから、隠す必要があるとは思わない。写真を撮るときにカツラをかぶったり、人に向き合うときに誰かから鼻を借りてきたりしようなんて思わないのと同じように。
下書きを読んだ編集者はほとんどみんな、(私の文章のスタイルを「もっとよく」するために)個組別の文のレベルでも(章の構成などといった)文章のレベルでも修正したほうがいいと言っていた。彼らの言うことはほとんど全部無視した。読者にそんな修正が必要だと思った人はひとりもいなかった。実際、(不完全な点も含めて)著者の性格が現れた文章のほうが生き生きしていると思う。出版業界も古典的な「専門家」問題に冒されていて、実証的にはぜんぜん有効でない、いい加減な経験則が山ほどあるということだろうか。その後私は、読者が一〇万人を超えたあたりで、本というのは編集者のために書くもんじゃないと悟ったのだった。
改訂第二版での謝辞
図書館の外へ
この本のおかげで、私は精神的に孤立した状態から抜け出すことができた(完全に学界の住人でないと、たくさんの点でいいことがある。独立独歩でいけるし、住人になるための手続きも避けられる。そのかわり、他人から孤立してしまうのだ)。第一版のおかげで、晩ごはんを食べたり文通したりする頭のいい友だちがたくさんできた。それに、彼らのおかげで、書いた題材のいくつかをさらに深めることができた。
加えて、書いた話に興味を持ってくれた人たちとの議論に刺激を受けて、夢の生活にまた一歩近づくことができた。本代を返さないといけないんじゃないかという気さえする。考えを進めるには、図書館を這い回るよりも、賢い人たちと話したりやりとりしたりするほうがいいという実証結果もあるみたいだ(人のぬくもりってことだろう。私たちに自然に備わった何かが、他の人たちとやりとりしたり付き合ったりしている間にアイディアを育むのだ)。ともかく、「まぐれ」前の人生と「まぐれ」後の人生は違っていた。第一版での謝辞は今でも生きているけれど、ここでは私がその後お世話になった人たちを挙げる。
世界を狭くする
ロバート・シラーと初めて直接会ったのは、朝食の席上で行われたパネル・ディスカッションで席が隣同士になったときだった。私はうっかりして、彼の皿にのっている果物を全部食べてしまい、そのうえ彼のコーヒーと水も飲んでしまった。彼にはマフィンやなんかのあんまりうれしくない食べ物ばかりが残った(そして飲み物は無しだ)。彼は文句も言わなかった(気づいていなかったのかもしれない)。
第一版で彼のことを書いたころは、まだシラーと知り合ってはいなかった。会ってみると、彼が親しみやすくて謙虚で魅力いっぱいなのに驚いた。そのあと、彼は私をニューヘイヴンの本屋まで車で連れて行き、『多次元・平面国:ペチャンコ世界の住人たち』を見せた。物理学の寓話で、高校時代に第一版を読んだそうだ。短く、個人的な本で、ほとんど小説だった。今回の書き直しで私がずっと心がけていたことだ(彼は第二版なんて書かないほうがいいと力説した。私は彼に、私のためだけにでもいいから『投機バブル 根拠なき熱狂』の第二版を書いてくれと言った。どっちの件でも勝ったのは私だと思う)。
本には第10章で説明するようなバブルを起こす力が働く。つまり、すでに世に出た本の改訂版のほうが、まったく新しい本よりも臨界点に達する可能性が高い(宗教や流行でも、ネットワークの外部効果のおかげで、新しいものより焼き直しのほうがずっとうまくいく)。物理学者にして暴落理論家のディディエ・ソネットは、第二版を出すことの効果について強力な説明を語ってくれた。情報カスケードのおかげで食っていける出版社の連中が彼のいう効果をわかっていなかったので、二人とも驚いた。
イタリアで二回にわたって行ったダニエル・カーネマンとの激しい議論は、この本を書き直す過程のほとんどを通じて私に働く原動力を与えてくれた。彼との議論には、知的探究の次の臨界点へと「後押し」してくれる効果があった。彼の研究が単なる不確実性下の合理的選択よりはるかに深いところまで行っているのを見て以来そうなった。彼が経済学に与えた影響(ノーベル記念賞も含めて)のせいで、彼の発見の広さや深さが注目されない。あれは幅広く一般的に当てはまることなのだ。
経済学は退屈だ、でも彼の研究は重要だ、私は自分にそう言い聞かせ続けた。彼が実証主義者だからというだけでもなければ、最近のノーベル記念経済学賞受賞者と彼の研究(や人となり)の重要さは好対照だからというだけでもない。むしろ、並外れて重要な疑問に対して彼の仕事が大きな意味を持つからだ。つまり、(a)彼とエイモス・トヴァスキーは、ギリシャ時代の教条的な合理主義に始まって、その後二三世紀の間私たちが持ち続けた人間観をひっくり返した。あの人間観のおかげで、私たちは、今になってひどい結末に苦しむはめになったのだ。(b)カーネマンの重要な仕事は、(さまざまな段階の)効用に関する理論で、幸せなどの重要な問題に大きな意義を持つ。今や、幸せは本物の研は究対象になった。
生物学者にして進化経済学者のテリー・バーナムとは長々と議論した。進化心理学を、気取ることなく紹介した本、『いじわるな遺伝子:SEX、お金、食べ物の誘惑に勝てないわけ』の共著者だ。偶然にも彼はジャミール・バーズの親友だった。子供のころからの友だちだそうだ。そのバーズは二○年前、私がランダム性について考え始めたころに、考えをぶつけて意見を聞いた相手だった。ピーター・マクバニーは人工知能をやっている人たちに私を紹介してくれた。この分野は哲学、認知脳科学、数学、経済学、そして論理学を合わせ、融合させているようだ。私は彼と、いろいろな合理性の理論についてなんとなくやりとりを始め、いつの間にか書簡は膨大になった。
マイケル・シュレイグは書評を書いてくれた一人であり、現代的(したがって科学的)インテリの典型だ。重要そうな本をかぎ当てて全部読む、そんな才覚がある。彼と話すと本物の知性を感じる。標準的な学界のしばりにとらわれていない。ラマズワミ・アンバリッシュとレスター・シーゲルは著作(注目されていないのがまったく不思議だ)を通じて、運用成績を評価する際、ランダム性にだまされていると、パフォーマンスの違いがいっそう見分けられなくなることを教えてくれた。マルコム・グラッドウェルは直観と自己認識を扱った文献から面白いものを見繕って送ってくれた。アート・ド・ヴァニーは非線形と稀にしか起きない事象が専門の経済学者で、洞察力があってとても興味深い人だ。彼が初めてくれた手紙はこんな宣言で始まっていた。「私は教科書をバカにしている」彼みたいに考えの深い人が、同時に人生を楽しんでいるのを見ると勇気が湧く。
経済学者のウィリアム・イースタリーは、経済発展をもたらす要因が勘違いされているのはランダム性が原因の一つだと教えてくれた。彼はよく、懐疑的な実証主義者であることと、政府や大学といった組織が知識を独占するのが嫌いであることの関係を語っていた。熱心な読者で、ハリウッドでエージェントをしているジェフ・バーグは、マスコミ業界に見られる強い種類の不確実性について考えを語ってくれた。彼にも感謝している。本のおかげでジャック・シュウェイガーと夕食の席上で興味深い議論をすることができた。彼は、いくつかの問題について、今生きている人の誰よりも長く検討してきたようだ。
ありがとうグーグル
次に挙げる人たちは、この本を書く際に手助けしてくれた人たちだ。アンドレア・ムンテアヌが厳しい読者として得がたい意見を言ってくれたのはとても幸運だった。彼女はデリバティブの世界で目覚ましい仕事をする傍ら、この本で引用した内容が正しいかどうか、グーグルで調べてくれた。アマンダ・ガルゴーもそうした検索を手伝ってくれた。
それから、イタリア語版の翻訳者がジャンルカ・モナコだったのは幸運だった。彼は文中の間違いを片っ端から見つけてくれた。私がやっていたら一世紀かけても終わらなかっただろう(この人は認知科学者であり、また翻訳者から数理ファイナンスの研究者に鞍替えした人だ。彼は出版社に電話して自分に翻訳させろと交渉した)。
科学哲学者で論文を一緒に書いたこともあるアヴィタル・ピルペルは専門的な確率の議論に付き合ってくれた。エリー・エイヤッシュは私と同じレバノン人で、トレーダー兼数学者兼物理学者から科学と確率と市場の哲学者に転身した人だ(神経生物学はやってないけれど)。この人のおかげで、私はボーダーブックスの哲学と科学のコーナーで膨大な時間を費やした。
フラヴァ・シンバリスタ、(今はライリー社にいる)ソール・マリティーミ、ポール・ウィルモット、マルク・シュピッツナーゲル、グル・フーバーマン、トニー・グリックマン、ウィン・マーティン、アレキサンダー・ライス、テッド・ジンク、アンドレイ・ポクロフスキー、シェップ・デイヴィス、ガイ・リヴィエア、エリック・シェーンバーグ、そしてマルコ・ディ・マルティーノは書いてあることについてコメントしてくれた。ジョージ・マーティンは、いつもどおり、考えをぶつける相手として得がたい人だ。読者のカリン・シシェリュー、ブルース・ベルナー、そしてイーリアス・カトソニスは膨大な量の誤植をeメールで指摘してくれた。シンディ、サラ、そしてアレキサンダーの支援にも感謝したい。彼らはいつも、確率と不確実性ばかりがすべてじゃないと思い出させてくれる。
第二のわが家、クーラン数理科学研究所にも感謝すべきだろう。興味のある分野を追究し、学生に教えながら、知的には独立性を保っていられる、すばらしい環境を提供してくれた。とくに、ジム・ガスラルは一緒に授業をやっていると四六時中私の言うことに口を挟んでくれる。パロマのドナルド・サスマンとトム・ウィズは非凡な洞察を示してくれた。彼らが「黒い白鳥」をとてもよく理解しているので私は感銘を受けた。また、エンピリカのメンバー(社員という言葉は禁止している)には、職場に激しく非情な空気を育み、本当に情け容赦ない知的な討論を行ってくれた。感謝している。私が何かいうたびに、私の同僚たちは必ずなんらかの形で反論してくれる。
この版でももう一度、デイヴィッド・ウィルソンとマイルズ・トンプソンに感謝する。彼らがいなければ、そもそもこの本は世に出なかった。さらに、ウィル・マーフィ、ダニエル・メナカー、エド・クラグスバーンは、この本を復活させてくれた。彼らがいなければ、この本は死んだままだっただろう。ジャネット・ワイガルには完璧で我慢強い仕事に対し、フリートウッド・ロビンズには提供してくれた手助けに対し、感謝している。彼らの熱心さからいって、間違いはあんまり残っていないと思うけれど、もしもあったらそれは私のせいだ。
まぐれ――投資家はなぜ、運を実力と勘違いするのか 目次
はじめに――知識を真に受けてはいけない
改訂第二版での謝辞
各章の要約
プロローグ――雲に浮かんだモスク
第I部 ソロンの戒め 歪み、非対称性、帰納法
第1章 そんなに金持ちなら頭が悪いのはどうしてだ?
ネロ・チューリップ
雷の一撃
一時的な正気
仕事の流儀
プロ意識なし
誰にだって秘密はある
ハイイールド債トレーダーのジョン
成金の田舎者
真っ赤に燃える夏
セロトニンとランダム性
あなたのかかりつけの歯医者はお金持ちだ、ものすごくお金持ちだ
第2章 奇妙な会計方法
違った歴史
ロシアン・ルーレット
あり得る世界
もっとたちの悪いルーレット
同僚とは仲良く
アエロフロートで拾い物
ソロンがリジンのナイトクラブにやってくる
ジョージ・ウィルはソロンじゃない――直観に反する真理について
討論で恥をかく
違った類の地震
ことわざを一つ
リスク・マネジャー
ついでに起きること
第3章 歴史を数学的に考える
ヨーロッパの遊び人の数学
道具について
モンテカルロの数学
屋根裏部屋での楽しみ
歴史をつくる
屋根裏部屋でゾルグルーブが増えていく
歴史を軽んじる
ストーブは熱い
過去の歴史を予測する能力
私にとってのソロン
パームパイロットで蒸留された考え
緊急ニュース
シラー再び
長老の支配
ピロストラトス、モンテカルロに現わる――ノイズと情報の違い
第4章 たまたま、ナンセンス、理系のインテリ
ランダム性と動詞
逆チューリング・テスト
エセ思想家の始祖
モンテカルロの詩
第5章 不適者生存の法則――進化は偶然にだまされるか?
新興市場の魔術師カルロス
いい時代
買い下がり
砂浜に描いた線
ハイイールド債トレーダーのジョン
コンピュータと方程式を操るクウォンツ
連中に共通する特徴
市場に巣食う、たまたまなのにその気になる連中の特徴を概観する
素朴な進化論
進化は偶然にだまされるか?
第6章 歪みと非対称性
中央値は語らない
牛熊動物学
傲慢な二九の若造
稀な事象
対称性と科学
ほとんどみんなが並以上
稀な事象に関する誤解
究極の引っ掛け
統計学者が稀な事象に気づかないのはなぜか?
いたずらっ子が球を入れ替える
第7章 帰納の問題
ベーコンからヒュームへ
シグナス・アトラトゥス
ニーダーホッファー
カール卿の広報担当
場所、場所
ポパーの答え
開かれた社会
誰にだって欠点はある
帰納と記憶
パスカルの賭け
ありがとうソロン
第Ⅱ部 タイプの前に座ったサル
生存バイアスとその他のバイアス
第8章 あるいはとなりの億万長者でいっぱいの世界
失敗して傷つくのをやめるには
ちょっと幸せ
仕事のしすぎ
お前は負け犬
二重の生存バイアス
また専門家
勝って表舞台へ
上昇相場のたまもの
カリスマのお言葉
第9章 卵を焼くより売り買いするほうが簡単
数字にだまされて
プラシーボ投資家
能力なんて誰もいらない
凡人へ逆戻り
エルゴード性
人生は偶然の出会いでいっぱい
不思議な怪文書
テニスの試合に邪魔が入る
生き残りの逆
誕生日のパラドックス
世間は狭いねぇ!
データ・マイニング、統計、いかさま
これまで読んだ中で最高の一冊!
バックテスト
もっと不穏な拡張
業績発表の季節――結果にだまされて
相対的な運
ガンの治療法
ピアソン教授、(文字どおり)モンテカルロへ行く――たまたまはたまたまに見えない!
吠えない犬――科学的知識のバイアス
結論はない
第10章 敗者総取りの法則――日常の非線形性
砂山のなだれ現象
ランダム性の導入
タイプを学ぶ
現実の世界の裏表と数学
ネットワークの科学
私たちの脳
ビュリダンのロバ――ランダム性のよい面
降れば土砂降り
第11章 偶然と脳――確率をわかるのに不自由
パリ?それともバハマ?
構造上の問題
哲学をやっている役人には気をつけろ
充足化
単なる不完全ではなく欠陥
カーネマンとトヴァスキー
ここぞというときにナポレオンはどこへ行った?
「どれだけ儲けるかが大事」、その他のヒューリスティック
フォーチュン・クッキー博士
二重思考
初めてのデートで結婚しないのはなぜか
私たちが本来生きていた場所
すばやく、つましく
神経生物学者も参戦
法廷のカフカ
不条理な世界
確率を見るときのバイアス、その例
ぼくらにオプションはわからない
確率とマスコミ(さらにジャーナリストについて)
お昼ごはんどきのCNBC
お前はすでに死んでいる
ブルンバーグの解説
ろ過のやり方
ぼくらに信頼水準はわからない
告白
第Ⅲ部 耳には蝋を
偶然という病とともに生きる
第12章 ギャンブラーのゲンかつぎと箱の中のハト
タクシー・ドライバーの英語と因果
スキナーのハトの実験
ピロストラトス再び
第13章 カルネアデス、ローマへきたる
確率論と懐疑主義カルネアデス、ローマへきたる
懐疑主義が生んだ確率論
ノルポワ侯爵の意見
信念の経路依存性
考える代わりに計算する
墓場から墓場へ
第14章 バッカスがアントニウスを見捨てる
ジャッキー・Oの葬式
偶然と人としての品格
エピローグ――ソロンの言うとおり器
ロンドンの渋滞には気をつけろ
あとがき――シャワーを浴びながら振り返る
振り返る、その一――能力は逆転する
振り返る、その二――偶然のメリットをもういくつか
不確実性と幸せ
メッセージにスクランブルをかける
振り返る、その三――一本足で立つ|
;
第一版での謝辞
訳者あとがき
図書館へ行く――参考文献
図書館へ行く――付注
索引
各章の要約
第1章 そんなに金持ちなら頭が悪いのはどうしてだ?
正反対の二人を通じて、偶然が社会の序列とねたみに及ぼす影響を描く。隠れた稀な事象について。現代の日常は急に変わる。例外は、たぶん、歯医者の業界ぐらいだ。
第2章 奇妙な会計方法
違った歴史、確率論的な世界観、知的欺瞞、そしてよく風呂に入るフランス人のランダム性に関する見識。どうしてマスコミはたまたまの物事がわからないのか。借り物の知恵にご用心。偶然の結果に関するすばらしい考えが、ほとんど全部、通念に反しているのはなぜか。正しいこととわかりやすいことの違いについて。
第3章 歴史を数学的に考える
時間とともに起きていく偶然の事象を理解するためのたとえとしてのモンテカルロ・シミュレーション。ランダム性とつくりものの歴史。古いものはほとんどいつも美しく、新しいものや若いものはだいたい毒だ。歴史の教授を標本抽出論入門の講座へ行かせろ。
第4章 たまたま、ナンセンス、理系のインテリ
モンテカルロ・ジェネレータで人工知能をつくり、ランダム性に頼らずに厳密につくられた知能と比べる。サイエンス・ウォーズは実業界へ。私の中の美を愛でる部分が好き好んでまぐれにその気になるのはなぜか。
第5章 不適者生存の法則――進化は偶然にだまされるか?
稀な事象を二つ。稀な事象と進化。生物学の外の世界で「ダーウィン主義」と進化がどれだけ誤解されているか。命は連続でない。進化がどう偶然にだまされるか。帰納の問題への序論。
第6章 歪みと非対称性
歪みという概念を持ち込む。「ブル」とか「ベア」とかいうのは動物学の外の世界ではあんまり意味がない件について。いたずらっ子がランダムな構造を台無しにする。認識の不透明さの問題とは。帰納の問題へあと二歩。
第7章 帰納の問題
白鳥の色素力学について。ソロンの戒めを哲学に持ち込む。ヴィクター・ニーダーホッファーが実証主義を教えてくれた。私はそれに演繹を加えた。科学を額面どおりに受け取るのがなぜ科学的でないか。ソロスがポパーを広める。フィフス・アヴェニューと一八番街の角の本屋。パスカルの賭け。
第8章 あるいはとなりの億万長者でいっぱいの世界
生存バイアスの例を三つ。どうしてパーク・アヴェニューに住んでいい人はとても少ないのか。となりの億万長者の衣はとても薄っぺら。また専門家。
第9章 卵を焼くより売り買いするほうが簡単
生存バイアスを専門的に拡張する。日常における「偶然」の分布。能力よりも運があったほうがいい(でもいつかはツケが回るかも)。誕生日のパラドックス。さらに詐欺の話(さらにマスコミの話)。プロ意識のある研究者ならデータから何でも見つけられる件について。吠えない犬。
第10章 敗者総取りの法則――日常の非線形性
日常における意地の悪い非線形。ベルエアへ行ってお金持ちの有名人の悪いところを身につける。マイクロソフトのビル・ゲイツが業界最高でないかもしれない(でも彼にそんなことを教えてはいけない)のはなぜか。ロバからエサを取り上げる。
第11章 偶然と脳――確率をわかるのに不自由
バケーションはパリとバハマを線で結んでも想像しにくい件について。たぶんネロ・チューリップは二度とアルプスでスキーはしない。役人に多くを望むのは間違い。ブルックリン製の脳みそ。ナポレオンが必要。スウェーデン国王にお辞儀する科学者たち。マスコミという公害についてもう少し。おまえはすでに死んでいる。
第12章 ギャンブラーのゲンかつぎと箱の中のハト
私の人生はギャンブラーのゲンかつぎでいっぱい。英語のわからないタクシー・ドライバーのおかげで儲かるのはなぜか。私がバカの中のバカなのはなぜか。でも、私は自分でそれを知っている。自分の遺伝子レベルの不適応と付き合う。トレーディング・デスクにはチョコレートの箱を置かない。
第13章 カルネアデス、ローマへきたる確率論と懐疑主義
監察官カトー、カルネアデスを追い返す。ノルポワ侯爵は前に自分が言ったことを覚えていない。科学者、注意せよ。アイディアと結婚。あのロバート・マートンが私を有名にした。科学は墓場から墓場へと進歩する。
第14章 バッカスがアントニウスを見捨てる
モンテルランの死。理性主義とは噛み締めた唇のことではなく、偶然に打ち克ったという幻想のこと。勇敢になるのはとても簡単。まぐれと人としての品格。
目次 – ブラック・スワン[上]―不確実性とリスクの本質
目次
鳥の羽根の色
わからないこと
専門家と「空っぽのスーツ」
学ぶことを学ぶ
新手の報われない人たち
日常はまったく日常的でない
プラトンとオタクたち
くだらなすぎて書けない
肝心なところ
章立ての見取り図
第1部
ウンベルト・エーコの反蔵書、あるいは認められたい私たちのやり口
第1章 実証的懐疑主義者への道
黒い白鳥の解剖学
やることをやることについて
「天国」が煙と消える
星の降る夜
歴史と不透明の三つ子
どうなってるのか誰にもなんにもわからない
歴史は流れない、歴史は移る
いとしい日記―歴史を後ろにたどる
タクシーでの教育
塊
祭はどこだ?
八・七五ポンドの後に
勝手御免の四文字言葉
リムジン哲学者
第2章
イェフゲニアの黒い白鳥
第3章
投機家と売春婦
最高の(最悪の)アドバイス
広げられるものにはご用心
拡張可能性の誕生
拡張可能性とグローバリゼーション
月並みの国の旅
おかしなところ、果ての国
果ての国と知識
強い・弱い
まぐれのなすがまま
第4章
千と一日、あるいはだまされないために
七面鳥に学ぶには
バカになる訓練
白鳥の色は知識で違う
黒い白鳥問題の大まかな歴史
(ああ)経験主義者、セクストス
アルガゼル
懐疑主義者は宗教の友だち
七面鳥にはなりたくない
月並みの国で暮らしたい連中
第5章
追認、ああ追認
ズーグルばかりがブーグルではない
証拠
否定の実証主義
三つ数えろ
また赤いミニだ!
全部ってわけじゃない
再び月並みの国へ
第6章
講釈の誤り
私が原因を否定するにいたった原因
脳の区分け
ドーパミンをもう少し
アンドレイ・ニコライェヴィチの法則
いい死に方
過去でもないのに記憶とは
狂える人の講釈
講釈と治療
間違ったことを限りなく几帳面にやる
非情の科学的
扇情と黒い白鳥
黒い白鳥を見るのに不自由
大騒ぎの引力
手っ取り早いやり方
脳みそに気をつけろ
講釈の誤りを避けるには
第7章
希望の控えの間で暮らす
まわりの冷たい目
大事なことが衝撃的でもあるところ
非線形
結果より過程
人間の本性、幸せ、そしていちどきに報われる
希望の控えの間
希望に酔う
予感の甘い罠
バスティアーニ砦が必要なとき
エル・デシエルト・デ・ロス・タルタロス
だらだら死ぬか、突然死ぬか
第8章
ジャコモ・カサノヴァの尽きない運
物言わぬ証拠の問題溺れる信者の話
文字の墓場
億万長者になれる一○のステップ
ネズミのスポーツジム
意地の悪いバイアス
もっと見えにくい応用
水泳選手の肉体の進化
見えるものと見えないもの
医者たち
ジャコモ・カサノヴァ、テフロン加工風の転ばぬ先の杖
「オレはリスク・テイカーだ」
私は黒い白鳥――人間バイアス
かりそめのなぜなら
第9章
お遊びの誤り、またの名をオタクの不確実性
デブのトニー
ブルックリンじゃないジョン
コモ湖のほとりで昼ごはん
オタクの不確実性
間違ったサイコロでギャンブル
第1部のまとめ
浅はかなものほど表に出る
霊長類からの隔たり
第2部
私たちには先が見えない
ヨギ・ベラからアンリ・ポワンカレへ
第10章
予測のスキャンダル
エカチェリーナの男の数の曖昧さについて
黒い白鳥を見るのに不自由、再び
推測と予測|情報は知識に悪い
専門家の問題、あるいは空っぽのスーツの悲劇
動くものと動かないもの
最後に笑うには
事件とは突拍子もないもの
牛みたいに群れる
オレは「ほとんど」正しかった
現実性?なんで?
「それ以外は」うまくいった
テクノロジーの美しさ――エクセルのスプレッドシート
予測誤差の性質
川の深さが(平均で)四フィートなら渡ってはいけない
ほかの仕事を見つけろよ
JFKにて
索引
[下巻]・目次第11章 鳥のフンを探して
第12章 夢の認識主義社会
第13章 画家のアペレス、あるいは予測が無理ならどうする?
第3部 果ての国に棲む灰色の白鳥
第14章 月並みの国から果ての国、また月並みの国へ
第15章 ベル・カーブ、この壮大な知的サギ
第16章 まぐれの美学
第17章 ロックの狂える人、あるいはいけない所にベル型カーブ
第18章 まめかしの不確実性
第4部 おしまい
第9章 半分ずつ、あるいは黒い白鳥に立ち向かうには
エピローグイェフゲニアの白い白鳥
謝辞
訳者あとがき
参考文献
注解
用語集
索引
プロローグ
鳥の羽根の色
オーストラリアが発見されるまで、旧世界の人たちは白鳥と言えばすべて白いものだと信じて疑わなかった。経験的にも証拠は完璧にそろっているように思えたから、みんな覆しようのないぐらい確信していた。はじめて黒い白鳥が発見されたとき、一部の鳥類学者(それに鳥の色がものすごく気になる人たち)は驚き、とても興味を持ったことだろう。
でも、この話で大事なのはそういうところではない。この話は、人間が経験や観察から学べることはとても限られていること、それに、人間の知識はとてももろいことを描き出している。何千年 にもわたって何百万羽も白い白鳥を観察して確認してきた当たり前の話が、たった一つの観察結果 で完全に覆されてしまった。そんなことを起こすのに必要なのは、黒い(それに、聞いたところだ とかなり醜い)鳥がたった一羽、それだけだ。
この哲学的・論理学的な問題をもう一歩進めて、私たちが経験する現実に当てはめよう。私が子 どものころから取り憑かれてきた問題だ。この本で黒い白鳥と言ったら、それはほとんどの場合、次の三つの特徴を備えた事象を指す。
次の三つの特徴を備えた事象を指す。
第一に、異常であること。つまり、過去に照らせば、そんなことが起こるかもしれないとはっきり示すものは何もなく、普通に考えられる範囲の外側にあること。第二に、とても大きな衝撃があること。そして第三に、異常であるにもかかわらず、私たち人間は、生まれついての性質で、それ が起こってから適当な説明をでっち上げて筋道をつけたり、予測が可能だったことにしてしまったりすること。
ちょっと立ち止まって、この三つ子の特徴をまとめてみよう。普通は起こらないこと、とても大きな衝撃があること、そして(事前ではなく)事後には予測が可能であることだ。一握りの黒い白 鳥で、人間の世界がほとんど説明できてしまう。アイディアや宗教の成功から歴史的な事件の経緯、 私たちの私生活のいろいろな要素まで、なんでも説明できる。一万年ほど前に更新世が終わって以 来、こうした黒い白鳥の影響はどんどん大きくなっている。産業革命の間に加速が始まり、世界が より複雑になる一方、私たちが新聞を読んで調べたり、論じたり、予測したりする普通の出来事は、 ますますどうでもよくなってきている。
一九一四年に事件が起こる直前、私たちがどれだけ世界のことを知らなかったか考えてみればいい。それで、その次に何が起こるか、どれだけ予測できたか想像してみるのだ。(高校のくだらない先生が、あなたの頭蓋骨の内側にねじ込んだ說明を使うなんてズルをしてはいけない。)ヒトラ ーの台頭、それに続く戦争なんて予測できただろうか? ソヴィエト圏の急激な崩壊はどうだろ う? イスラム原理主義の台頭はどうなんだ? インターネットの浸透は予想できただろうか?
一九八七年の市場の暴落(と、それよりもさらに予想外だった回復)はどうだ? 一発屋、流行、 ファッション、アイディア、芸術分野や流派の勃興、そうしたものが全部、黒い白鳥の挙動に従う。 私たちのまわりにあるものごとなら、文字どおりほとんどなんにでも黒い白鳥が当てはまる。
予測が難しく、大きな衝撃を与えるというだけでも黒い白鳥は十分に不思議な生き物だが、この 本が主に扱うのはそういう点ではない。そういう現象に加えて、私たちは黒い白鳥なんていないフ リまでする!あなたやあなたの従兄弟のジョーイやわたしだけがそうなのではなくて、「社会科 学者」はほとんどそうだ。彼らは一世紀以上もの間、自分たちのやり方で不確実性がちゃんと測れるなんて思い込んで仕事をしている。でも、その手の不確実性の科学を現実の世界に応用しようと すると、とんでもないことになる。
運よく、私は金融や経済の分野でそういう例を目の当たりにしてきた。自分のポートフォリオ・ マネジャーに、あなたにとって「リスク」とはどんなものですかと聞いてみればいい。たぶん、黒い白鳥がやってくる可能性を取り除いた測り方について、とうとうと語ってくれるだろう。そういうやり方でリスクを測っても、予測能力は星占いと変わらない(この手の人たちが知的サギを数学 で飾りつける様子は、この本にたびたび登場する)。社会を扱う分野では、この問題は風土病みたいに根づいている。
この本が主として扱うのは、人間にはランダム性、とくに大きな変動が見えないという問題であ る。科学者の連中もそうでない人たちも、やり手の人も凡人のジョーも、どうして木を見て森を見 ないのだろう?どうして人間はどうでもいい細かいことばかり気にして、重要で大きな事件が起こる可能性は気にならないのだろう? どう見ても、大きな事件のほうがとても深刻な影響を及ぼすのに? それから、私の言うことがわかるなら、新聞を読むと世の中のことがかえってわからなくなるのはどうしてだろう?
人生は大きな出来事がいくつか積み重なってできている。これは簡単にわかるだろう。安楽椅子 に座ったままで(なんならバーの椅子でもいい)、黒い白鳥の果たす役割に思いをはせるのは、それほど難しくない。こんなことをやってみればいい。自分の存在を見直すのだ。自分が生まれてから身のまわりに起こった大きな事件や技術革新や発明を並べてみて、それが発明される前に予想されていたことと比べるのだ。
スケジュールどおりに起こったことがいくつある? 自分の生活を考 えてみよう。たとえば、仕事選びでも、つれあいとの出会いでも、生まれ故郷からの亡命でも、誰 かの裏切りでも、急にお金持ちになったことでも、急に貧乏になったことでもいい。その中で、あらかじめ立てた計画どおりに起こったことがいくつある?
わからないこと
黒い白鳥の論理では、わかっていることよりかからないことのほうがずっと大事だ。黒い白鳥は、 予期されていないからこそ起こるし、だからこそ大変なのだ。
二〇〇一年九月一一日のテロ攻撃を考えてみればいい。九月一〇日の段階で、ああいうことが起 こる可能性がそれなりに想定できていたなら、そもそもああいう事件は起こらなかった。そういう 可能性にも気をつけたほうがいいということになれば、戦闘機が世界貿易センターの上をぐるぐる回っていただろうし、旅客機のほうも防弾ドアをつけて鍵をかけていただろう。テロ攻撃は起こら なかった、マル。何かほかのことが起こっていたはずだ。何が起こっていたか? それはわからない。
事件が起こるのは、まさしく起こるはずもなかったからだなんて、おかしなことだと思いません か? そういうことから、どうやって身を守ったらいいんだろう? 何か(たとえばニューヨーク はテロの標的になりやすいことが)わかっても、こちらが知っていると敵が知ってしまえば、それ がなんであれ、もうとるに足らないことになってしまう。こういう戦略的ゲームでは、わかっていることはもう本当に関係なくなってしまう。ヘンな話だ。
同じことが仕事全般に当てはまる。レストラン業界で大ヒットを生み出す「秘密のレシピ」を考 えてみよう。そんなものがわかっていて簡単だったら、誰かそこら辺の人がもう思いついているだろうから、ありふれたレシピになってしまう。レストラン業界の次の大ヒットは、レストラン経営 者の今の母集団がそう簡単には思いつかないアイディアでないといけない。予想と違っていないと いけない。
そういう試みの成功が予想外であればあるほど、競争相手は少なくなるし、そんなアイ ディアを実行した起業家の成功は大きくなる。同じことが靴のメーカーにも、本の業界にも、それこそどんな仕事にだって当てはまる。科学的な仮説もそうだ。些細なことなんか誰も興味を持たな い。一般的に、人が思い切ったことをして得るものの大きさは、予想されていたものと逆相関する。
二〇〇四年に太平洋で起こった津波を考えてみよう。あれがあらかじめ予想されていたことだったら、あれほどの被害にはならなかっただろう。被害を受けた地域にはあまり人もいなかっただろうし、早めに警戒体制が敷かれていただろう。最初からわかっていることなら、あんまりひどいことにはならない。
専門家と「空っぽのスーツ」
外れ値を予測できないということは、歴史のための道か予測できないということだ。外れ値がさまざまな事件に占める割合を考えると、そういうことになる。
それなのに、私たちは歴史的な事件を予測できるかのように振る舞っている。もっと悪くすると、 歴史の行く末を左右できるかのように振る舞っている。社会保障制度の赤字だの石油価格だのを三 ○年先まで予測するとき、来年の夏にそういった数字がどうなっているかさえ、自分たちがろくに 予測できないのを忘れている。政治や経済に起こることを読み誤り、そうした予測の誤りが山のように積み重なっている。実績を調べるたびに、悪い夢でも見てるんじゃないかと頬をつねらないと いけないほどだ。
そして驚きなのは、予測の間違いの大きさではなくて、私たちがそれに気づいていないことのほうだ。こういうのは、命をかけて戦うようなときだといっそうやっかいだ。戦争の行方は本質的に 予測できない(そして私たちにはそれがわからない)。私たちは方針と行動を結ぶ因果の鎖をわかっていないから、無知を積極的に振り回して簡単に黒い白鳥を起こしてしまう。化学実験セットを もらった子どもみたいなものだ。
黒い白鳥に支配される環境では予測がきかない。それが私たちにはわからない。この二つが合わさって、人はある種の仕事に就くと、自分はもののわかった専門家だなんて思い込むことになる。 でも、実際にはまったくわかっていない。彼らの専門分野での実績を見ると、普通の人たちからなる母集団とまったく変わらない。彼らはただ、講釈をたれるのがうまいだけだし、もっと悪くする と、こんがらがった数学モデルで人を煙に巻くのがうまいだけだったりする。ついでに、そういう 連中はネクタイを締めている可能性が高い。
黒い白鳥は予測できない。私たちは(予測しようなんて無邪気にたくらむのではなく)、黒い白 鳥がいる世界に順応するほかない。反知識、つまりわからないことに焦点を絞るなら、できること はたくさんある。うまいやり方はいろいろあるけれど、要は思いがけない(いいことがある類の) 黒い白鳥を集め、それに対するエクスポージャー(受ける影響の大きさ)を最大限まで高めるのだ。 実際のところ、科学的発見とかベンチャー・キャピタル投資とかといった分野では、わからないことから得られるペイオフ(報い)は非常に大きい。失うものなんてほとんどなく、万が一のことが 起これば得られるものはとても大きいからだ。
今後見ていくように、社会科学で教えているのとは違って、設計図や計画にもとづいて実現した 大きな技術革新なんていうものはない。技術革新は黒い白鳥なのだ。発明家や起業家がとる作戦は、 全体を描く計画はあまりあてにせず、できるだけあれこれいじくりまわして、チャンスがやってき たときに、それを捕まえるというやり方だ。だからマルクスやアダム・スミスの徒には同意できな い。自由な市場がうまくいくのは、人が積極的に試行錯誤をして運のいい思いをするのを認めるか らだ。能力に対する報酬だの「インセンティブ」だのを与えるからではない。それならとるべき作戦は、ありとあらゆることをやってみて、黒い白鳥を捕まえるチャンスをできる限り集めるという やり方になる。
学ぶことを学ぶ
関連する人間の欠陥にはもう一つ、知っていることにばかり集中しすぎる点がある。細かいこと にばかり目が行って、全体像が見えない。
九・一一の出来事から人は何を学んだだろう? ものごとは予測ができる領域の外側で展開する ことがあるのを学んだだろうか? NOだ。通念には最初から欠陥が組み込まれているのを学んだ だろうか? NOだ。それじゃあ、何を学んだんだろう? 彼らが学んだことと言えば、イスラム 教のテロリスト予備軍と背の高いビルは避けて通ったほうがいい、そんなおうむ返しなルールぐらいだ。
知識を「理論化」するより、地面に足をつけて一歩一歩進むのが大事だ。そう思い起こさせてくれるものはいくらでもある。人間が具体的な細かいことにどれだけ捉われるようにできているか、 マジノ線を見ればよくわかる。大戦後、フランスはドイツが再び侵略してこないように、前回ドイ ツが進入してきたルートに壁をつくった。で、ヒトラーが(ほとんど)苦もなくそれを回り込んだ。 フランス人は歴史からよく学ぶ人たちだ。ただ、おうむ返しに学びすぎる。彼らは現実的すぎていて、同時に、自分たちの身の安全ばかり気にしているのである。
私たちは、私たちは学ばないということを私たちは学ばないということを自然とは学ばない。問題は私たちの頭の構造にある。私たちは法則を学ばない。事実ばかり学ぶ。事実しか学ばない。ど うやら、メタ法則(私たちは法則を学ばないといったような法則)がうまく理解できないようだ。 私たちは抽象的なことをバカにする。しかも、熱心にバカにするのだ。
どうしてだろう? ここで通念をひっくり返してみないといけない。複雑でどんどん再帰性が高 まる現代の環境では、通念はまったく通用しないのを理解する必要がある。これはこの本で論じる 重要な点でもある。
でも、問題はもっと根深い。そもそも私たちの頭はなんのためにあるんだろう? なんだか間違った取扱説明書がついてきたみたいだ。私たちの頭は、何かを考えたり自分を顧みたりするように はできていないようだ。そんなふうにできていたら、今ごろ私たちも楽ができたのだろうが、代わりに、今ごろこうやって生きてはいない。私もここにいてこんな話をしてはいないだろう。目の前 で起こっていることに注意せず、自分を振り返って考え込んでばかりいる私の先祖はライオンに食 われてしまい、一方、ろくに考えもせずに、とりあえず反応する彼の従兄弟はとっとと逃げおおせるだろう。考えるのには時間がかかるし、そもそも大変なエネルギーの無駄遣いだ。
私たちの祖先は一億年以上にわたって脳みそを使わない哺乳類の動物として過ごしてきた。やっ と脳みそを使い出したのは、歴史の中ではほんの一瞬にすぎない。ごく最近になっても、何に使っていたかと言えば枝葉末節のどうでもいいことばかりだ。証拠を見る限り、私たちは自分で思って いるほどものを考えてはいない。もちろん、そのこと自体を考えるときは別にして、ということだ けれども。
目次 – ブラック・スワン[下]―不確実性とリスクの本質
目次

第11章
鳥のフンを探して
鳥のフンの探し方
うっかり発見
答えが問いを待っている
探し続けろ
自分の予測を予測する!
N番目のビリヤード・ボール
第三共和国の流儀
三体問題
いまだにハイエクを無視する
オタクにならないために
学術自由主義
予測と自由意志
エメラルドはグルー
偉大なる予測機械
第12章
夢の認識主義社会
ムッシュー・ド・モンテーニュ、認識主義者
認識主義
過去の過去、過去の未来
予測、間違った予測、そして幸せ
ヘレノスと逆さまの予言
溶ける角氷
もう一度、不完全な情報
彼らが知識と呼ぶもの
第13章画家のアペレス、あるいは予測が無理ならどうする?
アドバイスはやすし。とてもやすし―
正しいときにバカになる
身構えろ
よい偶然というアイディア―
黒い白鳥のボラティリティとリスク
バーベル戦略
「誰にもなんにもわかりゃしない」
壮大な非対称性
第3部
果ての国に棲む灰色の白鳥
第14章
月並みの国から果ての国、また月並みの国へ
この世は何かと不公平
マタイ効果
共通言語り
アイディアと伝染
果ての国では誰も安心できない―
ブルックリンのフランス人的
長い尻尾
考えの甘いグローバリゼーション
果ての国から逆戻り―
第15章
ベル・カーブ、この壮大な知的サギ
ガウス的なものとマンデルブロ的なもの―
減少の増加
マンデルブロ的なもの
覚えておくこと
不平等
果ての国と80/20ルール
草と木
コーヒーを飲んでも安全なのはなぜか
確かなものが好き
大惨事の起こし方
ケトレの月並みなバケモノ――
光り輝く月並み
神様の誤り
ポワンカレの救いの手引
不公平な影響を取り除く
「ギリシャ人なら神とあがめただろう」
YESかNOか
(文系的)思考実験――ベル型カーブはどうやってできるか――
都合のいい仮定
「ガウス分布はどこにでも」
第6章
まぐれの美学
まぐれの詩人―
三角形のプラトン性―
自然の幾何学
フラクタル性
果ての国と月並みの国への視覚的な接近
豚に真珠
フラクタル的ランダム性の論理(ただし注意書きつき)
上限という問題
厳密さにはご用心
水たまり再び
描写から現実へ
もう一度、予測をするなら気をつけろー
もう一度、幸せな解決
灰色の白鳥はどこに?―
第17章
ロックの狂える人、あるいはいけない所にベル型カーブ
たったの五〇年
サラリーマンの裏切り
誰でも大統領に
怖い話をもっと
追認
ただの黒い白鳥―
ものごとを「証明」する方法
第18章
まやかしの不確実性
お遊びの誤り、再び―
インチキを見破れ
哲学者は社会に害をなせるか?
実践の問題
ウィトゲンシュタインは何人までピンの頭で踊れるか?
ここぞというときにポパーはどこへ行った?
坊主とアナリスト
思っているより簡単――懐疑主義者としての意思決定の問題
第4部
おしまい
第19章
半分ずつ、あるいは黒い白鳥に立ち向かうには
電車に乗り遅れても平気なとき
おしまい―
エピローグ――イェフゲニアの白い白鳥
謝辞
訳者あとがき
参考文献
注解
用語集
索引
プロローグ
第1部 ウンベルト・エーコの反蔵書、あるいは認められたい私たちのやり口
第1章 実証的懐疑主義者への道
第2章 イェフゲニアの黒い白鳥第3章
第3章 投機家と売春婦
第4章 千と一日、あるいはだまされないために
第5章 追認、ああ追認
第6章 講釈の誤り
第7章 希望の控えの間で暮らす
第8章 ジャコモ・カサノヴァの尽きない運―物言わぬ証拠の問題
第9章 お遊びの誤り、またの名をオタクの不確実性
第2部 私たちには先が見えない
第10章 予測のスキャンダル
索引
第19章 半分ずつ、あるいは黒い白鳥に立ち向かうには
残りの半分。アペレスを思い出せ。電車を逃すのが残念なとき。
さて、最後の言葉を書くところまで来た。 私は、あるときはものすごく懐疑的で、そうでないときは確実なものにこだわり、ものすごく頑 固で決して妥協しない。もちろん、私がとても懐疑的になるのは、ほかの人が信じやすいところで ある。とくに私が教養俗物と呼ぶ連中が信じやすくなるところでは、私はとても懐疑的になる。一 方、ほかの人たちが懐疑的になりそうなところでは、私は信じやすくなる。私は追認を疑うけれど、 それは間違えばとても痛い目に遭うときだけで、反追認は疑わない。
データがいくらあっても追認 にはならない。でも一つ事例があれば、追認を棄却するのに十分なこともある。私は強いランダム 性があると思うところでは疑い深くなるし、弱いランダム性の下では信じやすくなる。 私は黒い白鳥が大嫌いで、それ以外のときは黒い白鳥が大好きだ。人生に機微を与えるランダム性やよい方の偶然、画家のアペレスの成功、ツケが回ることのないありがたい贈り物は大好きだ。 アペレスの話の美しさがわかる人はほとんどいない。実際、間違いを避けようと、自分の中に棲むアペレスを押さえ込んでしまう人は多い。 自分自身にかかわることでも、私は、あるときはものすごく保守的で、そうでないときはものすごく積極的だ。そういう人は珍しくないかもしれない。でも、私が保守的になるのはほかの人がリ スクをとるところだし、積極的になるのはほかの人が用心するところだ。
小さな失敗はそれほど心配しない。大きな失敗、とくに致命的になりそうな失敗はとても心配す る。投機的なベンチャー企業より、「有望な」株式市場、とくに「安全な」優良株に不安を感じる。 後者は見えないリスクの代表だ。前者は、変動が大きいのが最初からわかっているし、投資する額 を小さくして、裏目に出たときの損を抑えることができるから、不意をつかれて驚くことはない。
世に騒がれる華々しいリスクは、それほど心配しない。たちの悪い隠れたリスクを心配する。テ 口を心配しない。糖尿病を心配する。はっきり見える不安だからという理由で人が普通に心配する ことよりも、私たちの意識の外側にあって人の話に出てこない、そんなことのほうを心配する(もう一つ、私はあんまりあれこれ悩まないというほうも告白しておく。つまり、私は自分でなんとか できることしか心配しないようにしている)。私は恥をかくことよりチャンスを逃すことのほうを 心配する。
結局、これは全部、ちょっとした意思決定のルール一つに根ざしている。よい方の黒い白鳥にさ らされ、失敗しても失うものが小さいときはとても積極的になり、悪い方の黒い白鳥にさらされているときはとても保守的になる。モデルの誤りがあっても、それでいい思いができるときはとても 積極的になるし、誤りで痛い思いをする可能性があるときは被害妄想みたいになる。そんなの当たり前だと思うかもしれないが、ほかの人たちはまったくそんなことをしていないのだ。たとえば金 融では、浅はかな理論を振り回してリスクを管理し、突拍子もない考えは「合理性」のじゅうたん の下に押し込んでしまう。
私は、あるときは学者で、そうでないときはたわごとの嫌いな実践の人だ。つまり、学術的なことではたわごとを嫌う現実的な人間であり、現実的なことになると学者になる。
私は、あるときはだまされやすく、そうでないときはだまされないようにしたいと思う。美術に 関しては、私はすぐにだまされる。リスクとリターンという文脈ではだまされたくない。私の美的 感覚では、散文より詩、ローマ人よりギリシャ人、優雅さよりも矜持、教養よりも優雅さ、見識よりも教養、知識よりも見識、知性よりも知識、そして真理よりも知性のほうが好きだ。でも、そう いうのは黒い白鳥が現れないところだけだ。黒い白鳥のいないところでは、私たちはとても合理的 になりがちだ。
私が知っている人の半分は私を不遜なやつだと言い(あなたの地元にいる教授について私が言ったことを読んだでしょう)、半分はこびへつらったやつだと言う(ユェ、ベール、ポパー、ポワン カレ、モンテーニュ、ハイエク、その他には奴隷みたいに身を捧げているのを見たでしょう)。
私は、あるときはニーチェが大嫌いだし、そうでないときは、彼の散文が大好きだ。
電車に乗り遅れても平気なとき
あるとき、人生を大きく変えるアドバイスをもう一つもらった。第3章に出てきた友だちからの アドバイスと違って、今度のアドバイスは、使えて、賢くて、実証的に正しかった。パリでのクラ スメートで、小説家志望のジャン=オリヴィエ・テデスコは、私が地下鉄に飛び乗ろうと走り出す のを止めてこう言ったのだ。「電車なんかで走るなよ」
自分の運命なんぞ鼻で笑ってやれ。私は自分に、予定に合わせようと泡を食って走り回らないようにしろと教えてきた。これはとても小さなアドバイスのように思えるかもしれない。でも、しっ かり心に残った。電車を捕まえようと走ったりするのをやめて、私は優雅で美しい所作の本当の価 値を知った。自分の時間や自分の予定、そして自分の人生を自分で思いのままにするということだ。 電車な逃いて残念なのは捕まえようと急いだときだけだ! 同じように、ほかの人があなたに期待 する成功に追いつこうとするのがつらいのは、まさしく、そんなことをしようとするからである。
自分の意志でイタチごっこや序列を捨てるのなら、それはイタチごっこや序列を外れるのではなく超えるということだ。
給料の高い仕事を自分から辞めれば、お金で得られるよりも高い満足が手に入る(頭がおかしく なったかと思うかもしれないが、やった私が言う。本当だ)。これは運命に四文字言葉を投げつけ た、ストア派の理性主義にいたる道の第一歩かもしれない。自分の土俵を自分で決めれば、自分の人生がそれまでよりずっと思いのままになる。
母なる自然は、私たちに自分を守る仕組みをくれた。イソップの寓話にあるように、そんな仕組 みの一つは、手が届かなかった(あるいは手に入れなかった)ブドウはすっぱいに違いないと思える能力だ。でも、最初からブドウなんてバカにして相手にしないという積極的な理性主義のほうが もっと実り多い。積極的に行こう。ガッツがあるなら、仕事を捨てられる人間になろう。
自分でつくったゲームなら、だいたいは負け犬にはならない。
黒い白鳥の文脈で言えばこうなる。ありえないことが起こる危険にさらされるのは、黒い白鳥に 自分を振り回すのを許してしまったときだけだ。自分のすることなら、いつだって自分の思いのままにできる。だから、それを自分の目指すものにするのである。
おしまい
でもそんな考えも、帰納の哲学も知識の問題も、強いランダム性がくれるチャンスも怖いぐらい の損が出る可能性も、こんな形而上学的なことを考えると、みんな色あせる。
私は、ごはんがまずかったとかコーヒーが冷たかったとか、デートを断られたとか受付が感じ悪 かったとかで、一日中惨めだったり怒っていたりする人に出くわしてびっくりすることがある。第 8章で、人生を左右する事象の本当のオッズはなかなかわからないという話を書いた。ただ生きて いるというだけでものすごく運がいいのを、私たちはすぐに忘れてしまう。それ自体がとても稀な事象であり、ものすごく小さな確率でたまたま起こったことなのだ。
地球の一○億倍の大きさの惑星があって、その近くに塵が一粒漂っているのを想像してほしい。 あなたが生まれるオッズは塵のほうだ。だから、小さいことでくよくよするのはやめよう。贈り物 にお城をもらっておいて、風呂場のカビを気にするような恩知らずになってはいけない。もらった 馬の口を調べるなんてやめておこう。忘れないでくれ、あなた自身が黒い白鳥なのだ。読んでくれてありがとう。
目次 – 強さと脆さ: ブラック・スワンにどう備えるか
強さと脆さ――目次
 セクションI 母なる自然に学ぶ
セクションI 母なる自然に学ぶ
もっとも古い教え、もっとも賢い教え
ゆっくり、でもたっぷり散歩――
私の間違い
強さと脆さ――
保険としての無駄
大きいことは悪いこと――そして脆いこと
気候変動と「大きすぎる」汚染者
種の密度
他の種類の無駄
差違のない区別、区別のない差違
誤りに強い社会――
セクションⅡ なんで散歩するか、あるいはシステムはどうやって脆くなるか
バーベルをもういくつか――
つくられた平穏に気をつけろ
セクションⅢ マルガリータース・アンテ・ポルコース
メッセージに関する主な誤解――
自分の罪を拭い去るには
トラヴェルセ・デュ・デゼール
セクションⅣ アスペルガーと存在論的黒い白鳥
アスペルガー的確率――
未来を見るのに不自由、再び――
確率は主観的にならざるを得ない――
温度計で測る確率
セクションV 現代哲学の歴史における(たぶん)一番役に立つ問題
二次元に生きる――
稀な事象で理論に頼る――
クレタのエピメニデス
判断不能性定理
重要なのは影響の大きさ
現実から表現へ
ほんものの証明
事象一個の確率という誤り――
変動の認識の心理学
帰納の問題と複雑な領域での因果――
帰納
目隠しをしてスクールバスを運転する
セクションⅥ 第四象限
一番役に立つ問題の解決
デイヴィッド・フリードマンよ安らかに
判断――
地図と第四象限――
セクションⅦ 第四象限をどうするか
間違った地図は使わない 医原病という概念――
否定形のアドバイス
医原病とニヒリズムのレッテル
知慮の原則
現実の生活でバーベル戦略がとれないときに、第四象限を和らげるためには何をする(あるいはしない)のが賢いか
セクションⅧ 黒い白鳥に強い社会の原則一○箇条
セクションⅨ 汝の運命を愛せ
滅ぼされないためには ニヒル・ペルディティ
ザ・ブラック・スワンの逆襲 訳者あとがきに代えて
注解
『ブラック・スワン』用語集
参考文献
索引
目次 – ブラック・スワンの箴言
プロクルーステース

ギリシャ神話によると、プロクルーステースはアテネとエレウシースの間にあるアッティカのコリダラスに小さな地所を持つ、残酷な地主だった。エレウシースは祭儀が行われていた場所だ。プロクルーステースはおもてなしについて独特な考えを持っていた。彼は旅人を捕まえては豪勢な晩餐を与え、今晩はここで泊まれと言って少々変わったベッドへ連れて行く。プロクルーステースはベッドと旅人がぴったり合うようにした。旅人の背が高すぎると、旅人の脚を鋭い斧で切り落とした。旅人の背が低すぎると、身体を引き伸ばした(彼の本名はダマステース、あるいはポリュペーモーンだったと言われている。プロクルーステースはあだ名で、「伸ばす人」という意味だ)。
因果応報そのままに、プロクルーステースは自分が作った仕掛けにはまることになった。あるとき捕まえた旅人が怖いものなしのテーセウスだったのだ。英雄としてのキャリアを歩み、後にミノタウロスを退治する人である。いつもの晩餐が終わると、テーセウスはプロクルーステースをベッドに寝かせ、プロクルーステースの流儀に従い、ベッドに完璧に合うようにプロクルーステースの首をはねた。目には目をというヘラクレスの流儀に倣ったわけだ。
この話にはもっと邪悪な異聞もある(偽アポロドーロスの『ギリシャ神話』なんかにも入っている)。そっちだと、プロクルーステースのベッドは大きいのと小さいのの二つがあって、彼は背の低い人を大きいほう、背の高い人を小さいほうのベッドに寝かせたことになっている。
これから書く箴言はどれも、ある意味プロクルーステースのベッドにかかわるものだ。知識の限界、つまり自分には観察できないもの、見えないものや知らないものに直面すると、私たち人間は人生や世界を、わかりやすくてありふれた考え、目立つところにだけ焦点を当てた紋切り型、特定の用語、出来合いの講釈に押し込もうとする。そうやっていると、ときどきひどい結果を招くことになる。
さらに、どうやら私たちは、自分がものごとをそんなふうに後づけで仕分けているのに気づかないようだ。いつもお客にぴったりのスーツを作っていると鼻高々で、でも実際にやっていることはというと、お客の手足を手術で切ったり伸ばしたりしている、そんな仕立て屋みたいなものである。たとえば、私たちは学校のカリキュラムに合うように子供の頭をあれこれいじくりまわす。子供の頭に合うようにカリキュラムを決めているのではないのがわかっている人は少ない。
箴言は、説明してしまうと必ず輝きを失う。だから、詳しい話はあとがきまで取っておいて、とりあえずここでは、この本の核になるテーマを匂わせるだけにとどめることにする。この本の箴言はそれぞれ、私の主題である、自分にはわからないことに私たちはどう対処するか、そしてどう対処するべきかにまつわる考えを短く述べたものになっている。つまり、『ブラック・スワン』や『まぐれ』でもっと深く論じた私の主題だ。
プロクルーステースが象徴しているのは、ものを間違った枠に押し込むことだけではない。間違ったほうの変数、ここではベッドではなく人間のほうを調節することをも表している。私たちが「叡智」と呼ぶもの(それに高度な技術を合わせたもの)がうまくいかない状況は、どれもプロクルーステースのベッドになぞらえることができる。
ブラック・スワンの箴言■ 目次
プロクルーステース
序幕
逆説の一言
実在
聖なるものと卑なるもの
偶然、成功、幸せ、そして理性主義
カモの問題、かわいらしいのとそうでもないの
テーセウス、あるいは古の暮らしを生きる
哲学界
普遍なものと特殊なもの
まぐれ
美学
道德
強さと脆さ
お遊びの誤りと領域依存
認識論と引き算の知識
予測のスキャンダル
哲学者になること 哲学者であり続けること
経済的生活、その他の卑しい題材
賢きもの、弱きもの、気高きもの
陰陽
愛なるものと愛ならざるもののいろいろ
終幕
あとがき
謝辞
目次 – 反脆弱性[上]――不確実な世界を生き延びる唯一の考え方
目次

反脆弱性[上]
目次
章のまとめとマップ
プロローグ
I. 風を愛するには
Ⅱ. 反脆さ
予測に頼らない
反脆さを奪うとどうなるか
他者を犠牲にして利を得る「逆英雄」に気をつけよ
Ⅲ. ブラック・スワンの特効薬
頑健なだけじゃダメ
(一部の)モノの測定可能性について
フラジリスタ
シンプルなほど洗練されているケース
Ⅳ. 本書
(むしろ幸せな)無秩序一家
唯一無二の本
勇気なくして信念なし
何かを目撃したら……
化石化を進行させる
V. 構成
付録: 三つ組(三つの性質に沿ってとらえた万物の世界地図)
物事は三つ組で成り立っている
実際の三つ組
第1部 反脆さとは
第1章 ダモクレスとヒュドラーの間で
世の中のモノの半分には名前がない
私の首を刎ねてくれ
名前の必要性について
反脆さの祖先
領域非依存は領域依存
第2章 過剰補償と過剰反応はどこにでもある
心的外傷後成長とイノベーション
競馬で勝つ方法
冗長性としての反脆い反応
エビデンスペースのウェイト・トレーニング
暴動、愛、そしてストレスの意外なメリットに潜む反脆さについて
私の本を禁書にしてください―情報の反脆さ
別の仕事に就け
第3章 ネコと洗濯機
生命と無機物を分ける神秘、老化の2層構造
複雑系と非複雑系
ストレスは情報である
均衡なんてもううんざり
子どもに対する罪――薬漬けの社会が奪うもの
言語習得のいちばんのやり方
「観光客化」という現代病
偶然への密かな欲望
第4章 私が死ねば、誰かが強くなる
反脆さの階層構造
進化と予測不能性
生物は集団、集団は生物
間違いに感謝
他者の失敗から学ぶ
マザー・テレサになるには
なぜ集団は個を嫌うのか
私が死ななくても、誰かが死ぬ
「私」と「私たち」
起業記念日
第2部 現代性と、反脆さの否定
プロクルステスのベッド
第5章 青空市とオフィス・ビル
2種類の職業、2種類の運命
チューリッヒのレーニン
ボトムアップ型の変化
果ての国を離れて
大いなる七面鳥問題
1万2000年続く繁栄
戦争、牢獄、あるいは戦争と牢獄
パクス・ロマーナ
戦争の有無を生むもの
第6章 ランダム性は(ちょっとなら)すばらしい!
「たゆたえども沈まず」
腹ぺこのロバー
政治の「焼きなまし」
安定という名の時限爆弾
二次的影響―(小さな)戦争は命を救うか?
外交政策の立案者に告ぐ
「現代性」とは何か
第7章 浅はかな干渉―医原病
確率論的な殺人
干渉と「医原病」
何よりもまず、害をなすなかれ
医原病の反対とは
エラい人たちが起こす医原病
クジラはワシのように飛べるか?
何もしなくなくなくない?
浅はかでない干渉主義へ
先延ばしの妙――フェビアン戦略
産業化社会の神経症的傾向
ノイズと信号―合法的に人を殺すには
メディアがもたらす神経症
国家もたまには役に立つ――無能な国家なら
みんなが思うよりもめちゃくちゃな国、フランス
スウェーデンと巨大国家
「きっかけ=原因」という錯覚
第8章 予測は現代性の生みの子――ブラック・スワンの世界へ
予測の成績はいつも0点
ガミガミ屋のガミ子さんには敵が多い
予測が必要なのは誰か
虫歯のあるなし
七面鳥にならない
さらば、ブラック・スワン
第3部 予測無用の世界観
第9章 デブのトニーとフラジリスタたち
怠け者の旅行仲間
ランチの重要性
蔵書の反脆さ
カモか否か
ネロの孤独と「空気」同然の証拠
予測しない人間が予測できること
第10章 セネカの処世術
反脆さの問題を解決した裕福な哲学者
人生からダウンサイドを減らす
ストア哲学の「心を頑健にする法」
感情を手なずける
運命の主人になるには
根本的な非対称性
第11章 ロック・スターと10パーセント浮気する――バーベル戦略
壊れた小包の不可逆性について
セネカの「バーベル」
90パーセント会計士、10パーセント・ロック・スター
“黄金の中庸”を忘れよ
不確実性を手なずける
第4部 オプション性、技術、そして反脆さの知性
私たちは行き先を本当に理解しているのか?
「目的論的誤り」と「分別ある遊び人」
アメリカのいちばんの財産って?
第12章 タレスの甘いぶどう――オプション性
アリストテレスの「高度な」誤解
オプションと非対称性
「甘いぶどう」のオプション
「ロンドンで過ごす土曜の夜」のオプション性
「家賃」のオプション性
非対称性(オプションの)
「ばらつき」を好むもの
タレス的な人とアリストテレス的な人
バカになる方法、「賢者の石」
いじくり回し――自然はオプションを行使する
理性とは
人生はロング・ガンマだ
ローマの政治はオプション性がお好き
まとめ、そして次へ
第13章 島に飛び方を教える――ソビエト=ハーバード流の錯覚
車輪つきスーツケースにみる「発見」と「実用化」
見つけられるのを待っている「半発明」
もういちど言う、少ないほど豊かだ
ギャップにご注意
財宝の探索と、失敗が投資になりうる仕組み
創造的破壊と非創造的破壊
ソビエト=ハーバード大学の鳥類学部
「随伴現象」という名の思いこみ
危機の原因はいつだって「欲望」なのか
随伴現象の正体を暴く
いいとこ取り(=追認の誤り)
第14章 ふたつが同じものじゃないとき
アブダビに欠けているもの
ストレスはどこにある?
芸術のための芸術、学びのための学び
洗練された夕食の友――教育の本当のメリット
グリーン材の誤謬
デブのトニーはどうやって金持ちに(そしてデブに)なったか
同一化――あるものとその関数の混同
試行錯誤のプロメテウスと講釈のエピメテウス
第15章 敗者が綴る歴史――試行錯誤の汚名をすすぐ
学問は「手柄」を横取りする
私が「鳥に飛び方を教える」現象の誤りを暴いたとき
証拠がこっちを見つめている
料理とコンピューター科学は似ている?
産業革命(科学過大評価の事例1)
政府がお金をかけるべきなのは、研究ではなく非目的論的ないじくり回しである
医学(科学過大評価の事例2)
マット・リドレーの反目的論的な議論
企業の目的論――戦略に効果はない
逆七面鳥問題
7プラスマイナス2回、失敗する
偽医者、学者、見世物師
第16章 無秩序の教訓
生きた世界とお遊びの世界
教育ママの観光客化
反脆い(バーペル型の)教育――半自伝的教育論
反脆弱性 下 目次
第17章 デブのトニー、ソクラテスと相対す
第5部 あれも非線形、これも非線形
第18章 1個の大石と1000個の小石の違いについて
第19章 賢者の石とその逆
第6部 否定の道
第20章 時と脆さ
第21章 医学、女性、不透明性
第22章 ほどほどに長生きする――「引き算」の力
第7部 脆さと反脆さの倫理
第23章 身銭を切る――他人の犠牲と引き換えに得る反脆さとオプション性
第24章 倫理を職業に合わせる――自由と自立
第25章 結論
エピローグ 生まれ変わりに生まれ変わりを重ねて
謝辞
参考文献
追記、補足、関連図書
付録Ⅱ(非常に専門的)
付録Ⅰ
用語集
章のまとめとマップ
第1部 反脆さとは
第1章 「反脆さ」という言葉が教室で見落とされていたことを説明する。脆弱・頑健・反脆弱とダモクレス・フェニックス・ヒュドラー。領域依存性。
第2章 過剰補償が起こる場所とは。経済学以外では、執着的な愛情ほど反脆いものはない。
第3章 有機体と人工物の違い。人生から変動性を吸い取ろうとする観光客化。
第4章 多くの場合、全体の反脆さは部分の脆さに依存する。人生に死が必要なワケ。失敗が全体にもたらす利益。リスク・テイカーが必要な理由。この点を見逃している現代性について二言三言。起業家とリスク・テイカーへの敬意。
第2部 現代性と、反脆さの否定
プロクルステスのベッド
第5章 ランダム性の2種類のカテゴリーを、その性質から読み解く。スイスはなぜトップダウンじゃないのか。月並みの国と果ての国の違い。都市国家、ボトムアップ型の政治システム、地方自治体のノイズが持つ安定化作用のメリット。
第6章 ランダム性を好むシステム。物理学内外の焼きなまし手法。有機体や複雑系(政治、経済など)を過度に安定化させることの影響について説明する。知識偏重主義の功罪。アメリカの外交政策と似非安定化。
第7章 現代性の産物の中でいちばん軽視されている、浅はかな干渉と医原病について。ノイズとシグナル。ノイズによる過剰な干渉。
第8章 予測は現代性の生みの子。
第3部 予測無用の世界観
第9章 脆さを嗅ぎ取る名人、デブのトニー。ネロ。長い昼食。フラジリスタから金を搾り取る。
第10章 自分の作った薬を飲もうとしないトリファット教授。反脆いものは必ずダウンサイドよりもアップサイドのほうが多いので、変動性、間違い、ストレスで得をする。これを根本的な非対称性という。これをセネカとストア哲学にたとえて説明する。
第11章 組み合わせていいものといけないもの。人生におけるバーベル戦略。脆さを反脆さへと変換するもの。
第4部 オプション性、技術、そして反脆さの知性
(秩序好きの教育と無秩序好きのイノベーションの対立関係)
第12章タレス対アリストテレス。状況を理解していなくてもへっちゃらなオプション性という概念。同一化のせいでオプション性が誤解されている理由。オプション性を見落としていたアリストテレス。私生活の中のオプション性。いじくり回しが計画よりも効果を発揮する条件。分別ある遊び人。
第13章 成長の裏にある非対称的なペイオフについて。ソビエト=ハーバード流の錯覚、別名「鳥に飛び方を教える」現象。随伴現象。
第14章 グリーン材の誤謬。エピステーメー(知識)と試行錯誤の対立関係と、その歴史を通じた役割。知識は富を生むのか?そうだとすれば、どんな知識が? 知識と宮が同じものじゃないとき。
第15章 技術史の書き直し。科学の世界で、歴史は敗者によってどう書き直されるのか。私がトレーダーの世界で目撃した歴史の書き直し。その一般化。生物学の知識は医療の邪魔になるのか?隠蔽されている運の役割。よい起業家とは何か?
第16章 教育ママへの対処法。遊び人の教育。
第17章 デブのトニー、ソクラテスと相対す。私たちはどうして、説明不能なことを実行できないのか? そして自分の行動を説明せずにはいられないのか? ディオニュソス的。「カモか否か」で物事を考える。
第5部 あれも非線形、これも非線形
第18章 凸性、凹性、凸効果。規模そのものが脆さを生む理由。
第19章 賢者の石。凸性についてさらに詳しく。ファニー・メイはどうして破綻した? 非線形性。脆さと反脆さを見分けるヒューリスティック。凸バイアス、イェンゼンの不等式と、それらが無知に及ぼす影響。
第6部 否定の道
第20章 最新性愛症。「否定の道」で未来を観る。リンディ効果(新しいものより古いもののほうが、その年齢に比例して長く生き残る)。エンペドクレスの煉瓦。非合理的なもののほうが、一見すると合理的なものより勝るワケ。
第21章 医学と非対称性。医療問題における意思決定の法則。重病患者のペイオフが凸で、ぴんぴんした人のエクスポージャーが凹である理由。
第22章 引き算的な医療。環境内のランダム性の種類と個人との相性について。私が不死になんてなりたくないワケ。
第7部 脆さと反脆さの倫理
第23章 脆さを移転させるエージェンシー問題。身銭を切る。ドクサ的コミットメント。または魂を捧げる。ロバート・ルービン問題、ジョセフ・スティグリッツ問題、アラン・ブラインダー問題。三つともエージェンシー問題であり、ひとつはいいとこ取りの問題。
第24章 倫理のひっくり返し。個人個人に分別があっても、集団になると問違えることもある。人はどうやって意見にとらわれていくのか。そこから解放するには。
第25章 結論。
エピローグ ネロがレヴァントを訪れ、アドーニスの儀式を見学していると……。
プロローグ
I.風を愛するには
風 はろうそくの火を消すが、炎を燃え上がらせる。
それは、ランダム性、不確実性、無秩序も同じだ。それらから隠れるのではなく、利用しなければいけない。炎になって、風が吹くことを期待するのだ。このたとえは、ランダム性や不確実性に対する私の前向きな考え方をずばり言い表わしている。
不確実性を生き抜くだけじゃいけない。乗り切るだけでもいけない。不確実性を生き抜き、ローマ時代の積極的なストア哲学者たちのように、不確実性を自分のものにするべきなのだ。その目的は、見えないもの、不透明なもの、説明不能なものを手なずけ、支配し、さらには征服することだ。
でも、どうやって?
Ⅱ. 反脆さ
衝撃を利益に変えるものがある。そういうものは、変動性、ランダム性、無秩序、ストレスにさらされると成長・繁栄する。そして冒険、リスク、不確実性を愛する。こういう現象はちまたにあふれているというのに、「脆い」のちょうど逆に当たる単語はない。本書ではそれを「反脆い」または「反脆弱」(antifragile)と形容しよう。
反脆さは耐久力や頑健さを超越する。耐久力のあるものは、衝撃に耐え、現状をキープする。だが、反脆いものは衝撃を糧にする。この性質は、進化、文化、思想、革命、政治体制、技術的イノベーション、文化的・経済的な繁栄、企業の生存、美味しいレシピ(コニャックを一滴だけ垂らしたチキン・スープやタルタル・ステーキなど)、都市の隆盛、社会、法体系、赤道の熱帯雨林、菌耐性などなど、時とともに変化しつづけてきたどんなものにも当てはまる。地球上の種のひとつとしての人間の存在でさえ同じだ。そして、人間の身体のような生きているもの、有機的なもの、複合的なものと、机の上のホッチキスのような無機的なものとの違いは、反脆さがあるかどうかなのだ。
反脆いものはランダム性や不確実性を好む。つまり、この点が重要なのだが、反脆いものはある種の間違いさえも歓迎するのだ。反脆さには独特の性質がある。反脆さがあれば、私たちは未知に対処し、物事を理解しなくても行動することができる。しかも適切に。いや、もっと言おう。反脆さがあれば、人は考えるより行動するほうがずっと得意になる。ずば抜けて頭はよいけれど脆い人間と、バカだけれど反脆い人間、どちらになりたいかと訊かれたら、私はいつだって後者を選ぶ。
一定のストレスや変動性を好むものは、身の回りにいくらでも見つかる。経済システム、人間の身体や精神、それから栄養だってそうだ(糖尿病のような現代病の多くは、食事のランダム性やたまの絶食というストレスがないことと関連があるようだ)。また、反脆い金融商品なんてものまである。そういう商品は、市場のボラティリティ(変動性)で利益が出るよう意図的に設計されている。
反脆さを理解することは、脆さをもっと深く理解することに通じている。病気を減らさなければ健康にはなれないし、まず損失を減らさなければ金持ちにはなれない。それと同じで、反脆さと脆さは同じスペクトル上に並んでいるわけだ。
予測に頼らない
反脆さの仕組みを理解すれば、不確実な環境のもとで、予測に頼らずに意思決定を下すための体系的で包括的な指針を築くことができる。ビジネス、政治、医療、生活全般のように、未知が大部分を占める場所や、ランダムで、予測不能で、不透明で、物事を完璧に理解できない状況では、反脆さが大きな役割を果たす。
システムに害をもたらす事象の発生を予測するよりも、システムが脆いかどうかを見分けるほうがずっとラクだ。脆さは測れるが、リスクは測れない(リスクが測れるのは、カジノの世界や、”リスクの専門家”を自称する連中の頭の中だけの話だ)。私は、重大で稀少な事象のリスクを計算したり、その発生を予測したりすることはできないという事実を、「ブラック・スワン問題」と呼んでいる。脆さを測るのは、この問題の解決策となる。変動性による被害の受けやすさは測定できるし、その被害をもたらす事象を予測するよりはよっぽど簡単だ。だから、本書では、現代の予測、予知、リスク管理のアプローチを根底からひっくり返したいと思っている。
応用する分野や領域は何であれ、本書では、脆さを緩和したり反脆さを利用したりすることで、脆い状態から反脆い状態へと移転するための鉄則を提案する。そして、次の簡単な非対称性テストを使えば、たいていは反脆さ(や脆さ)を見極められる。ランダムな事象(や一定の衝撃)によるダウンサイド(潜在的損失)よりもアップサイド (潜在的利得)のほうが大きいものは反脆い。その逆のものは脆い。
反脆さを奪うとどうなるか
今日まで生き残ってきたありとあらゆる自然界の(複雑な)システムに、反脆さという性質が備わっているとすれば、変動性、ランダム性、ストレスを奪うのはかえってシステムにとって有害になるはずだ。システムはみるみる弱まり、死に、崩壊するだろう。私たちはランダム性や変動性を抑えこもうとするあまり、経済、健康、政治、教育など、ほとんどすべてのものを脆弱にしてきた。1か月も布団にくるまって、『戦争と平和』の完全版を読んだり、『ザ・ソプラノズ』の全部話を観たりしていれば、ストレスを失った筋肉は萎え、複雑な人体のシステムは衰え、悪くすれば死んでしまうかもしれない。現代の構造化された世界の大部分は、トップダウン型の政策やシステム (本書でいう「ソビエト=ハーバード流の錯覚」)を通じて、私たちを傷つけつづけている。ひと言でいえば、システムの持つ反脆さを侮辱しているわけだ。
これは現代性のもたらした悲劇だ。ノイローゼみたいに過保護な親や、よかれと思って何かをする人たちが、いちばんの加害者であることも多い。
トップダウン的なもののほとんどが脆さを生み出し、反脆さや成長を妨げているとすれば、ボトムアップ的なものはみな、適度なストレスや無秩序のもとで成長する。発見、イノベーション、技術的進歩のプロセス自体を担っているのは、学校教育ではなく、反脆いいじくり回しや積極的なリスク・テイクなのだ。
他者を犠牲にして利を得る「逆英雄」に気をつけよ
社会を脆くし、危機を生み出している主犯は、~身銭を切らない、人たちだ。世の中には、他者を犠牲にして、自分だけちゃっかりと反脆くなろうとする連中がいる。彼らは、変動性、変化、無秩序のアップサイド(利得)を独り占めし、損失や被害といったダウンサイド・リスクを他者に負わせるのだ。そして、このような他者の脆さと引き換えに手に入れる反脆さは目に見えない。ソビエト=ハーバード流の知識業界は反脆さに対して無知なので、この非対称性が着目されることはめったにないし、教えられることは(今のところ)まったくない。さらに、2008年に始まった金融危機でわかったように、現代の制度や政治事情が複雑化しているせいで、破綻のリスクを他者に押しつけても、簡単には見破られない。かつて、高い地位や要職に就く人というのは、リスクを冒し、自分の行動のダウンサイドを受け入れた者だけだった。そして、他者のためにそれをするのが英雄だった。ところが、今日ではまったく逆のことが起こっていて、逆英雄という新しい人種が続々と出現している。官僚。銀行家。ダボス会議に出席する国際人脈自慢協会の会員のみなさん。真のリスクを冒さず説明責任も果たしていないのに、権力だけはやたらとある学者など。彼らはシステムをいいように操作し、そのツケを市民に押しつけている。
歴史を見渡してみても、リスクを冒さない連中、個人的なエクスポージャーを抱えていない連中が、これほど幅を利かせている時代はない。
いちばん重要な倫理規範を挙げるとすればこうだ。他者の脆さと引き換えに反脆さを手に入れるべからず。
Ⅲ.ブラック・スワンの特効薬
私は、自分の理解できない世界で幸せに暮らしたい。
ブラック・スワンとは、巨大な影響をもたらす、大規模で、予測不能で、突発的な事象を意味する。ブラック・スワンの予測に失敗し、不意を衝かれ、被害を受けた人たち全般を、本書では「七面鳥」と呼ぶことにする。私がずっと主張してきたように、歴史の大半はブラック・スワン的な事象で成り立っている。なのに、私たちは正常な状態に関する知識を微調整して、モデル、理論、説明を構築しようとする。でも、そういうモデルではブラック・スワンを追跡することなどとうてい無理だし、衝撃の起こる確率を測定することもできない。 ブラック・スワンは私たちの脳を乗っ取り、ブラック・スワンを”なんとなく”とか”だいたい”予測していた気分にさせる。後付けならいくらでも説明がつくからだ。私たちはこの予測可能性という幻想に惑わされ、ブラック・スワンが人生において果たす役割に気づいていない。人生というのは、私たちの記憶の中にあるイメージよりも、ずっとずっと迷路のように入り組んでいる。人間の脳は、歴史を滑らかで線形的なものへと変えようと躍起になる。そのせいで、私たちはランダム性を過小評価してしまう。ところが、いったんブラック・スワンが姿を見せると、恐怖し、過剰反応する。この恐怖と秩序への渇望のせいで、人間のシステムは目に見えない(見えづらい)物事のロジックを破壊することがある。その結果、ブラック・スワンから損害をこうむることはよくあっても、利益を得ることはまずない。秩序を求めようとすれば、得られるのは似非秩序だ。ランダム性を受け入れてはじめて、一定の秩序と統制が得られるのだ。
複雑系は、見つけづらい相互依存性や非線形的な反応に満ちている。「非線形的」というのは、たとえば薬の用量や工場の労働者数を2倍にすると、効果が元のぴったり2倍ではなくて、それより増えたり減ったりするという意味だ。フィラデルフィアで2週間を過ごすのは、1週間過ごすより2倍楽しいかというと、そこまでじゃない。ソースは私だ。反応をグラフにすると、直線(「線形的」)にはならず、曲線になる。このような状況では、単純な因果関係を当てはめるのは間違いのもとになる。個々の部分を見ただけで、物事の全容をつかむのは難しいからだ。
人工的な複雑系では、暴走的な連鎖反応が起きることが多い。その結果、予測は難しく(時には不可能に)なり、思ってもみなかった規模の出来事が起こる。そのため、現代社会では、技術的知識はどんどん増えているのに、逆説的にも物事は今までよりずっと予測不能になっている。人工物が増え、昔のやり方や自然界のモデルが軽視され、あらゆる設計が複雑化して頑健さが失われている現代、ブラック・スワンの役割は高まりつつある。しかも、私たちは本書で「最新性愛症」と呼んでいる新しい病に冒されている。そのおかげで、私たちはブラック・スワンに対して脆弱な「進歩」という名のシステムを築いている。
ブラック・スワン問題には、困った一面がある。稀少な事象の確率はずばり計算不能であるということだ。これは実はとても大事な点なのだが、たいがい見落とされている。100年に1回の洪水は、5年に1回の洪水よりもはるかに予測しづらい。微小な確率となると、モデル誤差は一気に膨らむ。事象が であればあるほど、とらえづらくなり、発生頻度は計算しにくくなる。ところが、予測やモデリングを専門とし、学会でカラフルな背景色や数式を使ったパワーポイント・プレゼンテーションを行う^科学者、たちは、事象がまれであればあるほど、自信たっぷりになる。
幸いにも、反脆さを備えた母なる自然は、稀少な事象にかけては一流のエキスパートであり、ブラック・スワンの最高の管理者でもある。アイビー・リーグの大学で教育を受け、人事委員会から指名された取締役が指揮を執ったりしなくても、母なる自然は、その数十億年の歴史をここまで見事に生き抜いてきたのだ。反脆さはブラック・スワンの特効薬というだけではない。反脆さをきちんと理解すれば、私たちはブラック・スワンが歴史、技術、知識といったすべてのものにとって不可欠な役割を果たしていることを、知的に臆することなく受け入れられるようになるのだ。
頑健なだけじゃダメ
母なる自然は、安全、なだけじゃない。破壊や置き換え、選択や改造を積極的に繰り返す。ランダムな事象に関していえば、「頑健」なだけでは足りない。長い目で見れば、ほんのちょっとでも脆弱なものはすべて、容赦ない時の洗礼を受けて、壊される。それでも、私たちの地球はまあW億年くらいは生きている。とすれば、頑健さだけじゃない、何かがあると考えるのがふつうだ。小さな亀裂がシステム全体の崩壊につながらないためには、完璧なる頑健さが必要だ。だが完璧な頑健さなどありえないことを考えると、ランダムな事象、予測不能な衝撃、ストレス、変動性を敵に回すのではなく、味方につけ、自己再生しつづける仕組みが必要なのだ。
反脆いものは、長い目で見れば予測ミスから利益を得る。この考えに従うなら、ランダム性から利益を得る多くのものが今日の世界を支配し、ランダム性から害をこうむるものはとっくになくなっているはずだ。実をいうと、それが正解だ。私たちは、世界がプログラムされた設計、大学の研究、お役所的な助成で成り立っていると思っている。でも、これが実は錯覚だという強力な証拠がある。私はその錯覚を「鳥に飛び方を教える」現象と呼んでいる。技術というのは、オタクが作った設計図を押し入れにしまいこみ、リスク・テイカーたちがいじくり回し(試行錯誤)という形で反脆さを開拓する結果として生まれるものなのだ。モノを生み出すのはエンジニアや試行錯誤する人たちなのに、歴史書を書くのは学者だ。私たちは、成長やイノベーションなど、色んなものの歴史的解釈を見直す必要があるだろう。
(一部の)モノの測定可能性について
脆さはかなりのところまで測定できる。だが、リスクは測定できない。特に、稀少な事象にまつわるリスクとなれば、なおさら不可能だ。
*1 カジノの中や人工的な環境・構築物などのごく限られた世界は除く。
私たちは脆さや反脆さを評価し、さらには測定することさえできる。だが、人類がどれだけ高度化しても、衝撃的な出来事や稀少な事象のリスクや確率を計算することなんてできない。現在実践されているリスク管理は、未来にどんな出来事が起こるかを研究するものだ。しかし、そういう稀少な事象の将来的な発生率を”測定”できると豪語できるのは、一部の経済学者や狂人だけだ。そして、カモたちは過去の経験や予測の成績を忘れて、連中の話を「はいはい」と聞いてしまう。しかし、脆さや反脆さは、物質、コーヒー・テーブル、会社、産業、国家、政治体制に備わった性質のひとつだ。
とはいえ、リスク同士の比較は(今のところ)当てにならないとしても、脆さを見分け、観察し、たいていは測定することができる。少なくとも相対的な脆さなら、わずかな誤差の範囲内で測ることができるのだ。ある稀少な事象や災害が、別の事象よりも起こりやすいと信頼性を持って述べることはできないが(思いこむのが好きだというなら話は別だが)、ある事象が起きた場合に、こっちのモノや構造のほうがあっちよりも脆い、と断言するのはずっと簡単だ。気温の急激な変化に対して、あなた自身よりもあなたの祖母のほうが脆いとか、政治的な変化に対して、スイスよりもどこそこの軍事独裁政権のほうが脆いというのは、ちょっと考えればわかる。また、危機が起きた場合に、こっちの銀行のほうがあっちよりも脆いとか、地震が起きたときに、シャルトル大聖堂よりも現代の欠陥ビルのほうがよっぽど脆いというのも簡単にわかる。そして、重要なことに、どちらのほうが長く残るかを予測することだってできる。
憶測的で弱気なリスクの話なんかするヒマがあったら、私は脆さについて考えるべきだと思う。脆さには予測は無用だし、リスクとは違って、それとは機能的に正反対のものを言い表わせる面白い言葉もある。「反脆さ」という強気な概念だ。
反脆さを測るコツとして、コンパクトで単純化された法則を用いる「賢者の石」風の手法がある。この方法を使えば、健康から社会の構造まで、色々な分野の反脆さを見極められる。
私たちは実生活では無意識のうちに反脆さを利用している。ところが、知的な生活となると、意識的に反脆さを否定してしまうのだ。
フラジリスタ
理解できないものはいじらないでおこう、というのが本書の考えだ。だが困ったことに、世の中にはそれとまったく逆の連中がいる。本書で「フラジリスタ」と呼んでいるのがその種の連中だ。彼らは決まってスーツにネクタイという身なりで(たいてい金曜日にも)、ジョークを投げても能面のような表情を返してくる。椅子の座りすぎ、飛行機の乗りすぎ、新聞の読みすぎで、若いうちから早くも腰を痛めていることが多い。それから、かいぎとかいう奇妙な儀式によく参加する。それに加えて、自分に見えないものはそこにない、理解できないものは存在していないと思いこんでいる。根本的に、「未知のもの」を「存在しないもの」と誤解しているわけだ。
訳注1 フラジリスタ(fragilista)は、「脆さ」や「脆弱性」を意味する「fragility」と、「~する人」を表わす接尾辞「-ista」を組み合わせて作った造語と思われる。「-ista」は悪い意味を表わすことが 多い。日本語にすれば「脆さを生み出す連中」というくらいの意味。
フラジリスタは「ソビエト=ハーバード流の錯覚」に陥りやすい。これは科学的知識の適用範囲を(非科学的に)過大評価する現象だ。この錯覚を抱える人々は、「浅はかな合理主義者」「合理化主義者」、または単に「合理主義者」と呼ばれる。彼らは物事の根底にある「道理」が、自動的に理解可能なものだと決めつけている。だが、合理化と合理的を混同するのは禁物だ。このふたつはほとんど正反対だからだ。物理学以外の複雑系の分野全般では、物事の根底にある道理は私たちには理解しづらい。フラジリスタにはもっと理解しづらい。ところが、自己紹介をしてくれるユーザー・マニュアルがないというこの自然界の事物の性質は、悲しいことに、フラジリスタにとってはあんまり障害物にはならない。フラジリスタたちは彼らの「科学」の定義に従い、団結して自分の手でそのユーザー・マニュアルを書き上げるのだ。
フラジリスタのせいで、現代社会は世の中の神秘的なもの、不可知的なもの、ニーチェのいう「ディオニュソス的」なものに対して、ますます盲目になっている。
本書の登場人物であるデブのトニーは、これをブルックリンの言葉遣いで「カモのゲーム」と呼んでいる。ニーチェほど詩的ではないが、意味深さでは劣らない。
ひと言でいえば、(医療、経済、社会計画の分野の)フラジリスタとは、利得は些少で目に見えるが、潜在的な副作用は深刻で目に見えない、人工的な政策や活動を推し進めようとする連中のことだ。
医療のフラジリスタは、人体に備わる自然治癒能力を否定して過剰に医療介入し、とても重い副作用があるかもしれない薬を平気で処方する。政治のフラジリスタ(干渉主義の社会計画者)は、経済を(自分の手で)修理しつづけなきゃいけない洗濯機のようなものと勘違いし、経済を崩壊させる。精神医学のフラジリスタは、知的・感情的な営み”改善”させるためといって子どもを薬漬けにする。金融のフラジリスタは、人々にリスク・モデルなるものを使わせ、銀行システムをぶっ壊す (そしてまた同じモデルを使う)。軍事のフラジリスタは、複雑な体制をかき乱す。未来予測のフラジリスタは、人々にリスクを冒させる。ほかにも挙げればキリがない。
*2 ハイエクは自身の有機的な価格づけという考えを、リスクや脆さの概念に取り入れたわけではない。ハイエクにとって、官僚は非効率的だというだけで、フラジリスタではなかった。本書では、まず脆さと反脆さを導入し、副次的な議論として有機的な価格形成の話をする。
事実、政治的な議論には「反脆さ」というコンセプトが欠けている。政治家たちがスピーチ、目標、約束で掲げるのは、反脆さではなく、「耐久性」や「堅牢性」とかいう弱気な考え方だ。そして、その過程で成長や進化のメカニズムを邪魔してしまう。私たちがこうして現世に生きているのは、「耐久性」とかいう軟弱な概念のおかげではない。もっといえば、議員さんのおかげでもない。一部の人たちが貪欲にリスクを冒し、失敗を繰り返してきたおかげなのだ。私たちはそういう人々をもっと応援し、守り、尊敬するべきだ。
シンプルなほど洗練されているケース
人々の考えとは裏腹に、複雑系には、複雑なシステムも規制も政策も不要だ。「シンプルであればあるほどよい」のだ。複雑化すると、想定外の影響が連鎖的に膨らんでいく。不透明性のせいで、干渉は予測不能な影響をもたらす。“予測不能”な結果について詫びたあと、二次的な影響を正すために別の干渉をする。すると、”予測不能”な反応は枝分かれ的に急増する。しかも、先に進むたびに影響は深刻になっていく。
なのに、現代の生活でシンプルを実践するのは難しい。自分の職業を正当化するために、何でもかんでも専門化しようとする連中の考え方に反するからだ。
少ないほど豊かだ。そして、ふつうは少ないほど効果的だ。そこで、私は本書でほんのいくつかのコツ、指針、禁止事項を提案したいと思う。理解不能な世界をどう生きるべきか。いやむしろ、絶対に理解できない物事に臆することなく対処するにはどうすればよいか。もっと原理的にいえば、そういう物事にどう対処すべきか。さらにいえば、自分たちの無知に面と向かいあい、人間であることを恥じることなく、人として積極的に堂々と生
きるにはどうすればよいのかを提案したい。だが、それにはちょっとした構造的な変化が
必要かもしれない。
私が提案するのは、人工的なシステムを修正し、シンプルで自然なシステムに舵取りを任せるためのロード・マップだ。
しかし、シンプルを実現するのはシンプルじゃない。スティーブ・ジョブズは「思考を整理し、シンプルにするには努力がいる」と述べている。アラブには、明快な文章についてこんな表現がある。「理解するのに技術はいらなくても、それを書くには名人の技がいる」
ヒューリスティックとは、物事をシンプルで実践しやすくする単純化された経験則だ。
しかし、ヒューリスティックのいちばんの利点は、それが完璧ではなく、単なる応急策だとわかっている点だ。だから、その威力にだまされることはあんまりない。危険なのは、そのことを忘れたときだ。
Ⅳ.本書
反脆さという概念に行き着くまでの旅は、いってみれば非線形的だった。
ある日、私は突然、それまで厳密な定義のなかった「脆さ」という概念を、「変動性を好まないもの」として表現できることに気づいた。そして、「変動性を好まないもの」はランダム性、不確実性、無秩序、間違い、ストレスなどを好まない。脆いものを思い浮かべてほしい。たとえば、居間にあるガラスの写真立て、テレビ、食器棚の磁器など、何でもいい。「脆い」と形容されるものは、安定的で、静かで、秩序的で、予測可能な環境に置いておきたいと思うものばかりだ。脆いものというのは、地震の発生やおてんばな姪の訪問で利益を得ることはまずない。さらに、変動性を好まないものはみんな、ストレス、害、渾沌、事件、無秩序、予測不能、な影響、不確実性、そしていちばん大事なことに、時の経過を嫌うということだ。
そして、反脆さは、この脆さの明確な定義からいわば自然と生まれる。反脆さは変動性などを好む。時の経過も歓迎だ。それから、非線形性と強力で有益な関係を持つ。非線形的な反応を示すものはみんな、一定のランダム性の根源に対して、脆いか反脆いかのどちらかなのだ。
何より不思議なのは、脆いものはすべて変動性を嫌う(およびその逆)という当たり前の性質が、科学や哲学の議論からすっぽりと抜け落ちてしまっていることだ。すっぽりとだ。私は成人してからの3年間、「変動性に対する物事の感応度を調べる」という、摩訶不思議な仕事を生業として生きてきた。おかしな生業だというのはわかっている。これについてはあとで説明する。この仕事で、私は「変動性を好む」ものと「変動性を嫌う」ものを見極めることに神経をすり減らしてきた。だから、私がしなくちゃならないのは、この考えを金融の分野から実世界へと一般化することだけだった。政治科学、医療、夕食の計画といった色々な分野において、不確実性のもとで意思決定するにはどうすればよいか を考えるわけだ。
*3 「変動性(ボラティリティ)を嫌う」を専門用語でいえば、「ショート・ベガ」、または「ショート・ガンマ」となる。これは「変動性が上昇すると損害をこうむる」という意味。その逆で利益になる場合は、「ロング・ベガ」、または「ロング・ガンマ」という。本書の残りの部分では、「ショート」、または「ロング」と言ったときには、それぞれ負および正のエクスポージャーを指す。言っておくが、私は変動性を予測できるなんて思ったことはいちどもない。私は変動性に対する物事の反応の仕方だけに着目してきたのだ。
そして、変動性を相手にするこの摩訶不思議な職業には、2種類の人種がいる。ひとつ目は、未来の事象を研究して本や論文を書く学者、レポート・ライター、評論家だ。ふたつ目は、未来の事象を研究するのではなく、変動性に対する物事の反応の仕方を理解しようとする実践家だ(だが、実践家は実践するのに手一杯で、本、記事、論文、スピーチ、数、理論を作っているヒマなんてないので、崇高なる学者様方からは尊敬されない)。ふたつの違いは重要だ。先ほども話したとおり、巨大なブラック・スワンのような有害な事象を予測しようとするよりも、何かが変動性で害をこうむるかどうか、つまり脆いかどうかを理解するほうが、ずっと簡単だ。ところが、この点を自然に会得しているのは、たいてい実践家(物 事を実行する人)だけなのだ。
(むしろ幸せな)無秩序一家
専門的なコメントをひとつ。さっきから繰り返しているように、脆さや反脆さとは、変動性に関連する何かに対するエクスポージャー(さらされている状態)から、利得や損失を受ける可能性があることを意味する。何かとは? 簡単にいえば、無秩序の親戚に当たるものだ。
無秩序の親戚(仲間)とは、次のとおり。①不確実性、②変化、③不十分で不完全な知識、④偶然、⑤渾沌、⑥変動性、⑦無秩序、⑧エントロピー、⑨時、⑩未知のもの、⑪ランダム性、⑫混乱、⑬ストレス、⑭間違い、⑮結果のばらつき、⑯似非知識。
うまいことに、不確実性、無秩序、未知のものは、その効果という点ではまったく同等なのだ。どれも、反脆いシステムにとっては (ある程度までは)利益になり、脆いシステムにとってはたいてい有害になる。でも、これらは大学の別々の建物で教えられているし、人生で本当のリスクなんて冒した経験もない(もっといえば本当の人生なんて生きたこともない)似非哲学者は、「これらは明らかに別物だ」なんて平気で言ったりする。
項目⑨に時が入っているのはどうして? 時は機能的には変動性と似ている。時がたてばたつほど、色々な事象が起こり、無秩序は大きくなる。あなたの受ける事が限られていて、あなたが小さな間違いに対して反脆いとしよう。すると、時はやがて、あなたにとって利益になるタイプの間違い、いわば逆間違いをもたらしてくれる。これこそ、あなたの祖母が「経験」と呼んでいるものだ。一方、脆いものは時とともに壊れゆく。
唯一無二の本
このアイデアこそ、本書が私の主要な研究であるゆえんだ。雛形になるたったひとつのアイデアから始めて、私は考察のたびに一歩ずつ進化させてきた。だが、その最後の一歩、つまり本書は、大ジャンプと言ったほうが私の感覚に近い。私は今、”実践的な私”、つまり私の実践家魂と再びひとつになっている。というのも本書は、実践家や「変動性の専門家」としての私の歴史全体と、ランダム性や不確実性に関する私の知的・哲学的な興味を、ひとつに融合させたものだからだ。このふたつは、今の今まで別々の道をたどっていたのだ。
私の著作は、具体的なトピックについて書いた独立型のエッセイではない。始まりと終わりがあるわけでもないし、賞味期限があるわけでもない。むしろ、核となるアイデアから枝分かれした、独立した章の集まりである。
著作全体のテーマは、不確実性、ランダム性、確率、無秩序だ。人間には理解できない世界、目に見えない要素や性質に満ちた世界、ランダムで複雑な世界をどう生きればよいのか。ひと言でいえば、不透明性のもとでの意思決定だ。私の著作群は『Incerto』と呼ばれ、(今のところ)三部作+哲学的・専門的な補遺からなっている。書くときの決まり事というのがあって、ある本(たとえば本書)の任意の章と、別の本(たとえば『まぐれ』)の任意の章との距離感を、一冊の長い本の章同士の距離感と同じにするようにしている。この決まり事のおかげで、混乱することなく、科学、哲学、ビジネス、心理学、文学、自伝を自由自在に横断できるわけだ。
訳注2 『Incerto』はラテン語で「不確実な」という意味。今のところ、『まぐれ』『ブラック・スワン』(『強さと脆さ』も含む)、本書の三部作と、『ブラック・スワンの箴言』『Metaprobability, Convexity, & Heuristics: Technical Companion for The INCERTO(メタ確率、凸性、ヒューリスティック――Incertoの技術的手引書)』の五つで構成されている。最後の手引書はウェブで無料公開されている300ページ超の論文集で、数式を使った専門的解説がなされている。
そこで、この本と『ブラック・スワン』の関係について言っておくと、次のようになる。時系列には反するが(本書は『ブラック・スワン』のアイデアから、自然で規範的な結論を導き出したものだ)、本書のほうが主要書である。『ブラック・スワン』はいわば本書の補助的な作品であり、理論的な裏づけを提供している。本書のミニ付録のようなものといってもいいかもしれない。なぜか? 『ブラック・スワン』(とその前作の『まぐれ』)は、危機的な状況をみんなに訴えるために書いたもので、そこにかなりのウェイトを置いていた。でも本書は、次のふたつを前提として書きはじめている。
(a)ブラック・スワンが社会や歴史を支配していること(そして、後付けの合理化により、人間がブラック・スワンを理解できると思いこんでいること)。
(b)したがって、特に非線形性が激しいところでは、何が起こるかなんてわかったものじゃないこと。
この前提のおかげで、すぐに本題に入ることができるわけだ。
勇気なくして信念なし
実践家の精神に従って、私は本書でこんなルールも設けている。自分の作った飯は自分で食うということだ。
私が職業人生を通じて書いてきたどの一文を取っても言えることは、自分で経験したことしか書いてこなかったということだ。私が他人に冒すよう(避けるよう)提案したリスクは、私自身も冒して(避けて)きた。間違えたときに真っ先に傷つくのは私だ。『ブラック・スワン』で銀行システムの脆弱性について警告したとき、私はシステムの崩壊にちゃんと賭けていた(私の忠告がまだ注目されていなかったころでさえ)。そうでなければ、そんなことを書くのは倫理違反だ。この個人的なルールは、医療、技術的イノベーション、人生のどうってことない物事など、どんな分野にも当てはまる。
目次 – 反脆弱性[下]――不確実な世界を生き延びる唯一の考え方
目次
反脆弱性[下]
目次
章のまとめとマップ(再掲)

第17章 デブのトニー、ソクラテスと相対す
対話篇『エウチュプロン』
デプのトニー対ソクラテス
定義的な知識の優位に反旗を翻したニーチェ
理解不能なものを不合理なものと勘違いする
伝統への敬意――ウィトゲンシュタイン、ハイエク、レヴィ=ストロース
カモとそうでないヤツの違い
確率ではなく脆さに基づく意思決定を
事象とエクスポージャーの同一化
第4部の結論
この先はどうなる?
第5部 あれも非線形、これも非線形
「屋根裏」の重要性について
第18章 1個の大石と1000個の小石の違いについて
脆さを見分ける単純な法則
脆いものはなぜ非線形的なのか?
笑顔としかめ面の使い分け
なぜ凹なものはブラック・スワン的な事象に弱いのか?
ニューヨークの交通、インフレーション、「凸効果」
誰かニューヨーク市の担当者を呼んでくれ!
多は異なり―スケーリングの性質について
“バランスのよい食事”の再定義
歩くな、走れ!
小さいものは醜いかもしれないが、間違いなく脆くはない
「スクイーズ」に陥る仕組み
ケルビエルとミニケルビエル
映画館を逃げ出すには
プロジェクトと予測
どうして飛行機は早めに到着しないか
戦争、赤字、赤字
“効率的”が効率的でないとき
地球に対する汚染と害
「宮」の非線形性
第18章の結論
第19章 賢者の石とその逆
破綻するヤツを見分ける方法
正と負のモデル誤差という考え方
おばあちゃんの亡くし方
お待たせしました、賢者の石
金を泥に変える方法 賢者の石の逆
第6部 否定の道
ダビデでない部分を削り取る
ペテン師はどこにいる?
引き算的な知識
バーベル戦略、再び
少ないほど豊か、というヒューリスティック
第20章 時と脆さ
「最新性愛症」という病理
シモニデスからイェンゼンへ
引き算を学ペ――未来を語るうえでの最大の間違い
技術の「最高の形」と自浄作用
逆向きに歳を取る――リンディ効果
心理的バイアスをいくつか
最新性愛症とトレッドミル効果
建築と「不可逆な最新性愛症」
壁一面の窓――フラクタルへの回帰
「メートル法化」の弊害
ジャーナリズム化、スポーツ化する科学の脆さ
壊れるべきもの
(引き算的な)予言者、古今東西
エンペドクレスの犬
理に適わないもののとらえ方
第21章 医学、凸性、不透明性
「何を証拠とみなすべきか」に関する法則
救急治療室で議論するには
医原病の第一原理―経験主義
医原病の第二原理―反応の非線形性
医療におけるイェンゼンの不等式
埋め隠された証拠の数々
終わりなき七面鳥問題の歴史
自然のロジックの不透明性
有罪か無罪か――”証拠”の名のもとに理論に背く
生物学なんて知りません――現象学
古代の人々のほうが医師に辛辣だった
人口の半数を薬漬けにするには
医学の「数学的厳密性」
まとめ、そして次へ
第22章 ほどほどに長生きする――「引き算」の力
寿命と凸性
引き算こそが寿命を延ばす
「お金」に潜む医原病
宗教対浅はかな干渉主義
水曜日だ、ヴィーガンになろう
凸効果とランダムな栄養摂取
自分を食べる方法――断食とオートファジー
「歩き」の剥奪は何をもたらすか
不死を求めるべきなのは
第7部 脆さと反脆さの倫理
第23章 身銭を切る――他人の犠牲と引き換えに得る反脆さとオプション性
身銭を切る英雄とエージェンシー問題
今こそハンムラビ法典を
アンフェア化する世界――おしゃべり屋の無料オプション
後言者と無自覚なカモたち
スティグリッツ症候群
頻度の問題、あるいは議論に負ける方法
間違った理由で正しい決断を
古代の人々のスティグリッツ症候群への対処法
自分の船を燃やす――背水の陣
詩が死をもたらすケース
絶縁の問題
シャンパン社会主義にキャピア左翼
魂を捧げてこそ
オプション、反脆さ、社会的公正
ロバート・ルービンの無料オプション(反脆さの移転)
どちらのアダム・スミスさん?
(大)企業の反脆さと倫理
職人、マーケティング、最割安
アラビアのロレンスか、マイヤー・ランスキーか
まとめ、そして次へ
第24章 倫理を職業に合わせる――自由と自立
倫理が先か、職業が先か
自立なき宮など
真の「自由人」とは
合法的であれば倫理的なのか?
オプション性としての決疑論
ビッグ・データと研究者のオプション
集団の暴政
第25章 結論
エピローグ 生まれ変わりに生まれ変わりを重ねて
謝辞
参考文献
追記、補足、関連図書
付録Ⅱ (非常に専門的)
付録Ⅰ
用語集
反脆弱性 上 目次
プロローグ
第1部 反脆さとは
第1章 ダモクレスとヒュドラーの間で
第2章 過剰補償と過剰反応はどこにでもある
第3章 ネコと洗濯機
第4章 私が死ねば、誰かが強くなる
第2部 現代性と、反脆さの否定
第5章 青空市とオフィス・ビル
第6章 ランダム性は(ちょっとなら)すばらしい!
第7章 浅はかな干渉医原病
第8章 予測は現代性の生みの子――ブラック・スワンの世界へ
第3部 予測無用の世界観
第9章 デブのトニーとフラジリスタたち
第10章 セネカの処世術
第11章 ロック・スターと10パーセント浮気する――バーベル戦略
第4部 オプション性、技術、そして反脆さの知性
第12章 タレスの甘いぶどう――オプション性
第13章 烏に飛び方を教える――ソビエト=ハーバード流の錯覚
第14章 ふたつが”同じもの”じゃないとき
第15章 敗者が綴る歴史――試行錯誤の汚名をすすぐ
第16章 無秩序の教訓
章のまとめとマップ (再掲)
第1部 反脆さとは
第1章 「反脆さ」という言葉が教室で見落とされていたことを説明する。脆弱・頑健・反脆弱とダモクレス・フェラー。領域依存性。
第2章 過剰補償が起こる場所とは。経済学以外では、執着的な愛情ほど反脆いものはない。
第3章 有機体と人工物の速い。人生から変動性を吸い取ろうとする観光客化。
第4章 多くの場合、全体の反脆さは部分の脆さに依存する。人生に死が必要なワケ。失敗が全体にもたらす利益。リスク・テイカーが必要な理由。この点を見述している現代性について二言三言。起業家とリスク・テイカーへの敬意。
第2部 現代性と、反脆さの否定
プロクルステスのベッド
第5章 ランダム性の2種類のカテゴリーを、その性質から読み解く。スイスはなぜトップダウンじゃないのか。月並みの国と果ての国の違い。都市国家、ボトムアップ型の政治システム、地方自治体のノイズが持つ安定化作用のメリット。
第6章 ランダム性を好むシステム。物理学内外の焼きなまし手法。有機体や複雑系(政治、経済など)を過度に安定化させることの影響について説明する。知識偏重主義の功罪。アメリカの外交政策と似非安定化。
第7章 現代性の産物の中でいちばん軽視されている、浅はかな干渉と医原病について。ノイズとシグナル。ノイズによる過剰な干渉。
第8章 予測は現代性の生みの子。
第3部 予測無用の世界観
第9章 脆さを嗅ぎ取る名人、デブのトニー。ネロ。長い昼食。フラジリスタから金を搾り取る。
第10章 自分の作った薬を飲もうとしないトリファット教授。反脆いものは必ずダウンサイドよりもアップサイドのほうが多いので、変動性、間違い、ストレスで得をする。これを根本的な非対称性という。これをセネカとストア哲学にたとえて説明する。
第11章 組み合わせていいものといけないもの。人生におけるバーベル戦略。脆さを反脆さへと変換するもの。
第4部 オプション性、技術、そして反脆さの知性
(秩序好きの教育と無秩序好きのイノベーションの対立関係)
第12章 タレス対アリストテレス。状況を理解していなくてもへっちゃらなオプション性という概念。同一化のせいでオプション性が誤解されている理由。オプション性を見落としていたアリストテレス。私生活の中のオプション性。いじくり回しが計画よりも効果を発揮する条件。分別ある遊び人。
第13章 成長の裏にある非対称的なペイオフについて。ソビエト=ハーバード流の錯覚、別名「鳥に飛び方を教える」現象。随伴現象。
第14章 グリーン材の誤認。エピステーメー(知識)と試行錯誤の対立関係と、その歴史を通じた役割。知識は富を生むのか?そうだとすれば、どんな知識が? 知識と富が同じものじゃないとき。
第15章 技術史の書き直し。科学の世界で、歴史は敗者によってどう書き直されるのか。私がトレーダーの世界で目撃した歴史の書き直し。その一般化。生物学の知識は医療の邪魔になるのか? 隠蔽されている運の役割。よい起業家とは何か?
第16章 教育ママへの対処法。遊び人の教育。
第17章 デブのトニー、ソクラテスと相対す。私たちはどうして、説明不能なことを実行できないのか? そして自分の行動を説明せずにはいられないのか? ディオニュソス的。「カモか否か」で物事を考える。
第5部 あれも非線形、これも非線形
第18章 凸性、凹性、凸効果。規模そのものが脆さを生む理由。
第19章 賢者の石。凸性についてさらに詳しく。ファニー・メイはどうして破綻した? 非線形性。脆さと反脆さを見分けるヒューリスティック。凸バイアス、イェンゼンの不等式と、それらが無知に及ぼす影響。
第6部 否定の道
第20章 最新性愛症。「否定の道」で未来を観る。リンディ効果(新しいものより古いもののほうが、その年齢に比例して長く生き残る)。エンペドクレスの煉瓦。非合理的なもののほうが、一見すると合理的なものより勝るワケ。
第21章 医学と非対称性。医療問題における意思決定の法則。重病患者のペイオフが凸で、ぴんぴんした人のエクスポージャーが凹である理由。
第22章 引き算的な医療。環境内のランダム性の種類と個人との相性について。私が不死になんてなりたくないワケ。
第7部 脆さと反脆さの倫理
第23章 脆さを移転させるエージェンシー問題。身銭を切る。ドクサ的コミットメント。または魂を捧げる。ロバート・ルービン問題、ジョセフ・スティグリッツ問題、アラン・ブラインダー問題。三つともエージェンシー問題であり、ひとつはいいとこ取りの問題。
第24章 倫理のひっくり返し。個人個人に分別があっても、集団になると間違えることもある。人はどうやって意見にとらわれていくのか。そこから解放するには。
第25章 結論。
エピローグ ネロがレヴァントを訪れ、アドーニスの儀式を見学していると……。
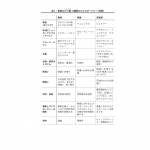




目次 – 身銭を切れ――「リスクを生きる」人だけが知っている人生の本質
目次
ふたりの勇敢な男性
ギリシア人たちのなかのローマ人
ロン・ポール
ギリシア・フェニキアの聖人
ラルフ・ネーダー
に捧ぐ

身銭を切れ
目次
第1部 「身銭を切る」とは何か
身銭を切ることの意外な側面
プロローグその1 アンタイオス、殺やられる
アンタイオスなきリピア
他人の命で遊ぶ――Ludis De Alieno Corio
人民の庇護者でなければ、貴族たりえない
ロバート・ルービン取引――隠れた非対称性とそのリスク
システムは排除によって学ぶ
その2 対称性の簡単なおさらい
I. ハンムラビからカントへ
なぜかパリにあるハンムラビ法典
白銀は黄金に勝る
普遍主義なんて忘れちゃえ
Ⅱ. カントからデブのトニーへ
ペテン師か、バカ者か、その両方か
因果関係の不透明性と頭示選好
身銭を切る必要のある人ない人
Ⅲ. 近代主義
専門化の痛すぎる弊害
シンプルがいちばん
身銭を切らないと私は愚鈍になる
規制か法制度か
Ⅳ. 魂を捧げる
職人
起業家という言葉に要注意
傲慢も方便
楽しみとしての市民権
英雄に本の虫はいない
魂を捧げる人々と適度な保護主義
身を切った裁判官
その3 「インケルトー』の肋骨
道
研ぎ澄まされた探知器
書評家
本書の構成
第1部の付録 人生や物事における非対称性
第2部 エージェンシー問題入門編
第1章 自分で捕まえた魚は自分で食べよ――不確実性に関する平等
お客は毎日生まれている
ロードス島の穀物の値段
不確実性に関する平等
ラブ・サフラとスイス人
会員と非会員――個から一般へのスケール変換の難しさ
私でもあなたでもなく、私たちのもの――Non Mihi Non Tibi, Sed Nobis
あなたは右でも左でもなく”斜め”寄り?
(文字どおり)同じ船の仲間
自分の持ち株を勧める
診察室に寄り道
次のテーマ
第3部 例のこの上ない非対称性
第2章 もっとも不寛容な者が勝つ――頑固な少数派の支配
あらゆる非対称性の生みの親「少数決原理」
ピーナッツ・アレルギー持ちの犯罪者――ラペリング
オーガニック食品と遺伝子組み換え食品を普及させるための共通の戦略
くりこみ群
“拒否権”効果
共通語
遺伝子と言語の違い
宗教の一方通行性と、ふたつの非対称的な規則
再び、分権化の話
道徳は少数派によって作られる
少数決原理の安定性に関する確率的議論
ポパーとゲーデルのパラドックス
市場と科学は聞く耳を持たない
1頭のみ、されど獅子―Unus Sed Leo
まとめと次のテーマ
第3部の付録 集団にまつわるいくつかの意外な事実
知能ゼロの市場
第4部 犬に紛れたオオカミ
第3章 合法的に他人を支配するには
フリーランス修道士が教えてくれること
パイロットを飼い慣らすには
企業マンから企業人へ
コースの企業理論
複雑な現代世界
奴隷所有の面白い形
自由はタダじゃない
犬に紛れたオオカミ
損失回避の心理
コンスタンティノポリスの復活を待ちわびて
官僚王国を揺るがすな
次のテーマ
第4章 人に身銭を切らせる
住宅ローンと2匹のネコ
隠れた弱みを見つける
自爆テロ犯に身銭を切らせるには
次のテーマ
第5部 生きるとはある種のリスクを冒すこと
第5章 シミュレーション装置のなかの人生
イエスはリスク・テイカー
パスカルの賭け
マトリックスの世界
あのドナルド・トランプが勝ったのは欠点のおかげ
次のテーマ
第6章 知的バカ
ココナッツはどこにある?
科学と科学主義
知的俗物
言語を話す前に文法を学ぶ
結論
追記
第7章 身銭を切ることと格差の関係
2種類の格差
静的な格差と動的な格差
ピケティとマンダリン階級の反乱
靴屋は靴屋を妬む
格差、富、縦の交流
共感と同類性
データ、ああ似非データ
公務員の倫理
次のテーマ
第8章 リンディという名の専門家
反脆弱性とリンディ効果
“真”の専門家は誰?
リンディのリンディ
審判は必要なのか?
女王との紅茶
学術機関の罠
自己の利益に反して
もういちど、魂を捧げる
科学は耐リンディである
経験的か理論的か?
おばあちゃんと研究者の対決
おばあちゃんの知恵のおさらい
第6部 エージェンシー問題 実践編
第9章 外科医は外科医っぽくないほうがいい
人は見た目が大事
グリーン材の誤謬
最高に着飾ったビジネス・プラン
仮装する主教
ゴルディアスの結び目
人生の過剰な知性化
干渉のもうひとつの側面
金と稲
報酬制度が生み出す歪み
贅沢品としての教育
いんちき探知ヒューリスティック
本物のジムはジムっぽくない
次のテーマ
第10章 毒を盛られるのはいつだって金持ち――他者の選好について
金持ちの選好は操られている
毒は金杯で飲まれる
巨大な葬儀場
会話の成立条件
進歩の非線形性
次のテーマ
第11章 不言実行
断りづらい提案
暗殺教団
マーケティングとしての暗殺
民主主義としての暗殺
カメラは身銭を切らせる道具
第12章 事実は正しいが、ニュースはフェイク
自分自身に反論する方法
情報は支配に抗う
反論の倫理学
次のテーマ
第3章 善の商品化
「善」の不正利用者ソンタグ
公と私
善の”売人”
そうなのか、そう見えるのか
聖職売買
善とは他者や集団に対して行うもの
不人気な善
リスクを負え
第14章 血もインクもない平和
平和はトップダウンでは生まれない
火星対土星
ライオンはどこへ消えた?
救急治療室から見た歴史
次のテーマ
第7部 宗教、信仰、そして身銭を切る
第15章 宗教を語るヤツは宗教をわかっていない
宗教の意味は人と時代によって異なりまくる
信念対信念
リバタリアニズムと教会なき宗教
次のテーマ
第16章 身銭を切らずして信仰なし
神々は安上がりなシグナリングがお嫌い
証
第17章 ローマ教皇は無神論者か?
ローマ教皇と無神論者の見分けはつくか
言葉では信心深い人たち
次のテーマ
第8部 リスクと合理性
第8章 合理性について合理的に考える
目の錯覚
エルゴード性が第一
サイモンからギーゲレンツァーへ
顕示選好
宗教は何のためにある?
“おしゃべり”と安っぽい”おしゃべり”
リンディの言い分は?
お飾りはお飾りとはかぎらない
第19章 リスク・テイクのロジック
エルゴード性
繰り返しリスクに身をさらすことが余命を縮める
*あなた”って誰のこと?
勇気と思慮深さは対極ではない
もういちど、合理性の話をしよう
ある程度のリスクを愛そう
浅はかな経験主義
まとめ
エピローグ リンディが教えてくれたこと
謝辞
参考文献
注解
専門的な付録
用語集
第1部 「身銭を切るとは」
本書は、かたや独立した本でありながら、かたや『インケルトー(Incerto)』と呼ばれる私の著作シリーズの一部でもある。『インケルトー』は、不確実性のもとで生き、食べ、眠り、論じ、戦い、睦み、働き、遊び、決断する方法や、ランダム性の問題について、(a)実践的な議論、(b)哲学的な物語、(c)科学的・分析的な解説を組み合わせたものだ。幅広い方々に読んでいただけるよう書いたつもりだが、だまされてはいけない。『インケルトー』は、あくまでもエッセイであって、どこか別の場所で行われた退屈な研究を大衆化したものではない(ただし、『インケルトー』の専門的な補遺は除く)。
本書では、次の4つの話題を同時に論じている。
(a)不確実性と、実践的な知識や科学的な知識の信頼性(両者が違うものだと仮定して)。
もう少しぶしつけな言い方をするなら、たわごとの見分け方。
(b)公平、公正、責任、相互性といった人間的な物事における対称性。
(c)商取引における情報共有。
(d)複雑系や実世界における合理性。
この4つが切り離せないものであるということは、身銭を切っている人間にとっては明々白々な事実だ。
身銭を切ることは、公平性、商業的な効率性、リスク管理にとって必要なだけではない。この世界を理解するうえで欠かせない条件なのだ。
本書の第1のテーマ (a)は、たわごとを見抜き、ふるい分けることだ。要するに、理論と実践、うわべだけの知識と本物の知識、(悪い意味での)学問の世界と実世界との違いを理解するということだ。ヨギ・ベラ流にいえばこうなるだろう。学問の世界では、学問の世界と実世界の違いはないが、実世界ではある。
第2のテーマ(b)は、人生における対称性や相互性の歪みだ。報酬が期待できるなら、それなりのリスクを引き受けるのが道理というものだ。ましてや、自分の失敗の代償をほかの誰かに払わせるなんてとんでもない。ほかの人にリスクを背負わせ、相手が危害をこうむったのなら、あなた自身がその代償の一部を払うのが仁義というものだ。「自分がしてほしいことを他者にもせよ」という原則に従うなら、あなた自身も、起こった出来事に対する責任を公平公正に負担するべきなのだ。
つまり、あなたが何か意見を述べ、誰かがその意見に従ったのなら、あなた自身もその結果に対してリスクを負う道義的な義務がある。経済的な見解を述べるなら、
「あなたの”考え”ではなく、ポートフォリオの中味を教えろ。」
*1 倫理、道徳的義務、能力が実生活で容易に切り離せないということを理解するには、次の例を考えるといい。あなたが責任ある立場の人、たとえば経理担当者に、「信頼しているよ」と伝えたとしよう。その意味は、(1)相手の倫理観を信頼している(パナマに金を流したりはしない、など)、(2)相手の経理の腕を信頼している、(3)その両方、のどれだろう? 実世界では、倫理と知識、倫理と能力をふたつに切り離すのは難しいというのが、本書の全体的な主旨だ。
訳注1 incertoはラテン語で「不確実性」という意味。
第3のテーマ(c)は、他者と共有すべき情報の量についてだ。中古車のセールスマンは、客が大枚をはたいて購入しようとしている車について、どんな情報を伝える(または伝えない)べきなのか?
第4のテーマ(d)は、合理性と時の試練だ。実世界における合理性とは、『ザ・ニューヨーカー』の記者や、軽薄な一次モデルを用いるどこぞの心理学者から見た合理性なんかではなくて、ある人自身の生存と関連するずっと奥深い統計的な合理性である。
ここで定義する(そして本書全体で使われている)「身銭を切る」という言葉の意味を、単なる金銭的なインセンティブの問題と誤解しないでほしい。金融の世界でよくいう利益の分配の話ではなくて、むしろ対称性の問題だ。いわば損害の一部を背負い、何かがうまくいかなかった場合に相応のペナルティを支払うという話だ。
この「身銭を切る」という概念こそが、インセンティブ、中古車の購入、倫理、契約理論、学習(実生活と学問の世界)、カントの定言命法、地方分権、リスクの科学、知識人と現実の接点、官僚の説明責任、確率論的な社会的公正、オプション理論、まっとうな行動、たわごとの押し売り、神学……等々の概念をひとつに結びつけるのだ。
身銭を切ることの意外な側面
本書にもう少し正確なタイトルをつけるとすれば、『身銭を切ることの意外な側面――隠れた非対称性とその影響』くらいになるだろう(かなりぎこちないけれど)。理由は単純。私自身、当たり前のことばかり書いてある本なんて、さらさら読む気にもなれないからだ。驚きがほしい。だから、「自分がしてほしいことを他者にもせよ」という相互性の原則にのっとり、大学の講義のような意外性のないあくび連発の旅ではなく、私自身が体験してみたいと思うような冒険へと、読者のみなさんをご案内したいと思う。
そういうわけで、本書は次のような構成になっている。第2部の終わりあたりまで読めば、身銭を切ること(つまり対称性)の重要性、一般性、普遍性があらかた理解できると思う。しかし、重要な物事が重要たる理由について、必要以上にくどくどと説明するのはよくない。原理原則というものは、正当化しようとすればするほど野暮になっていく。
このワクワクするような旅路では、第2のステップにも目を向ける。つまり、身銭を切るという概念が持つ意外な意味(つまり、パッと見ではわからないような隠れた非対称性)と、その予想外の影響である。そのなかには、私たちにとってかなり不都合な真実もあるが、多くのものは思いがけず役立つ。身銭を切るという概念の仕組みを理解すれば、複雑な現実の根底にある難問が解けるようになる。
たとえば、次のような問題だ。
なぜもっとも不寛容な少数派が世界を支配し、自分たちの選好を私たちに押しつけるのか? なぜ普遍主義は人々を助けるつもりがかえって害を及ぼすのか? なぜ現代には古代ローマ時代よりも奴隷が多いのか? なぜ外科医は外科医っぽく見えないほうがいいのか?なぜキリスト教神学は、神的な側面とは必然的に異なるイエス・キリストの人間的な側面を主張しつづけたのか? なぜ歴史家は平和ではなく戦争ばかりを記し、私たちを惑わせるのか? なぜ(リスクを伴わない)安上がりなシグナリングは、経済でも宗教でも同じように失敗するのか? なぜ一点の曇りもない経歴を持つ官僚よりも、明らかに性格に問題のある政治家候補のほうが、本物らしく見えるのか? なぜ私たちはハンニバルを崇拝するのか? なぜプロ経営者がお節介を焼きはじめたとたん、会社はつぶれるのか? なぜ異教信仰のほうが集団間で対称的なのか? 外交はどう行うべきか? なぜ非常に分権的な方法で運営されていない(現代の用語を使えば、ウーバー化されていない)かぎり、組織的な慈善団体に寄付すべきではないのか?なぜ遺伝子と言語の広まり方は異なるのか? なぜコミュニティの規模が重要なのか?(たとえば、なぜ漁師のコミュニティは、集団の人数、つまり規模が1段階上がったとたん、協力的なものから敵対的なものへと様変わりするのか?) なぜ行動経済学は個人の行動研究といっさい関係がないのか?そして、なぜ市場は市場参加者の個々のバイアスとほとんど関係がないのか? なぜ「生存」こそが合理性の唯一の尺度だといえるのか?リスク分担の基本的なロジックとは何か?
しかし、筆者にとって、身銭を切るという行為の本質は、公正、名誉、犠牲といった、人間の実存にかかわる物事にある。
身銭を切るという原則を取り入れれば、文明化に伴ってどんどん広がっていく次の乖離の影響を抑えられる。それは、行動と口からでまかせ(くっちゃべり)、結果と意図、実践と理論、名誉と名声、専門知識とペテン、具体的と抽象的、倫理的と合法的、中身とうわべ、商人と官僚、起業家と最高経営責任者、強さと強がり、愛と玉の輿、コヴェントリーとブリュッセル、オマハとワシントンDC、人間と経済学者、作家と編集者、学究と学問、民主制と統治、科学と科学主義、政治と政治家、愛と金、精神と字義、大カトーとバラク・オバマ、品質と宣伝、コミットメントとシグナリング、そして何より、集団と個人だ。
まずは、身銭を切るという概念がさまざまなカテゴリーに応用できるものだという事実を理解いただくため、ふたつのエピソードを通じて、先ほど挙げたいくつかの項目どうしを結びつけてみよう。
プロローグその1
アンタイオス、 殺やられる
母ちゃんから離れるな。
武将はいつの世にもいる。
ロバート・ルービンと彼の取引。
システムは自動車事故がお好き。
アンタイオスは、ギリシア神話に登場する巨人(正確には半巨人)であり、地母神ガイアと海神ポセイドンの文字どおりの息子だった。彼には奇妙な日課があり、(古代ギリシア時代の)リビアで通りがかりの者に格闘を挑んでは、地面に押し倒し、殺していた。この薄気味悪い日課は、彼なりの親孝行だったようだ。アンタイオスは殺した人々の頭蓋骨を材料にして、父ポセイドンのために神殿を建てようとしていた。
アンタイオスは無敵とされていたが、そこにはあるカラクリが潜んでいた。彼は母なる大地に足を着けることで、力を得ていたのだ。地から足が離れたとたん、アンタイオスはみるみる力を失っていった。一説によると、ヘラクレスは2の功業の一環として、アンタイオスを倒すよう命じられた。ヘラクレスはアンタイオスを地面から持ち上げると、母なる大地に足が着いていないうちに彼の息の根を止めた。
このひとつ目のエピソードが象徴しているのは、「知識は地に足の着いたものでなければならない」ということだ。いや、それどころか、どんなものも地に足が着いていなければならない。では、どうすれば実世界との接触を保っていられるのか? ずばり、身銭を切ることだ。つまり、実世界に対してリスクを背負い、よい結果と悪い結果のどちらに対しても、その報いを受けるという意味である。あなたが身に負った切り傷は、学習や発見の助けになる。いうなれば、有機的なシグナリングのメカニズムであり、ギリシア語でいうpathemata mathemataだ(「痛みは学びを助く」。幼い子を持つ母親ならよく知っているだろう)。『反脆弱性』で、大学が~発明したと考えられているものの大半は、実際にはいじくり回しによって発見され、そのあとで何らかの形式化を通じて正当化されたのだと説明した。私たちがいじくり回し、試行錯誤、実体験、時の営みによって得る知識、つまり地に足を着けることで得る知識は、純粋な推論を通じて得られる知識よりも、ずっと優れている。ご都合主義の教育機関や研究機関は、この事実を必死に隠しつづけているが。
次に、この考え方を、政策決定、とかいう似非概念に当てはめてみよう。
アンタイオスなきリビア
ふたつ目のエピソード。先ほどの逸話から数千年後、私がこの文章を書いている時点で、アンタイオスが暮らしていたとされる地、リビアには、奴隷市場が存在する。独裁者を排除する」ためのいわゆる トン政権交代、 が失敗に終わった結果だ。実際、2017年時点で、駐車場に設けられた即席の奴隷市場では、捕らえられたサハラ以南のアフリカ人たちが最高入札者へと売り渡されている。
2003年のイラク侵攻や2011年のリビア最高指導者の排除を推し進めた「干渉屋」と呼ぶべき連中(本書の執筆時点で活動しているヤツらの名前を何人か挙げるとすれば、ビル・クリストル、トーマス・フリードマン など)は、シリアなどの別の国々に対しても、似たような強制的な政権交代を支持している。
*1 干渉屋にはひとつ、大きな共通点がある。十中八九、ウェイト・リフターではない。
こうした干渉屋や、アメリカ国務省のお仲間たちは、反体制イスラム教組織の誕生、訓練、支援に手を貸した。当初、彼らは穏健派、だったが、やがてアルカイダの一部へと姿を変えていった。そう、2001年9月1日のテロ事件で、ニューヨーク市のタワーを吹っ飛ばした例のアルカイダだ。アルカイダは、もともとアメリカがソビエト・ロシアと戦うために構築(あるいは育成)した^穏健な反体制派、によって構成されたのだが、干渉屋たちはどういうわけか、そんなことをすっかり忘れているらしい。こういう教養人たちは、これから説明していくとおり、影響の影響、そのまた影響……を考えるようにはできていないからだ。
つまり、私たちはイラクの政権交代という例の手段を試し、大失敗した。こんどはリビアで例の手段を試し、代わりに活発な奴隷市場が生まれた。だが、「独裁者の排除」という当初の目的は達成した。めでたし、めでたし――。もしこんな道理がまかり通るなら、医者は患者のコレステロール値を改善するために、〝穏健、ながん細胞を注入し、患者の死後、検屍でコレステロール値が大きく改善したのを見て、自信満々で勝利を宣言する、なんてことになる。だが、私たちの知る医者は、死につながる `治療”を患者に施したりはしないし、するとしてもこんなに雑な方法は取らない。理由は明白。ふつう、医者はある程度の身銭を切っているし、複雑系について漠然と理解している。そして、数千年間かけて少しずつ築き上げられてきた医者の行動規範なるものを身につけているからだ。
だからといって、論理、知性、教育に愛想を尽かすのは間違っている。2次的、3次的な影響についてちょっと論理的に考えれば、今までの経験的証拠をすべて否定する方法でも見つからないかぎり、政権交代が奴隷制度の復活のような国家の衰退を後押しするということはすぐにわかるからだ(それが今までの典型的な結果だから)。つまり、干渉屋たちは実践感覚に欠けていて、歴史から何も学び取らないばかりか、純粋な推論すらまともにできない。ヤツらは、流行語まみれの巧妙であいまいな議論を用いて、純粋な推論を覆い隠してしまうのだ。
干渉屋の欠陥は3つある。(1)動ではなく静で物事を考える。(2) 高次元ではなく低次元で物事を考える。(3)相互作用ではなく行為という観点で物事を考える。こうした愚の骨頂の教養人(もっというと似非教養人)が頭のなかで行う推論の欠陥については、本書全体を通じてより詳しく見ていく。今の段階では、先ほどの3つの欠陥を具体的に述べるにとどめよう。
干渉屋のひとつ目の欠陥は、ヤツらが2次的な影響という視点で物事を考えられず、しかもその必要性にすら気づいていないという点だ。モンゴルの農民、マドリードのウェイター、サンフランシスコのロードサービス・オペレーターならほとんど誰でも、実生活には2次的、3次的、4次的、n次的な影響があると知っている。
ふたつ目の欠陥は、多次元的な問題と、それを1次元的に表現したものとの区別をつけられないという点だ。たとえるなら、多次元的な健康と、コレステロール値だけを下げることとの区別がつかないのだ。経験的にいって、複雑系には明白な1次元の因果関係のメカニズムはなく、不透明性のもとではそういうシステムにちょっかいを出してはならないということを、干渉屋たちは理解できない。この欠陥の延長線上として、ヤツらは独裁者』の行動を、現地ではなくノルウェーやらスウェーデンの政府の長の行動と比較してしまう。
3つ目の欠陥は、攻撃されることでかえって力を増していく人々の進化や、介入の反動として生じる問題の拡大を予測できないという点だ。
他人の命で遊ぶ――Ludis De Alieno Corio
そうして、いざ目論見が破綻すると、干渉屋たちは(ものすごく)頑固な男が書いた本にちなんで「ブラック・スワン」(影響の大きな想定外の出来事)と呼ばれている現象を持ち出してきて、不確実性がどうのこうのと騒ぎ出す。だが、ヤツらは結果が不確実性に満ちている場合にはシステムに余計なちょっかいを出すべきでないということをまるで理解していないし、もう少し一般的にいうと、結果が予測できない場合にはダウンサイド(潜在的損失)の大きな行動は避けるべきだということも理解していない。
ここで重要なのは、そのダウンサイドが干渉屋自身には何の影響も及ぼさないという点だ。干渉屋は、車2台分のガレージがあり、1匹の犬がいて、平均2・2人いる過保護な子どもたちのために作られた殺虫剤不使用の芝生の遊び場がある、エアコンの効いた郊外の家でくつろぎながら、性懲りもなく干渉を続けるのだ。一方で、非対称性をまるで理解できない愚鈍な人々に、飛行機の操縦を任せたらどうなるだろう。経験から教訓を学び取れず、理解不能なリスクを進んで冒すような無能なパイロットは、多くの人々の命を危険にさらすだろう。ただし、そういう無能なパイロットであれば、たとえばバミューダ・トライアングルのもくずと消えるだろうから、他人や人類を危険にさらすことはない。
ところが、知識階級と呼ばれている連中は、まったく深みのない近代主義的なスローガンを繰り返すくせに(たとえば、一方では首狩り族たちを応援しつつ、一方では「民主主義」という単語を連呼したりする。彼らにとって、民主主義というのは大学院の研究テキストに出てきた概念にすぎない)、自分たちの行動が招いた結果に対する代償はいっさい払わない。したがって、必然的に、文字どおり頭のねじがはずれた妄想人間たちが集団に居座りつづけるはめになる。一般的に、近代主義的な抽象概念を連呼する人間は、一定の教育を受けてはいるが(ただし、十分には受けていないか、受ける分野が間違っている)、説明責任はほとんど負わない。
こういうエアコンの効いた快適なオフィスに座っている干渉屋たちの失敗のツケを払わされたのは、ヤジディ教徒、近東(および中東)の少数派キリスト教徒、マンダ教徒、シリ
ア人、イラク人、リビア人といった罪のない人々だ。この状況は、これから説明するように、聖書が編纂される前、バビロニアの時代から続く正義の概念に反するし、人類が生き長らえてきたよりどころとなる倫理構造にも反する。
医師の場合と同じように、介入の第一原則は、「何よりもまず、害をなすなかれ(primum non nocere)」だ。もっといえば、「リスクを負わぬ者、意思決定にかかわるべからず」と言うこともできるだろう。
さらにいうと、
「人間は昔から愚かだったが、世界を破滅させるほどの力は持っていなかった。今は持っている。」
こうした干渉屋たちの「和平、プロセスが、いかにしてイスラエルとパレスチナのような数々の行き詰まりをもたらしてきたのかについては、またあとで。
人民の庇護者でなければ、貴族たりえない
この「身銭を切る」という概念は、歴史に織りこまれている。歴史的に、武将や戦争屋たちはみな自分自身が戦士であり、いくつかの面白い例外を除けば、社会はリスクを転嫁する連中ではなく、リスクを冒す人々が統治してきた。
過去の偉人たちは、一般市民よりはるかに大きなリスクを冒した。ローマ皇帝の背教者ユリアヌスは、皇帝在位中、ペルシア戦線の果てしなく続く戦いで命を落とした。ユリウス・カエサル、アレクサンドロス大王、ナポレオンについては、伝説作りの好きな歴史家たちのせいで、真相は予測の域を出ないが、ことユリアヌスに関していえば証拠は歴然としている。ペルシア兵の槍を胸に受けたユリアヌスほど、最前線で戦った皇帝の歴史的な証拠としてはっきりしているものはない (ユリアヌスは鎧を着けていなかった)。
ユリアヌス以前のローマ皇帝のひとり、ウァレリアヌスも、ペルシア戦線で捕虜となり、ペルシア王のシャープール1世が馬に乗るときの踏み台にされたといわれている。
また、東ローマ帝国最後の皇帝、コンスタンティノス1世パレオロゴスは、紫色の着衣を脱ぎ去り、イオアニス・ダルマトスといとこのテオフィロス・パレオロゴスに加勢すると、剣を頭上に振りかざし、トルコ軍のなかへと斬りこみ、避けられぬ死に堂々と向きあった。しかし、コンスタンティノス1世は降伏と引き換えに取引を持ちかけられたという説もある。そんな取引は、誇りある王たちにはふさわしくない。
これらは特殊な逸話ではない。私のなかの統計理論家は、こう確信している。ベッドの上で死を迎えたローマ皇帝は、3人にひとりにも満たない。さらに、高齢で亡くなったその数少ない皇帝も、もっと長生きしていれば、クーデターや戦闘で命を落としていただろう。
今日でさえ、君主は肉体的なリスク・テイクを求める一種の社会契約から、自分自身の正当性を得ている。イギリス王室は、1982年のフォークランド紛争の際、王室の成員のひとりであるアンドルー王子に,平民、よりも高いリスクを負わせ、戦線でヘリコプターを操縦させた。なぜか? いわゆる高貴たる者の義務というやつだ。元来、貴族の地位は、名声と引き換えに個人的なリスクを負い、ほかの人々を守ることで得られるものだった。王室は、奇しくもその社会契約をまだ覚えていた。人民の庇護者でなければ、貴族たりえないのだ。
ロバート・ルービン取引――隠れた非対称性とそのリスク
戦士をトップに据えないことが、文明だとか進歩だと思う人もいる。それは違う。
「官僚制度とは、人間が自分自身の行動の責任を取らなくてもいいようにするご都合主義の構造である。」
また、こんな疑問を持つ人もいるかもしれない。中央集権制度には、失敗の代償を直接負わない人々が必ずいる。だとしたら、いったいどうすればいいのか?
システムを分権化(もう少し丁寧にいえば局所化)するよりほかに選択肢はない。失敗の代償を背負わなくてすむ意思決定者をなるべく少なくするしかないのだ。
「分権化は、ミクロなたわごとよりもマクロなたわごとを言うほうが易しいという単純な事実を背景にして起こる。」
「分権化は、構造上の巨大な非対称性を和らげる。」
ただ、心配はいらない。私たちが分権化や責任の分散を行わなくても、分権化はひとりでに起こる。それも、痛みを伴う形で。身銭を切るという機構が備わっていないシステムは、不均衡が累積していくと、やがて吹っ飛び、分権的な形で自己修復する。もし絶滅を免れれば、の話だが。
たとえば、2008年、隠れた非対称のリスクがシステム内に累積した結果、銀行が吹っ飛んだ。リスク転嫁がお得意な銀行家たちは、特定の種類の爆発的リスクを隠して安定した儲けをあげ、教科書のなかでしか成り立たないような学術的なリスク・モデルを使い(学者はリスクについて無知も同然なので)、いざ銀行が吹っ飛ぶと急に不確実性(目に見えない予測不能なブラック・スワンと、例のものすごく頑固な作家)の話を持ち出してきて、過去の収入はちゃっかりそのまま懐に収める。これこそが、私のいうロバート・ルービン取引だ。
ロバート・ルービン取引?元アメリカ合衆国財務長官のロバート・ルービンは、国民がコーヒー代の支払いに使う紙幣に署名の入っている財務長官のひとりだが、2008年の銀行崩壊に先立つ10年間で、シティバンクからなんと1億2000万ドル以上をかき集めた。
訳注1 アメリカで発行されるドル紙幣には、在任中の財務長官の署名が印刷される。
ところが、シティバンクが文字どおりの支払不能に陥り、納税者による救済を受けても、彼は不確実性を言い訳として持ち出し、小切手に署名しなかった。表が出れば大儲け。裏が出れば「ブラック・スワンだ」と大騒ぎ。ルービンは、納税者にリスクを転嫁したことさえ認めなかった。そうして、スペイン語文法の専門家、補助教員、ブリキ缶工場の現場監督、菜食主義の栄養アドバイザー、地方検事補の事務官といった人々が、彼のために”損切り”を行った。要は、彼のリスクを引き受け、彼の損失を穴埋めしたわけだ。
しかし、最大の犠牲者は自由市場だ。もともと資産家を毛嫌いしていた一般大衆が、自由市場と高次の腐敗や縁故主義を混同するようになったからだ。実際には、ふたつはまったく逆のものだ。救 済という仕組みによって腐敗や縁故主義を可能にしているのは、市場ではなく政府なのだ。救済だけでなく、一般的に政府の介入そのものが、身銭を切らなくてすむシステムを生み出している。
一方で、朗報もある。レントシーキングに勤しむ銀行家や銀行業界の保護に加担したオバマ政権の努力とは裏腹に、リスク・テイク業界は「ヘッジ・ファンド」と呼ばれる独立した小さな構造へと移ろいはじめたのだ。
*2 「レントシーキング」とは、保護目的の規制や、利権”を利用して、経済活動になんら貢献することなく、つまりほかの人々の富を増やすことなく、収入を得ようとする行為。数ページ後に登場するデブのトニーがいうように、保護による経済的恩恵をまったく受けることなく、マフィアにみかじめ料を払わされるのと似ている。
こうした動きが起きたのは、主に銀行システムがあまりにも官僚化しすぎたせいだ。官僚たち(仕事といえば書類仕事だと思っている連中)は、銀行を規則でがんじがらめにしたが、どういうわけか、その何千ページという追加の規制のなかで、身銭を切るという概念はみじんも考慮されていなかった。一方、分権化されたヘッジ・ファンドの場合、オーナー経営者が純資産の半分以上を自身のヘッジ・ファンドに投じているので、顧客と比べて高いリスクにさらされている。もし船が沈めば、自分も一緒に沈む運命にあるのだ。
システムは排除によって学ぶ
さて、本書のここぞというセクションをひとつだけピックアップするとすれば、間違いなくこのセクションだろう。干渉屋の事例は、本書の物語の核とでもいうべき部分である)影響の両方を及ぼすことを示しているからだ。これまで見てきたように、干渉屋たちがいつまでたっても学習しないのは、ヤツらが失敗の被害をこうむっていないからだ。「痛みは学びを助く(pathemata mathemata)」のところで示唆したとおり、
「リスク転嫁のメカニズムは、学習も妨げる。」
もう少し実践的な言い方をするなら、
「相手が間違っていることを言葉で完全に納得させることはできない。それを思い知らせることができるのは、現実だけ。」
いや、正確にいえば、現実は議論に勝とうなどとは思っちゃいない。重要なのは、生き残ることだ。
つまり、
「現代性の由々しき側面とは、理解するよりも説明するほうが得意な人間がうじゃうじゃと増殖しているという点だ。」
あるいは、「行動するよりも説明するほうが得意」といってもかまわない。
要するに、「学習」とは、学校という名の厳重警備の刑務所のなかで行われる囚人教育とは似て非なるものだ。生物学でいえば、学習とは、世代間の自然選択というふるいを通じて、細胞レベルに刷りこまれるものだ。身銭を切るという行為は、抑止力というよりもこのふるいに近いと私は考えている。そして進化は、絶滅リスクが存在しないかぎり起こりえないものなのだ。さらにいえば、
「身銭を切らないかぎり、進化は起こりえない。」
この最後のポイントは、明々白々だ。ところが、進化論は擁護するくせに、身銭を切ったりリスクを分担したりしたがらない学者はごまんといる。彼らは全知全能の創造主による設計”という概念は否定するくせに、自分はまるで全知全能であるかのように何かを設計、しようとする。
一般的に、人は神聖なる国家(または大企業でも同じ)を崇拝すればするほど、身銭を切ろうとしなくなる。自分の予測能力を信じれば信じるほど、身銭を切ろうとしなくなる。スーツとネクタイを着ければ着けるほど、身銭を切ろうとしなくなる。
干渉屋の例でも見たとおり、人間は自分自身や他者の失敗からそれほど多くを学ばない。むしろ、学習するのはシステムのほうだ。システムは、特定の種類の失敗を犯しにくい人々を選択し、そうでない人々を排除することで学習していく。
「システムは部分を排除することによって、つまり否定の道によって学ぶ」
*3 「否定の道」とは、何が正しいかよりも何が間違っているかのほうが明瞭であるという原則。言い換えれば、知識は引き算によって膨らんでいくという原則。また、何がおかしいのかを理解するほうがその解決策を見つけるよりも易しいともいえる。何かをつけ加える行動よりも、何かを取り除く行動のほうが頑健である。なぜなら、何かをつけ加えると、目に見えない複雑なフィードバック・ループを生む可能性があるからだ。この点については、『反脆弱性』である程度詳しく論じている。
先ほども触れたとおり、無能なパイロットの多くは、とっくのとうに大西洋の底に沈んでいるし、危険な悪質ドライバーの多くは、美しい並木道に彩られた地元の静かな墓地に埋葬されている。交通システムが少しずつ安全になっていくのは、人間ではなくシステムが失敗から学ぶからだ。システムは人間と異なり、ふるい分けに基づいて経験を積み重ねていく。
これまでの話をまとめると、
「身銭を切るという行為が、人間の傲慢さを抑制する。」
さて、プロローグその2ではもう少し突っこみ、対称性という概念について考えてみよう。